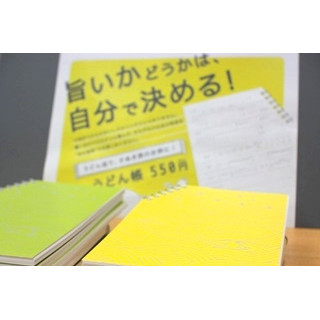群馬県桐生市の「ひもかわうどん」と埼玉県鴻巣市の「こうのす川幅うどん」は、幅広の麺が特徴の見た目にもインパクトが強いご当地グルメです。一見、同じ料理のようにも思えるこのふたつのうどんですが、麺の幅はどちらが太いのでしょうか?
それぞれの特徴を紹介しつつ、探っていきます。
※以下、紹介する各店ともに、掲載情報は2019年7月時点でのものとなっています。営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、詳細はご来店前に店舗にご確認ください
群馬の伝統グルメ「ひもかわうどん」とは?
ひもかわうどんは桐生市に伝わる郷土料理
ひもかわうどんは、群馬県の東部に位置する桐生市に伝わる郷土料理です。薄く伸ばした幅広の麺がひもかわうどんの特徴で、つるっとした喉ごしともちもちっとした食感が楽しめます。
もともとは冬によく食べられていたというひもかわうどんですが、現代では、冷たいざるうどんなども登場しており、食べ方のバリエーションが豊富になっています。麺の幅は、広いものでは10cm以上になるものもあるそう。
群馬県は、もともと小麦粉の生産地として知られており、「地粉(じごな)」と呼ばれる国内産の小麦粉が今でも作られています。そのため、地粉を用いた多彩な料理が昔から数多く作られてきました。ひもかわうどんも、そのうちの1つ。
そのほかにも、幅広の麺を味噌または醤油味の味付けで煮込んだ「おっきりこみ」や、コシの強い食感が特徴の「水沢うどん」、素まんじゅうを焼け串に刺して炭火で焼き、甘辛の味噌を塗って仕上げる「焼きまんじゅう」なども有名です。
埼玉県鴻巣市の「こうのす川幅うどん」とは?
川幅日本一で町起こし
群馬県のひもかわうどんとよく似た見た目をしているのが、埼玉県の鴻巣市の名物こうのす川幅うどんです。
このうどんが誕生したのは、鴻巣市~吉見町間を流れる荒川の川幅(=河川敷も含めた両岸の堤防から堤防までの距離のこと)が2,537mあり、日本一の川幅として国土交通省に認定されたことがきっかけだったのだそう。
2009年に誕生した「こうのす川幅うどん」
その“川の幅”にちなんでうまれたのが、こうのす川幅うどん。なんでも、”川幅日本一”を町おこしのテーマに掲げた鴻巣市が、市内の飲食店にうどんの開発を依頼して2009年に誕生したのがこのうどんなのだそう。ちなみに鴻巣市では、川幅グルメとして、パスタやハンバーグ、漬物、和菓子などでも川幅をテーマにしたものを開発しているそうです。
川幅うどんの食べ方は、魚介ダシが利いた汁を味噌味でアレンジした温かい「川幅味噌煮込みうどん」や、だし汁と一緒につるっと食べられる冷やしうどんなどが主流。川の流れをイメージして作られているという麺は、麺の幅が5~8cmほどあり、強めのコシともちっと食感が特徴です。
【合わせて読みたい】 : 幅広さでは負けない! 埼玉県の川幅日本一の町ではあらゆるグルメが幅広に…
ひもかわうどんとこうのす川幅うどん、どちらが太いのか
材料は同じでも、食感は別物!
古くから続く粉ものの食文化の中で生まれたひもかわうどんと、町おこしの一貫として誕生したこうのす川幅うどんは、ほぼ同じ素材を使って作っています。しかし、その見た目や作り方こそ似ているものの、それぞれの味わいは別物です。
たとえば、食感。薄くてつるっと食べられるひもかわうどんに対して、より厚みのあるこうのす川幅うどんはコシが強いのが特徴です。
太いのはどっち?
それでは、ひもかわうどんとこうのす川幅うどんは、いったいどちらが太いのでしょうか?
ひもかわうどんの老舗「ふる川」で提供されているひもかわうどんは、最大幅が約12cmあるとのこと。これは、通常のうどんの幅を4mm程度とすると、約30倍もの幅があることになりますね。
一方、こうのす川幅うどんの有名店「久良一(くらいち)」では、川幅みそ煮込みうどんに使用するうどんが約5.5cm、冷製 川幅うどんには約7cmのうどんを使っているそう。喉越しがいいひもかわうどんに比べると、生地にコシがあり噛み締めながら麺そのものの風味をじっくり味わえます。
ほかには、「長木屋」というお店では、11.5cmのこうのす川幅うどんが提供されているということがわかっています。
ここまで来ると、それぞれのうどんの太さはお店によって異なるため、太さについてはほぼ互角でどちらが太いという判断はできなさそうですね……。