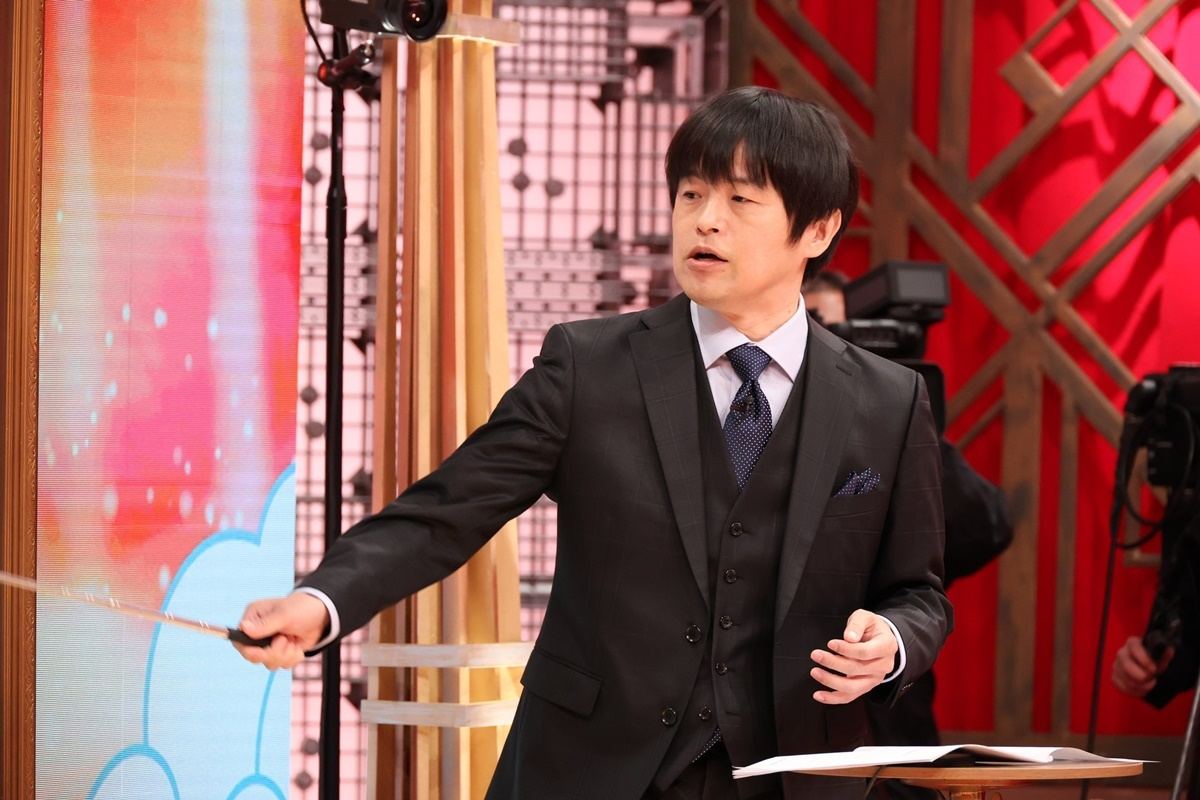印象的な番組名を挙げていくと、当時では珍しいマーケティングを掘り下げた『マーケティング天国』、市場を歴史に置き換えて解釈していく『カノッサの屈辱』、静止画を背景に官能小説を朗読する『曼荼羅図鑑』、視聴者置き去りのカルトクイズで競い合う『カルトQ』、哲学でさまざまな事象を考察する『哲学の傲慢』、映画の撮影技法をフィーチャーした『アメリカの夜』、芸術と裁判を掛け合わせた『宣誓』、体や病気を過激に深掘りした『完全人体張本』、文学作品の予告編を放送する『文學ト云フ事』、一般人1,000人にインタビューを重ねる『インタビューズ』などがあった。
まだまだ挙げればキリがないし、「くだらなさ優先か、教養寄りか」の違いこそあるが、「スタッフがやりたいことを愚直に追求する」というスタイルは同じ。だからこそ、その愚直さが視聴者に乗り移るような形で盛り上がりが生まれていた。『私のバカせまい史』はそんなフジテレビの四半世紀における“バラエティ史”を感じさせる番組であり、しかもゴールデンタイムでレギュラー化したところが意義深い。
平成中期あたりから後期にかけて、いつのまにか同番組のような「せまい」を狙った企画は、「テレビ東京の十八番」という印象に変わっていた。それ以外の主要4局で放送されるとしても、ほとんどが視聴率の不安が少ない深夜帯やBS・CS。ゴールデンタイムでのレギュラー化はハードルが高かった。
しかし、フジテレビがそんなハードルを乗り越えてゴールデンタイムのレギュラー番組として放送することで、「せまい」ながらも「より深い」ところまで掘ったものを制作できる。言わば、フジテレビとゴールデンタイムだからこそのスケール感を出せることになり、それは『JOCX-TV2』から続く同局のイズムであり、意地のようなものなのかもしれない。
ただ気がかりなのは、フジテレビの象徴であったスターを軸にしたバラエティが不発続きであること。他局も厳しい状況ではあるものの、フジテレビがバラエティのトップを走っていた頃のような影響力の大きい番組は見当たらない。
その意味で『まつもtoなかい』への期待は大きく、この番組がスターを軸にしたバラエティとして輝きを放てば、『私のバカせまい史』の魅力も、より伝わりやすくなるのではないか。早ければ半年後、1年後に「同じ2023年春スタートの両番組がフジテレビを支えている」という状態にしていきたいところだろう。