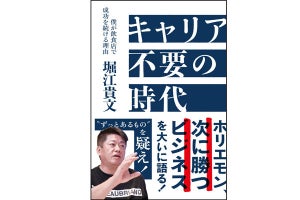労働生産性がどういうわけか伸びない国、「日本」
バブル崩壊以降、日本の給与水準はまったく上がっていないまま、世界の水準から取り残されている。その事実が問題であることに、今、多くの人が気づき始めています。
かつてはジャパン・アズ・ナンバーワンと言われることもあった日本ですが、バブル崩壊後はその勢いをなくし、取り戻せないままにリーマンショックを経て今に至ります。
気がつけば、OECD(経済協力開発機構)の調査による平均年収ランキング(2020年)で22位。1位のアメリカには程遠く、おとなりの韓国の19位にも及びません。
他の競合国がこの数十年の間に急速に生産性を伸ばしている中で、日本も懸命の努力は続けているのですが、その努力もバブル崩壊後の生産性の伸びにはほとんど結びついてはいない、という厳しい現実があります 。
生産性とは、投入した資源(労働など)に対する創出した「付加価値」の割合です。より少 ない資源からより多くの付加価値が得られるほど、より生産性が高いという関係になります。生産性を高めるのは、豊かな社会を創り上げるためであり、そのためには無駄な「動き」を減らし、価値を生み出す「働き」の部分を増やすことが必要なのです。
日本の企業の現場に目をやれば、みんなまじめに一生懸命「動き」をしています。それなのに生産性は伸びず、給料も上がらない。国を挙げての「働き方改革」も思うような成果が見えない。どこか「あきらめ感」さえ漂っているのが日本の現状ではないでしょうか。
「職務に忠実な勤勉さ」が停滞を生む
努力は必死に続けているにもかかわらず、給料の水準は伸びていない。この厳しい現実は、努力の方向性が無駄な「動き」になっていることを示しています。その根源にあるのは、高度経済成長期以来、日本の得意だった経済モデルが通用しなくなってしまったことです。
すなわち、日本の代わりを圧倒的に安い人件費という経済モデルでやってしまう国々が、一瞬のうちに世界市場を席巻してしまったのです。
一方、世界では、米国を中心にデジタル化が急速に進んでいきました。日本も相応の努力はしているのですが、結果として見れば、一歩も二歩も後れを取っています。確かに、個別には素晴らしい結果も残してはいるのですが、残念なことに全体として見れば、新しい価値を生み出せていないのが日本の実態なのです。
新しい価値を生み出そうと思うとき、私たちにいちばん必要とされているのが「創造性」です。しかし、それがうまくいっていません。
なぜ創造性というものが何よりも大事にされていないのか。それは、みんなの力を合わせてものづくりに励む、という経済の高度成長を支えてきた旧来の考え方ややり方、言うなれば、ある種の文化が今もそのまま残っているところに問題が潜んでいるからです。
私たち日本人はまじめで勤勉であるという特性を持っています。日本の高度経済成長に大きく寄与したのもこの勤勉さと言えます。実はそこに問題が隠されている、ということです。
つまり、「日本経済の高度成長を支えてきた、日本人が持つ職務に忠実な勤勉さこそが、今の停滞の主因になっている」というのが、約30年にわたって日本企業の変革の現場に身を 置いてきた私がたどり着いた結論なのです。
「勤勉」がもたらす「思考停止」のワナ
高度成長期には、欧米をお手本にしながらの、日本人の勤勉さを生かした質の高いものづくりが日本に繁栄をもたらしました。
しかしながら、昭和の時代が過ぎ平成に入ると、合理化が進み安定志向が強まります。そうした中で現代の「職務に忠実な勤勉さ」がもたらす「思考停止」が蔓延し弊害をもたらしてくるのです。
「思考停止」と言っても何も考えていないということではありません。ひとことで言えば、無自覚に置かれている前提を問い直さずに、「どうやるか」しか考えない姿勢のことです。
広く日本の社会に根づいている、ただ規範に何も考えずに従う「思考停止」という特性をどのように扱えばよいのか。この特性を自覚することからスタートし、コントロールすることができるなら、私たちの将来も変わってくるのではないか、と思うのです。
揺るがない前提を堅持している限り仕事の処理は簡単で効率的です。ただ「どうやればいいのか」だけを考えておけばいいからです。
しかし、今の日本が喉から手が出るほど必要としているのは、目先の安定、従来のビジネスモデルの維持ではなく、新しい価値を創造していく新たなビジネスモデルの構築なのです。新しい価値を生み出そうと思えば、前提そのものを問い直す姿勢が何よりも必要です。
前提を問い直そうと思えば、「前提が持つ意味、めざす目的、それが生み出す価値」などを考えることが不可欠です。この前提を問い直す姿勢が欠如しているから、日本には、「変えなければ」と言い続けながらも、結果としてまったくと言ってもいいほど変わっていない現実が存在するのです。
ビジネスモデルが安定してきた会社であればあるほど、お客様に直接使う時間よりもはるかに多くの時間を勤勉に無駄な仕事に割いています。間違いが起きることがないよう、作法 の通り面倒な手続きを踏みながら、すべての仕事を制約の範囲内でただまじめに処理していく姿がそこにはあるのです。
つまり、置かれている規範の中で「余分なことは何も考えずに」ただひたすら仕事をさばく、という「思考停止」の状態です。
この「思考停止」から抜け出し、仕事のしかたを変え、新しい価値を生み出していかなければ、生産性は伸ばせません。ひいては給与水準も上がらない状況が続くことになるのです。
そうならないように、日本人の強みでもある「勤勉さ」を進化させることで、日本企業に、そして、そこで働く皆さんに、もう一度活力を呼び戻してほしい。
本特集では、「思考停止」から脱却し、働く人生を豊かなものにする処方箋について、一緒に考えてみたいと思います。
著者プロフィール:柴田昌治(しばた・まさはる)
|
|
株式会社スコラ・コンサルト創業者。30年にわたる日本企業の風土・体質改革の現場経験の中から、タテマエ優先の調整文化がもたらす社員の思考と行動の縛りを緩和し、変化・成長する人の創造性によって組織を進化させる方法論「プロセスデザイン」を結実させてきた。最新刊に 『日本的「勤勉」のワナ まじめに働いてもなぜ報われないのか』(朝日新聞出版)。