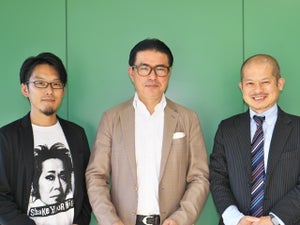1分トークコンサルタントとして活躍している、沖本るり子氏。30代前半で取締役となり、人間関係に頭を悩ませた同氏がたどり着いたのは、円滑なコミュニケーションに求められる第一条件が「話を1分以内にまとめること」であるという事実だった。また、自身でセミナーなどを行う中で「共感をスキルとして捉える」という発想も見出したとのこと。本稿では「プレゼンの達人」とも称される沖本氏に、若いビジネスパーソンの人脈作りのヒントを伺っていく。
聞き手は、マイナビニュース別稿で"人脈"についての対談を行った、ビジネスプロデューサー・書評ブロガーの徳本昌大氏、IT企業 Sansanで"コネクタ"の肩書きを持つ日比谷尚武氏の2名。人との付き合い方を考え続ける3氏の対談から、人脈構築術について考えてみたい。
コミュニケーションに苦労した過去
現在ではコミュニケーションに深く関わる仕事を行っているが、昔はコミュニケーションの“コ”の字も知らなかったという沖本氏。普段の会話では広島弁が飛び出ることも相まって、周りからは怖い人と思われがちだと自身について述べる。
そんな同氏が、コミュニケーションを円滑にするためにとっている行動のひとつを紹介してくれた。それは、オレンジの服を着ること。ビジネスでオレンジの服を着ている人は珍しいので、人目を引くし印象にも残る。そして、名刺交換の際に「“オレンジの”沖本です」と一言沿えるのだという。これで、相手にはオレンジの服を着ている人=沖本さんというイメージが根付く。
この話からもわかるように、沖本氏は独自のメソッドでコミュニケーションを考え、人と組織を育てる専門家だ。その知見は、大企業で働いた後、管財商社で業務改善・業務改革に携わり、30代前半で取締役になったものの部下との行き違いなどで一度会社を倒産させてしまったという経歴から生まれた。
感情的な会話も論理的(ロジカル)に
「自主的に私のセミナーにいらっしゃる方は、『共感する』『褒める』という感情の部分を苦手とする“論理的な人”が多いようです。しかし、相手の感情に注目し、自分も感情を使おうと考えること自体が論理的な発想なのです。感情を活用するスキルを身に付けましょう」
沖本氏も、感情を数値化する検査を受けた時に低い数値が出た“共感値が低いタイプの人間”であり、周囲には「怖い」「冷たい」と言われてきたという。しかし、自分を変えたいと思ったところで、周りが喜んでいても嬉しいと思えないし、悲しんでいても悲しいと共感することはできない。
それでも「沖本さん、すごく共感されますね」と言われることは稀にあった。それはなぜなのか……。沖本氏はそういった状況を分析し、「共感とはスキルだ」という気付きを得た。
「人は、自分の感情を動かすことはできません。しかし、他人を励ますことはでき、傷つけることもできます。他人の感情は動かせるんですよ」
論理的に感情を活用すれば、相手の気持ちをプラスにし、想像以上の働きをしてもらえる。もちろん、動かそうと思ったら恐怖で相手を動かすこともできる。ただし恐怖では、期待値以上の動きはしてくれないのだという。
相手の気持ちを動かすためには
それでは、相手の気持ちをプラスにするためには、具体的にどのような行動をとればいいのだろうか。沖本氏は、わかりやすい例として上司とのコミュニケーションを挙げる。若いビジネスパーソンほど、上司や同僚にうまく動いてもらわないと自分の仕事もうまくいかない。
「上司に気持ちよく動いてもらうために、褒めるという行動をとる人は多いでしょう。しかし、褒めるのは良くありません。それは上から目線だから。例えば、相手が身に付けているものを褒めたいと思った場合、相手の気持ちをプラスにするためには『どこで購入されたんですか? 』といった質問をするといいんです。質問とは、教えを乞うということであり、下から目線です。相手が自慢できる空気を作っていくようにしましょう。自慢話は気持ちが良いのです」
褒めるも共感するも相手次第であり、相手が感じること。興味を持ってもらえたと感じるような会話をすれば、相手は想像以上の動きをしてくれるのだという。
気を付けたほうが良い言葉
若い人に限らず、「なるほど」という言葉は相槌の定番文句となっている。しかし沖本氏は、「なるほどという言葉もまた上から目線に取られることがあるので、使わないほうが良い」と説明する。つい使ってしまいがちな言葉だが、年配の方ほど不快に思う人は多く、悪気はないと理解していても、気分は良くないのだそうだ。うっかり口にしてしまったときは「なるほど、おっしゃる通りですね」といった形でフォローすることを同氏は勧める。
「ただし、言葉というのは時代とともに変わっていくものです。例えば『すばらしい』という言葉は、江戸時代にはマイナスの意味を持った言葉だったのですが、現代ではプラスの意味を持つ言葉になっています。『なるほど』という言葉も今後はそのように変化していくのではないでしょうか」
すべては相手の解釈次第。本人が良かれと思ったり、問題ないと思ったりして選んだ言葉でも、受け手がマイナスの印象を受けると、気持ち良く動けなくなるのだという。
誘いを断るときはお詫びから入らない
「今度、一緒に飲みに行きませんか? 」ビジネスパーソンなら、このようなお誘いを受ける機会はいくらでもあるだろう。そんなお誘いを断らねばならないとき、どのように返事をしているだろうか。
例えば、「ごめんなさい」という言葉から入る人は少なくないはずだ。しかし、このようなお詫びの言葉は相手にマイナスの印象を与えるという。最初に返すべきは「ありがとうございます」。「すみません」「ごめんなさい」という言葉はいくつかの意味を持っているため、感謝の言葉に置き換えたほうが良いと沖本氏は言う。誘った側も「ありがとうございます」と言われると、また誘おうかという気分になる。
「お詫びが必要だとしたら、誘いに応じたのにキャンセルする必要が生じた時です。お誘いを受けた時点ではお互いにイーブンです。詫びられると、相手は『無理な誘いをして謝らせてしまった』という印象を抱き、次の誘いをしづらくなってしまいます」
さらに、興味がないのに常套句として「またお誘いください」と言ってしまうのも良くない。興味があるようであれば、誘う側はまたその人を誘うだろう。
「相手に『期待値の空振り』をさせないようにしましょう。興味がないのであれば相手は他の提案をしてきますから、他のことで誘ってほしいと素直に言ったほうが良いのです」
人脈とは何人もの人が連なっていくもの
若いビジネスパーソンがすぐにでも活用できる、具体的なアドバイスをする沖本氏。同氏は最後に、人脈とはなにか、どのようにしてできていくものなのかを語ってくれた。
「人脈は山脈と一緒で、何人もの人が連なっていくものです。誰か新しい人と出会ったときは、“つなげることで何かが生まれそうな”他の人とつなげるようにしています。例えば、紹介された仕事を終えた時に、そこで出会った人をさらに別の人に紹介することで人脈をつなげていきます。人脈は、連なることで大きな広がりを見せてくれるのです」