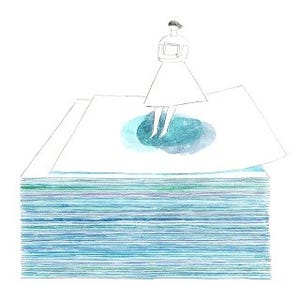芙美子が典洋と恋愛関係になったのは、わりと急なことだった。芙美子は今の職場に転職する前の仕事の関係で、典洋を知っていた。8歳も年下の、仕事ができると評判の典洋には婚約している女がいることも知っていた。
自分とは無関係の、「上」にいる男だと、独身で稼ぎも良くない自分とは違って、仕事もできて当たり前に結婚もする男なのだということが、芙美子を油断させた。
どういうつもりなんだろう、なぜ私なんかに興味を持っているんだろう、きっと彼にとっては珍しい人種なんだろうな、と思っているうちに、週に数回も典洋が家にやって来るようになった。典洋は、なついた犬のように屈託のない好意の表現をした。芙美子はそれを、遊び慣れた男の上手な甘え方だと受け取った。
結婚がしたかった。芙美子は38歳で、もういいかげん、実りのない恋愛を繰り返すことに疲れ果てていた。信頼できる男を見つけて、この人、と決めてしまいたかった。婚約者のいる典洋は、はなからその候補には入っていなかったが、無邪気に好意を示してくる典洋に、そんな気持ちを吐き出すのはためらわれた。
どうせ短い関係なのだから、黙っていようと思った。
典洋が家に来ているとき、芙美子は自分の携帯が鳴るのが気になった。画面を上にしていると、メールの相手の名前や、文章の最初のほうが表示されてしまう。
結婚するにはいいかもしれない、と思ってやりとりをしている相手がいることを、典洋には知られたくなかった。知られたら、と想像すると、なぜか典洋のひどく傷ついた顔が浮かんだ。
芙美子は携帯の画面をテーブルに伏せて置くようになった。そのことの言い訳のように、背面に金属のリボンの飾りがついたケースを買って、それを携帯に着けた。ケースのせいで表向きに置けないふうを装って、芙美子は携帯を伏せて置き続けた。いつしか、典洋も同じように携帯を伏せて置くようになっていた。
典洋から、もうやっていけないと思う、と言われたとき、芙美子はほっとした。いつ来るかわからない悲しみの瞬間がやっと来た、もうこれでその日が来ることにおびえなくて済むんだ、と、恐怖からようやく解放されるのだと思った。
「そうだね、結婚するんだもんね」
芙美子がそう言うと、典洋は、芙美子が以前想像した通りの傷ついた顔をした。
「いや、婚約破棄したから」
芙美子が言葉を失っていると、典洋は力のない笑顔を見せた。
「言ったでしょ、彼女とは別れる、俺が好きなのは芙美子さんだから、って。芙美子さんがいれば、何もいらないと思ってた。けど、芙美子さんはそうじゃなかったから、俺は、もう一緒にはいられない」
芙美子は、自分がどんなに間違った世界を見ていたのか、初めて知った。
先に信頼を裏切ったのは自分だった。相手を信頼しなかったのも自分だった。私とは違う人種だから、私とは釣り合わない人だから、と真剣に考えようとしなかった。卑屈さを胸の内で育んで、きれいなものがこの世にあることすら信じなくなっていた。
なぜ、こんな人間になってしまったのだろう。芙美子は自分のことが、初めて本気で嫌いになった。一人になった部屋で、芙美子はまずリボンのついたケースを外した。
結婚したい、という思いが、早くしてしまって安心したいという気持ちが、冬の強い風に吹かれる雲のように、すーっと遠くへ消え去っていった。愛して、相手の愛を受け止めたい。怖くても疑わずにいたい。なんの飾りもない強い気持ちだけが、芙美子の中に残った。
<著者プロフィール>
雨宮まみ
ライター。いわゆる男性向けエロ本の編集を経て、フリーのライターに。著書に「ちょっと普通じゃない曲がりくねった女道」を書いた自伝エッセイ『女子をこじらせて』、対談集『だって、女子だもん!!』(ともにポット出版)がある。恋愛や女であることと素直に向き合えない「女子の自意識」をテーマに『音楽と人』『SPRiNG』『宝島』などで連載中。マイナビニュースでの連載を書籍化した『ずっと独身でいるつもり?』(KKベストセラーズ)を昨年上梓。最新刊は『女の子よ銃を取れ』(平凡社)。
イラスト: 安福望