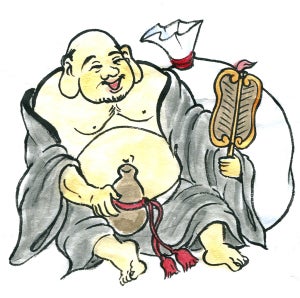日本には古来より八百万の神々がいるといわれていますが、その中でも七福神は人々から厚く信仰されています。その七福神で紅一点の「弁財天」(べんざいてん)は、仏教の守護神といわれています。
本記事では弁財天について、見た目の特徴やご利益、由来・歴史を詳しく解説。また、その他の七福神や、どこで祀られているのかもまとめました。
弁財天とはどんな神様?
弁財天(べんざいてん)は、仏教における守護神の一人で、七福神の中の一人でもあります。もともとはヒンドゥー教の女神であり、「サラスヴァティ―」と呼ばれるインドの聖なる川をモチーフにしているそうです。このことから水に関連する神様だと考えられていますが、現在ではあらゆることにご利益がある縁起物としても考えられているようです。
日本で弁財天は少し違う性質を持つ
日本の弁財天は、仏教を守護する天部のさまざまな神の一面を吸収しているため、インドや中国で言い伝えられている弁財天とは少し異なります。
神仏習合思想のひとつ「本地垂迹(ほんじすいじゃく)」という考え方では、弁財天は日本神話に登場する市杵島姫命(いちきしまひめ)と同一視されることが多いです。そのため、古くから弁財天を祀っている神社などでは、市杵島姫命を祀っている所も多くあります。
弁財天の見た目の特徴
弁財天の見た目は特徴的で、頭の上に白蛇をのせて鳥居がついた冠をかぶっています。弁財天は「宇賀神(うがじん)」という蛇神と習合したといわれています。この宇賀神は蛇の体に人間の顔を持つ神様で、そこから弁財天の頭の上にも蛇が乗るようになったとされています。さらにこの宇賀神は財福の神様とも言われていたようです。
ただ、弁財天と宇賀神の関係性については日本独自のものであり、インドや中国ではそのような言い伝えはありません。
弁財天の手に持っているものは戦うための武器がメインで、弓矢や宝剣、縄や斧などです。ここから戦う女神として認識されていたことがわかります。
しかし密教系の像では、武器ではなく楽器の琵琶を持った姿が多く見られます。この場合は戦う女神というよりかは、現代のような縁起物といった意味合いが強いのでしょう。
弁財天のご利益は
弁財天は七福神の一人として、単なる神様ではなく縁起物としても扱われています。
弁財天の名前に「財」という漢字が使われていることもあり、一般的に知られているのが金運アップや商売繁盛でしょう。
しかし、それ以外にも交通安全や恋愛成就、子孫繁栄や技芸上達、長寿といったご利益があるといわれています。弁財天は現世において幅広いご利益を授かれる、万能な神様なのです。
弁財天の由来・歴史
弁財天はヒンドゥー教に登場する神様でした。釈迦が始めた仏教が発展していく途中で取り入れられた神様だとも言われています。弁財天はインドで崇拝された川の神様で、水に関わることはもちろん学問や音楽などの芸術を司るとも言われていました。
もともとの表記では「弁才天」ですが、日本に渡ってきた後に財運の神様としての性格が与えられ、「弁財天」という表記になったそうです。
日本三弁天とは
上述した通り、弁財天は水に関連している女神なので、水に囲まれた場所で多く祀られています。その中でも、滋賀県にある竹生島、広島県にある厳島、神奈川県にある江の島が「日本三弁天」と呼ばれ有名です。
他の七福神について
七福神は弁財天の他にも、 恵比寿天、 大黒天、 毘沙門天、 福禄寿、 寿老人、 布袋尊 が存在します。
七福神を信仰すれば、七福神の七つの幸福を授けられ、七つの厄災が取り除かれると言い伝えられています。それぞれ異なった特徴を持っているので他記事も参考にしてみてください。
弁財天が祀られている場所は
弁財天のご利益を得るためにはどこに参拝しに行けばいいのでしょうか。弁財天が祀られている有名な神社やその姿を見られる場所を紹介していきます。
鎌倉国宝館「弁財天坐像」
鎌倉鶴岡八幡宮の近くにある国宝館には、1266年に奉納された弁財天が祀られています。琵琶を弾いているようなポーズを取っていますが、実際には琵琶は持っておらずポーズだけです。
この像ができた鎌倉時代には裸体彫刻という文化が流行していました。この文化は、裸体像を造って服を着せることで、生きている仏のように見せるというものです。この弁財天も裸体彫刻で作られているため、「裸弁財天」と呼ばれることもあります。
東京国立博物館「弁財天坐像」
上野恩賜公園の中にある東京国立博物館にも弁財天が安置されています。この弁財天は武器を手にしており、戦う女神として祀られていた過去を想起させます。
頭上には蛇がとぐろを巻いており、その先に老人のような顔をみることができます。宇賀神との習合を像にしたタイプの弁財天で、より財運アップを期待できそうです。
東大寺「弁財天立像」
東大寺建築の中で最も古い、東大寺法華堂に祀られていた弁財天は、現在東大寺ミュージアムに安置されています。他の像と異なるのは、立っている状態の弁財天だということです。約2mの像となっており、少し違った弁財天を拝みたい方におすすめです。
「宇賀神像」を見るなら本山寺へ
本山寺は大阪にある天台宗の寺院で、宇賀神像があることで有名です。宇賀神と弁財天を同一視する見方もあり、どちらも財運アップの効果があるとされています。
通常であれば弁財天の頭の上に乗っている宇賀神像ですが、本山寺だと独立した宇賀神像を拝むことができるのがポイントです。実はこの宇賀神像は、「千と千尋の神隠し」の「オクサレサマ」というキャラクターのモデルになったといわれており、ファンにとってもたまらない像なのではないでしょうか。
弁財天は福徳や財宝を授ける女神
弁財天は財運アップや商売繁盛のほかにも、あらゆるご利益を受けることができる縁起物として親しまれています。特に「巳(み)の日」に弁財天のお参りをすると、ご利益がアップすると言われているので、お参りに行く際は日程を調整してみるといいかもしれません。
日本国内で弁財天が祀られている場所はたくさんあります。七福神唯一の女性の神様を見に、一度は足を運んでみてはいかがしょうか。