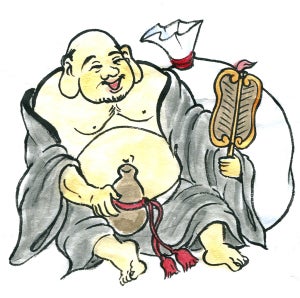七福神の一人である「毘沙門天(びしゃもんてん)」について解説していきます。
毘沙門天がどんな神様なのか、歴史や姿の特徴、ご利益などの観点から紹介します。また毘沙門天が祀られていたり御朱印がもらえたりする場所や、他の七福神についても見ていきましょう。
毘沙門天とはどんな神様?
毘沙門天(びしゃもんてん)は七福神の中でも名前を聞いたことがある人が多い神様です。ここでは毘沙門天がどのような神様なのか紹介していきます。
毘沙門天の歴史 - インドから中国、日本へ
毘沙門天は古代インドの神様です。古代インドで毘沙門天は広まり、その後中国や日本でも信仰される存在となりました。色んな国を渡り歩いてきた神様なのです。
毘沙門天の名前の意味と由来
毘沙門天の名前の由来について解説します。
毘沙門天は古代インドの「クベーラ」という神様がもとになっており、そこから生まれました。このクベーラですが、別名を「ヴァイシュラヴァナ」といいます。これを漢字にすると「毘沙羅門」となりそれが変化して「毘沙門」と呼ばれるようになりました。
「ヴァイシュラヴァナ」は「ヴィシュラヴァス神の息子」という意味で、そこに天界に住む者であることを示す「天」の文字がついて、「毘沙門天」と呼ばれるようになったのです。
毘沙門天の像のお姿
毘沙門天は古代インドにおいて武人の神様として知られていました。日本の仏像で毘沙門天の姿を見ると、ほとんどが武装しています。顔も非常に迫力があり、まさに戦いの神様といった姿です。
日本では財福の神様として信仰されている
日本において毘沙門天は、財福の神様として信仰されています。これは古代ヒンドゥー教において、毘沙門天が財福の神様だったことを引き継いでいるからです。また、無病息災を願うという意味で毘沙門天を祀っている神社やお寺も多いです。
武人のような見た目からは、あまり健康面でのご利益を期待できそうにないので、見た目とご利益のギャップが大きい神様だと感じるかもしれません。しかし、病を倒す、なぎ払うという意味で毘沙門天は悠々たる見た目をしているのです。
毘沙門天の真言
真言(真言/マントラ)とは神様にささげる言葉で、参拝時に唱えるといいとされています。毘沙門天の真言は「オン ベイシラ マンダヤ ソワカ」です。
唱える回数は3回、7回、21回、108回などといわれていますが、お寺や神社に行った際に案内があればそれに従うのがいいでしょう。
毘沙門天は「七福神」「四天王」「十二天」の一人
毘沙門天は、七福神の他にも、四天王や十二天の一人としても数えられています。それぞれどのようなくくりなのか、見ていきましょう。
毘沙門天と「七福神」
七福神には毘沙門天の他にも、 福禄寿、 大黒天、 恵比寿天、 寿老人、 弁財天、 布袋尊が存在します。
七福神を信仰すれば、七福神の七つの幸福を授けられ、七つの厄災が取り除かれると言い伝えられています。それぞれ異なった特徴を持っているので他記事も参考にしてみてください。
毘沙門天と「四天王」
毘沙門天は四天王の一人としても知られています。四天王とは仏法を守護する四神のことで、多聞天(毘沙門天の別名)、持国天、増長天、広目天を意味します。
毘沙門天と「十二天」
また、毘沙門天は十二天の一人でもあります。十二天とは仏教の護法善神12種の天神の総称です。毘沙門天の他は、帝釈天、火天、焔摩天、羅刹天、水天、風天、伊舎那天、梵天、地天、日天、月天の天が各方位に当てられています。
毘沙門天のご利益は?
毘沙門天には数多くのご利益があります。毘沙門天を参拝する際は、毘沙門天にどのようなご利益があるのか知っておきましょう。
毘沙門天から得られる10種の福
毘沙門天を参拝することで、得られる10種の福があります。
- 無尽の福(尽きることのない福)
- 衆人愛敬の福(皆から愛される福)
- 智慧の福(智慧により物事を正しく判断する福)
- 長命の福(長生きする福)
- 眷属衆太の福(周囲の信頼に恵まれる福)
- 勝運の福(勝負事に勝つ福)
- 田畠能成の福(田畑を豊作に導く福)
- 蚕養如意の福(家業が成功する福)
- 善識の福(良い教えを学ぶ福)
- 仏果大菩提の福(悟りを得られる福)
七福神の中でも得られる福の数はトップであり、この世に存在するほとんどの問題を毘沙門天の福によって解決できるといえそうです。参拝する際は、ご利益だけを求めることなく清い心で参拝しましょう。
他にも金運・開運・商売繁盛などのご利益も
毘沙門天として有名なご利益は金運や開運、商売繁盛です。毘沙門天は財福の神様としてあがめられた歴史があるので、お金に関するご利益は多くなっています。
また、武人である毘沙門天は、疫病を払うことができるともいわれています。病気から身を守る、すなわち健康長寿につながり、こういったご利益も毘沙門天にはあるのです。
仏教を守るというイメージが見た目に現れている
毘沙門天が武装した姿をしているのは、戦いの神だからという理由だけではありません。もちろん、昔は争いに勝利するために毘沙門天に祈りをささげたこともあるでしょう。しかし、現代においては違います。
毘沙門天は仏教を守るという強いイメージから武将の姿で表現されているのです。日本では仏教を信仰している方が多いですが、毘沙門天の認知度が他の七福神と比べて高いのは、より仏教に根付いている神様だからかもしれません。
毘沙門天像は邪鬼といわれる、鬼形の者の上に乗っています。迫力のある毘沙門天ばかりに目が行きがちですが、邪鬼も表情が豊かなので注目してみるといいでしょう。
また七福神巡りを行う際には、他の七福神との見た目の差に着目してみてください。毘沙門天は七福神の中でも非常に勇ましい見た目をしています。比較してみると、より興味深く感じられるでしょう。
毘沙門天を祀る、有名な神社やお寺
毘沙門天はいろいろな場所で祀られています。ここでは、毘沙門天が祀られている代表的な場所について詳しく解説していきます。
駒形神社 (神奈川・箱根)
駒形神社(こまがたじんじゃ)は箱根にある神社です。この駒形神社は、箱根の七福神めぐりに選ばれています。七福神めぐりとは、特定の神社やお寺を参拝すれば、七福神すべてに参拝ができるというものです。
駒形神社に参拝をする際には、他の箱根七福神めぐりに選ばれている神社も一緒に参拝してみましょう。
白旗神社 (神奈川・藤沢)
白旗神社(しらはたじんじゃ)は神奈川県にある神社です。藤沢七福神巡りに選ばれており、半日くらいで七福神すべてを参拝することができます。白旗神社は七福神めぐりができる期間が限られているので、注意しましょう。
福王神社 (三重)
福王神社(ふくおうじんじゃ)は三重県にある神社です。急な石段を登った先に福王神社はあり、聖徳太子が1,200年前に奉じたと伝えられている毘沙門天を祀っています。毎月3のつく日は縁日を行っており、地元の人たちで賑わいをみせています。
三重県は伊勢神宮が有名です。福王神社に祀られている毘沙門天には、伊勢神宮を守るという意味もあったといわれています。毘沙門天はこのように何かを守るという目的で祀られていることが多いです。
善國寺 (東京・神楽坂)
善國寺(ぜんこくじ)は東京は神楽坂にあるお寺です。善國寺に祀ってある毘沙門天は、江戸時代から神楽坂の毘沙門天として人気を集めました。現在では、新宿山ノ手七福神の一つに数えられており、七福神めぐりをする方も多いです。
鞍馬寺 (京都)
京都・鞍馬山にある鞍馬寺は、牛若丸と呼ばれた源義経が幼少期に修行した地としても知られています。本殿金堂には毘沙門天が秘仏としてまつられており、60年に一度の丙寅の年に開帳されます。毎年12月最後の寅の日には「おさめの寅」という古札を火にあげる行事が行われます。本殿金堂前には、毘沙門天の使いである虎を狛虎とする阿吽の虎が安置されています。
毘沙門天の御朱印がいただける場所
毘沙門天をご本尊として祀っているところで、毘沙門天の御朱印をいただくのもいいでしょう。
東京・神楽坂の善國寺、栃木の大岩山毘沙門天、奈良の信貴山・朝護孫子寺、京都の鞍馬寺、大阪の神峯山寺、愛知・名古屋の福生院などで毘沙門天の御朱印がいただけます。
ご利益が多い毘沙門天は日本でも親しまれている
毘沙門天は日本でも親しまれている、ご利益の多い神様です。また毘沙門天像は迫力もあり、見ていると何か深く感じるものがあるでしょう。
自分の抱えている悩みや不安に対してほぼ対応している毘沙門天を、休日などを利用して参拝してみてはいかがでしょうか。