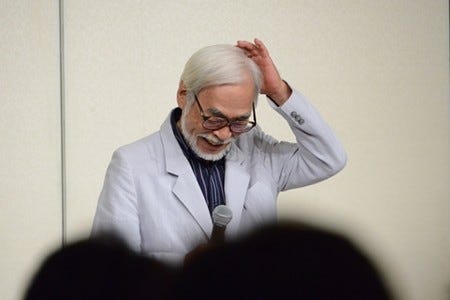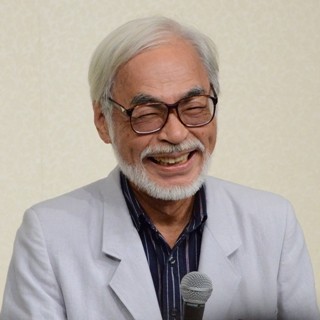――(フランス記者)フランスはいかがでしょうか。
宮崎監督:正直に言いますね。イタリア料理のほうが口に合います(笑)。クリスマスにたまたまフランスに用事があって行ったときに、どこのレストランに入ってもフォアグラが出てくるんです。これが辛かった記憶があります(笑)。答えになっていませんか? あ、ルーブルはよかったですよ。いいところはいっぱいあります。ありますけど、料理はイタリアのほうが好きでした。あの、そんな大した問題と思わないでください(笑)。フランスの友人にイタリアの飛行艇じゃなくてフランスの飛行艇の映画を作れって言われたんですけど、いやーアドリア海に沈んでいったからフランスの飛行艇はないだろうという話をした記憶はありますけどね。フランスがポール・グリモーという、「王と鳥」という名前になっていますが、昔は「やぶにらみの暴君」っていう形で、反戦映画ではなかったけど、1950年代に公開されて甚大な影響を与えたんです。特に僕よりも5つ上の高畑監督の世代には、圧倒的な影響を与えたんです。僕はそれは少しも忘れていません。今見ても志とか世界の作り方を見ても本当に感動します。いくつかの作品がきっかけになって自分はアニメーターをやっていこうと決めたわけですが、そのときにフランスで作られた映画のほうがはるかに大きな影響を与えてます。イタリアで作られた作品もあるんですが、それを見てアニメーションをやろうと思ったわけではありません。
――1963年に東映動画に入社されてちょうど半世紀。振り返って一番辛かったこと、アニメを作って一番よかったと思うことはありますか?
宮崎監督:辛かったのはスケジュールで、どの作品も辛かった。終わりまでわかっている作品は作ったことがないです。つまりこうやって映画が収まっていくというか、見通しがないまま入る作品ばかりだったので、毎回ものすごく辛かったです。最後まで見通せる作品は僕はやらなくてもいいと勝手に思い込んで、企画を立てたり、シナリオを書いたりしました。絵コンテという作業があるんですが、月刊誌みたいな感じで絵コンテを出す。スタッフは、この映画がどこにたどり着くのかぜんぜんわからないままやってるんです。よくもまぁ我慢してやってたなと思うんですが、そういうことが自分にとっては一番しんどかった。でも2年とか1年半とかいう時間の間に考えることが自分にとっては意味がありました。同時に上がってくるカットを見て、ああではない、こうではないといじくっていく過程で、前よりも映画の内容についての自分の理解が深まることも事実なんで、それによってその先が考えられるような、あまり生産性には寄与しない方式でやりましたけど、それは辛いんですよね(笑)。とうとうとスタジオにやってくるという日々になってしまうんですが、50年のうちに何年そうだったのかわかりませんが、そういう仕事でした。
監督になってよかったと思ったことは一度もありませんけど、アニメーターになってよかったと思ったことは何度かあります。アニメーターっていうのは何でもないカットが描けたとか、うまく風が描けたとか、うまく水の処理ができたとか、光の差し方がうまくいったとか、そういうことで2、3日は幸せになれるんですよ。短くても2時間くらいは幸せになれるんです。監督は、最後に判決を待たなきゃいけないでしょ。これは胃に良くない。ですからアニメーターは最後までやってたつもりでしたけど、アニメーターという職業は自分に合っているいい職業だったと思っています。
――それでも監督をずっとやってこられたのは?
宮崎監督:簡単な理由でして、高畑勲と会社が組ませたわけじゃないです。僕らは労働組合の事務所で出会ってずいぶん長いこと話をしました。その結果、一緒に仕事をやるまでにどれほど話をしたかわからないくらいありとあらゆることについて話をしてきました。最初に組んでやった仕事は、自分がそれなりの力を持って彼と一緒にできたのは『ハイジ』が最初だったと思うんですけど、その時にまったく打ち合わせが必要ない人間になっていました。双方にね。こういうものをやるって出した途端に、何を考えているかわかるって人間になっでしまったんですよ。ですから、監督というのはスケジュールが遅れると会社に呼び出されて怒られる。高畑勲は始末書をいくらでも書いてましたけど、そういうのを見るにつけて、僕は監督はやりたくないと。やる必要がないと。僕は映画の方をやっていればいいんだと思っていました。まして音楽や何やらかんやらは修行もしなければ何もやらないという人間でしたから、ある時期がきてお前一人で演出をやれと言われた時は本当に途方に暮れたんです。音楽家と打ち合わせなんて何を打ち合わせしていいかわからない。よろしくって言うしかない。しかもこのストーリーはどうなっていくんですかって、僕もわかりませんって言うしかないんで。
つまり初めから監督や演出をやろうと思った人間じゃなかった。それがやってしまい、途中高畑監督に助けてもらったこともありましたけど、その戸惑いは『風立ちぬ』まで、ずっと引きずってやってきたと今でも思ってます。音楽の打ち合わせでこれどうですかって聞かされても、どこかで聞いたことあるなとか、それくらいのことしか思いつかない(笑)。逆にこのCDをとても気に入ってるんですけど、これでいきませんかと。"これワグナーじゃないですか"(と言われる)とか、そういうバカな話はいくらでもあるんですけど、本当にそういう意味では映画の演出をやろうと思ってやってきたパクさんの修行とですね、絵を描けばいいんだって思ってた僕の修行はぜんぜん違うものだったんです。それで、監督をやっている間も、僕はアニメーターとしてやりましたので、多くの助けやとんちんかんがいっぱいあったと思いますが、それについてはプロデューサーがずいぶん補佐してくれました。つまり、テレビも見ない、映画も見ない人間にとっては、どういうタレントがいるか何も知らないんです。すぐ忘れる。そういうチームというか、腐れ縁があったおかげでやってこれたんだと思っています。決然と立って一人で孤高を保っているというそういう監督ではなかったです。わからないものはわからないという、そういう人間として最後までやれたんだと思います。
――『風立ちぬ』についてお聞きします。長編最後の場面のセリフを「あなたきて」から「あなた生きて」に変えたとプロデューサーが以前にお話されていました。宮崎監督が考えていたものとは違うものになったと思いますが、長編最後の作品として悔いのないものになったのか。また今変えたことについてどう思っていますか?
宮崎監督:『風立ちぬ』の最後については本当に煩悶しました。なぜ煩悶したかというと、とにかく絵コンテを上げなければいけない。制作デスクにさんきちという女の子がいますが、本当に恐ろしいです(笑)。他のスタッフと話していると床に「10分にしてください」って貼ってあるとかね。机の中に色々な叱咤激励が貼ってありまして、そんなことはどうでもいいんですけど(笑)。とにかく絵コンテを形にしないことにはどうにもならないので、とにかく形にしようと形にしたのが追い詰められた実態です。それで、やっぱりこれはダメだなと思いながらその時間に絵が変えられなくてもセリフは変えられますから、自分で冷静になって仕切り直しにしました。こんなこと話してもしょうがないですが、最後の草原はいったいどこなんだろう――これは煉獄であると仮説を立てたのです。ということは、カプローニも堀越二郎も亡くなってそこで再会してるんだ、そう思いました。それから奈緒子は、ベアトリーチェだ、だから迷わないでこっちに行きなさい、と言う役として出てくるんだって。言いはじめたら自分でこんがらがりまして、それでやめたんですよね。やめたことによってすっきりしたんです。『神曲』なんて一生懸命読むからいけないんですよね(笑)。
――自分の作りたい世界観は表現できたのか、達成感はありますか? もし悔いが残っているとしたらどこでしょう?
宮崎監督:その総括はしていません。自分が手抜きしたという感覚があったら辛いだろうと思いますが、とにかく辿り着けるところまでは辿り着いた、というふうにいつでも思ってましたから、終わった後はその映画は見ませんでした。ダメなところはわかっているし、それが直ってることもないので、振り向かないようにやっています。同じことはしないつもりで……ということなんですが。……続きを読む