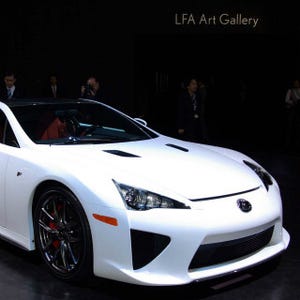年の瀬も迫ってきたある日、LFAの生産終了のニュースが流れた。「あ、まだ作っていたんだ」というのが筆者の正直な感想。末席とはいえ、自動車業界に身を置く筆者でさえそうなのだから、生産終了と聞いて人気がないと勘違いした人もいるかもしれない。
しかし実際には、LFAは最初から500台限定で発売され、予定通り500台生産したから生産を終了したにすぎない。そしてこの500台は3年前の予約開始から数カ月で完売している。「人気がない」などとんでもない誤解なのだ。
1日1台LFAを製作するという「最高に幸せな仕事」
とはいえ、どうもピンと来ない人が多いのではないだろうか?
LFAが街で走っているのを見かけることはまずないし、テレビでも雑誌でもネットでも、LFAの姿を見かけることは非常に少ない。レースで活躍したという話も聞かない。発売と同時に2年先の生産分まで売り切れたという、それほどの人気の盛り上がりというか、熱気のようなものがまったく伝わってこない。非常に陳腐な問題提起で気恥ずかしいが、やはり、「LFAとは何だったのか?」と考えずにはいられない。
まず、なぜたった500台の生産に2年もかかったのか? 「まだ作っていたんだ」と筆者が思ったのは、生産を開始した2年前の時点で500台限定と聞いていたので、「500台くらいあっという間に作り終わっているはず」という先入観があったためだ。
LFAは炭素繊維のボディを採用し、製造が非常に難しいという。生産拠点は元町工場(愛知県豊田市)の専用ラインだが、その生産台数は1日1台。比較しても仕方がないが、プリウスは月間5万台ずつ生産されている。
試しに計算してみよう。1年が365日、うち土日は休みとして、いわゆる「平日」は261日ほど。さらに年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みをそれぞれ10日とすると、トヨタの工場の年間の稼働日数は230日程度になる(トヨタには世間のカレンダーとは別の「トヨタカレンダー」があり、そこには基本的に祝日がない)。
LFAは2010年12月から生産を開始し、2012年12月14日に生産を終了した。なるほど、1日1台ペースで500台生産したら、ちょうど丸2年かかる計算だ。
そんなくだらない計算をしていたら、ふと、元町工場内にあるという「LFA工房」に勤務し、毎日1台ずつLFAを製作(「生産」ではなく「製作」と言いたくなる)していた従業員たちの姿が目に浮かんだ。毎日毎日、LFAをほぼ手作りで組み上げる人々。なんと幸運な仕事に就いていたことか。この世で最高に幸せな仕事ではないか、とさえ思える。
じつは、ここにLFAの存在意義の一端があるのではないか? つまりLFAは顧客に対してというより、トヨタ社員に、「我が社は世界に冠たるスーパーカーを作った」という誇り、プライドを持たせ、トヨタにいても「スーパーカーの製造」という夢のある仕事ができると思ってもらうために存在していた。実際、企業が社員の士気高揚のため、あまり儲けにならない業務をしたり製品を作ったりすることは珍しくない。
LFAは「旧来の自動車の最終進化形」となるかもしれない
このように社内目線で考えると、LFAの役割はいろいろと考えられる。たとえば、これからの自動車開発の最重要課題となる軽量化技術の実証用車両という役割。炭素繊維ボディはBMWなども採用する予定で、トヨタでもそのノウハウの蓄積や実証実験は急務だろう。あるいは、2輪車事業が不調ながら高い技術力を持つヤマハ発動機がその技術を継承、発展させていくために、V10エンジンの開発が役立ったかもしれない。
では、一般の人から見たらどうか? LFAとはカーマニアにとって、スーパーカーファンにとって、いかなる存在であったのか? さまざまな答えがあると思うが、これまであまり指摘されていなかった点をあえて挙げると、LFAは「旧来のスタイルの自動車の最終進化形」として、自動車史に記録されることになるかもしれない。
旧来のスタイルとは、ガソリンのみで走るということだ。LFAの後継モデルはありやなしやと議論を呼んでいるが、もしあったとしても、間違いなくそのパワーユニットはハイブリッドになるだろう。ポルシェやBMWも、これからハイブリッドが主力になることはまず間違いないし、フェラーリやランボルギーニですら、その流れには逆らえない。
まさかトヨタがこのタイミングを狙ったわけではないだろうが、LFAはガソリンエンジン時代(と後に呼ばれるだろう)の最後を飾る、究極のガソリンエンジン車となりそうだ。そんなクルマを、ハイブリッド時代を切り開いたトヨタが作ったというのはおもしろい。