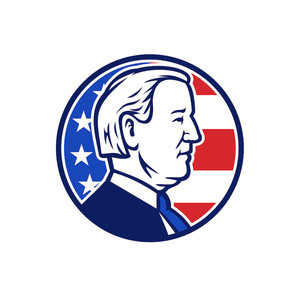マネ―スクエアのチーフエコノミスト西田明弘氏が、投資についてお話しします。今回は、円安について解説していただきます。
歴史的な「円安」が進行中⁉
足もとで米ドル/円が堅調に推移しています。6月9日に米ドル/円は一時134円台半ばに到達し、約20年以上前の02年1月31日の高値135.220円が目前となりました(本稿執筆時点では未達)。それより上の水準となると、やや遠いですが98年8月11日の147.710円が視野に入ります。その98年8月の高値は90年8月以来の高水準でした。
実のところ現在、歴史的な「円安」が進行しています。BIS(国際決済銀行)が公表している円の実質実効レートは、今年4月の時点で73年2月の変動相場制移行後の最低水準まで下落しました。ここからの「円安」は未知の領域と言えなくもありません。
背景は日米の金融政策の方向性の差
足もとの米ドル/円の上昇は、日銀とFRBとの金融政策の方向性の差やそれを反映した金利差を背景にしています。そうした状況は今に始まったことではありませんが、今年5月には米国景気の先行きに対する懸念などから米ドル/円はいったん調整していました。
しかし、足もとで黒田総裁が「金融緩和はこれまでのところ半分しか成功していない(6月8日の講演)」と述べて金融緩和継続へ強い意思を示したこと、そして5月の雇用統計などを受けて米国経済の先行きに対する懸念がやや後退していることが、改めて米ドル/円の上昇をもたらし、それに拍車をかけているのでしょう。
日本でもCPI(消費者物価指数)が伸びを高めており、4月には前年比2.1%上昇と、消費税引き上げの影響を除けばリーマン・ショック時の08年9月以来の伸びをみせました(当時も原油高が物価押し上げ要因でした)。それでも、日銀の黒田総裁は、日銀の目標である2%の物価目標を持続的に達成する状況ではないと判断しています。
だとすれば、足もとの「円安」はまだまだ続くのでしょうか。目先的には、次の2つの点に注意する必要があると思われます。
リスクオフへの転換
一つめは、投資家のリスクオン/オフです。為替相場が金利差を素直に反映している状況は、低い金利(調達コスト)で高い金利(運用利回り)を狙うという投資家のマインド、いわゆるリスクオン(リスク選好)だからです。リスクオフ(リスク回避)になれば、リスクオンで作られたポジションが巻き戻され、あるいは安全な資産へ資金がシフトします。その場合、金利差にかかわらず米ドル/円は下落するでしょう(米ドルは円以外の通貨に対しては上昇)。
ロシアによるウクライナ侵攻は長期化しています。また、新型コロナも終息したわけでありません。それらが状況次第では金融市場のリスクオフ要因になる可能性があります。また、世界経済、とりわけ米国経済の先行きに対する懸念が再浮上するかもしれません。実際に米国経済が大きく減速したり、リセッション(景気後退)になったりすれば、米国が利下げに転換するなどの形で金利差が縮小して米ドル/円の下落要因になるでしょう。
米ドル/円は短期的には上がり過ぎ!?
2つめは短期的な上がり過ぎの反動、あるいは当局のけん制です。足もとの「円安」は過熱気味です。6月8日時点で米ドル/円の終値134.250円は90日移動平均を9.0%上回っています。米ドル/円が90日移動平均を10%超上回ったのは、90年代後半以降でも数回しかありません。16年末のトランプ・ラリー、14年10月の日銀の異次元緩和(黒田バズーカ)第2弾、13年春の黒田日銀総裁誕生(量的緩和)への期待、98年6月の円キャリー取引最盛期です。いずれも短期間でいったんピークをつけています。
直近でも今年4月28日に一日だけかい離率が10%を超えました。日銀が金融政策決定会合で金融緩和の継続を決定し、また長期金利の許容上限である0.25%を死守するために連続での指値オペを発表した日です。
当局のけん制はあるか
黒田総裁は6月7日の財政金融委員会で、「安定的な円安は日本経済全体としてみればプラス」と改めて述べました。一方で、「短期で大幅な円安進行は企業の事業計画策定を困難にすることで経済にマイナスに作用し得る」とも述べています。「短期で大幅な円安」の定義は不明ですが、90日移動平均からのかい離率10%超はこれに該当するかもしれません。
目先的にかい離率が10%を超えるとすれば、米ドル/円は135円台後半と算出できます(現局面では時間が経過するにつれて90日移動平均は上昇するので、算出値も上昇します)。黒田総裁は「為替レートを目標にしていない(8日の講演)」ものの、目先的に米ドル/円が135円台に突入してさらに勢いがつくようなら、何らかのけん制があるかもしれません。少なくとも金融市場は警戒し始めるでしょう。