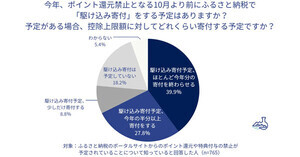佐藤さんの疑問(1)注文住宅の予算はどのように把握したらいい?
「注文住宅を建てる正しい順番を教えてもらって良かったです。早速土地探しやハウスメーカーの情報収集から始めていきたいと思いますが、総額いくらの予算で考えた方が良いのでしょうか?把握しておくべき費用を教えてほしいです!」
FPからのアドバイス(1)購入時と購入後にかかるお金を確認しましょう
住宅購入でかかる費用は、「購入時」と「購入後」の大きく2つがあります。「購入時」にかかるお金は現金で用意し、「購入後」にかかるお金は住宅ローンで用意することが一般的に多いです。
購入時の費用
「購入時」にかかる費用として、税金や登記費用、住宅ローン融資手数料、引っ越し費用、家具・家電購入費などの「購入時諸費用」や「住宅ローンの頭金」、「生活予備資金」があります。
目安として、注文住宅の「購入時諸費用」が物件価格の6%~10%くらいで、「住宅ローンの頭金」は物件価格の10%くらいを見ておくと良いでしょう(頭金なしでも住宅購入はできます)。また、「生活予備資金」は毎月の支出の6カ月分は残した方が良いです。
「そんなに預貯金を貯めないといけないの?」と思われる方でも、諸費用ローンというものもあります。融資手数料やローン保証料、家具代、引っ越し代などの諸費用分も借りることができるという、自己資金が足りない方にとっては魅力的なローンです。お困りの場合はこちらを検討すると良いでしょう。
購入後の費用
「購入後」にかかる住宅ローンはいくらまで借りられるのか、金融機関が決める「借入可能額」と「安心して返済できる金額」を知ることが大事です。金融機関が定める借入可能額の指標は以下の通りです。
▶返済負担率
「年収に占める年間返済額の割合」のことです。例えば、返済負担率が30%、年収350万円の場合、350万円×30%÷12カ月=87,500円となります。この金額が毎月の返済額の上限です。※金融機関によって返済負担率は違います。
住宅ローン返済額は、一般的に返済負担率が25%以内なら安心といわれています。
▶融資率
「住宅価格に対する借入金の割合」のことです。例えば、5000万円の物件に対して融資率が90%の場合、4500万円まで住宅ローンが借入できます。残りの500万円は頭金として必要になるということです。
▶借入限度額
「年収や返済負担率に関わらず、一人あたりが借り入れできる上限額」のことです。フラット35は8000万円まで、民間銀行は約1億円まで、と覚えておくと良いでしょう。(最近は民間銀行でも1億円以上でも借りられるところが増えています。)
▶安定性・担保価値
住宅ローンの契約者の勤め先や勤続年数などが考慮され、公務員など安定した職業だと借入希望額での住宅ローン審査が有利になります。
また、支払いが滞った際に回収できるかどうか、金融機関が物件の価値を事前に確認します。