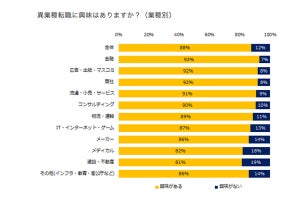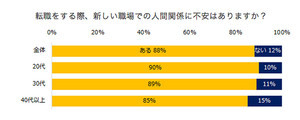テクノロジーが進化し、AIの導入などが現実のものとなった今、「働き方」が様変わりしてきています。終身雇用も崩れ始め、ライフプランに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本連載では、法務・税務・起業コンサルタントのプロをはじめとする面々が、副業・複業、転職、起業、海外進出などをテーマに、「新時代の働き方」に関する情報をリレー形式で発信していきます。
今回は、IT企業経営者としての経験も持つ弁護士・中野秀俊氏が、起業家が知っておくべき「契約書」の基本について語ります。
起業して取引が始まると「契約書」を提示されることがあります。契約書チェックなどは、弁護士に依頼することも考えられますが、コストがかかりますし、そもそも弁護士の知り合いがいないといったことも考えられます。そこで今回は、取引相手から契約書が提示された場合に、最低限ここだけはチェックしてほしいポイントを解説していきます。
契約の期間と解除を把握する
継続的な契約(基本契約、業務委託契約など)を締結する場合には、契約期間がいつから始まり、いつ終わるのかをチェックしましょう! また、自動的に更新するかどうかもチェックが必要です。
契約の解除とは、既に成立した契約関係を一方的に失わせることをいいます。典型的には、契約違反があった場合には、契約解除をすることができます。その他にも、企業の経済状態が悪くなった場合などが考えられます。チェックする際には、自社が守れそうもないことがないかを確認しましょう!
最低限確認したい条項とは?
具体的な確認してほしい事項をいくつか紹介しておきます。
●期限の利益喪失条項
お金を借りる場合や分割で支払う契約の場合には、「○○の場合には、当然に期限の利益を喪失し、相手方に債務の全部を直ちに弁済しなければならない」といった条項があります。
これに該当すると、一括で支払う必要があるので、スタートアップ・ベンチャー企業としては、「期限の利益の喪失条項」がある場合には、どのような事項が記載されているか確認するようにしましょう。
●損害賠償条項
気を付ける点は、損害賠償を負わない場合(免責)や損害賠償額の上限があるかどうかです。免責規定があると、損害賠償は負わないことになりますし、上限がある場合には、それ以上の金額の賠償請求はできないことになります。
●完全合意条項
法律上、契約書に記載がない条項でも、お互いの合意があれば契約内容になります。例えば、担当者同士のチャット・メールや会議の場で、契約書にはないやり取りをしている場合です(会議の発言については、議事録として残っていれば証拠になります)。
実際、当事者間に争いが生じた場合には、契約書に記載がない事項が契約の内容になるのか、といったことが争いになることがあります。
そこで、このような事態を避けて、「契約書に記載されたことに限って合意事項とする」べき場合に、完全合意条項を設けることがあります。このような規定があれば、契約書以外に記載されていない事項は、お互いを拘束することはできないことを肝に銘じておきましょう!
●合意管轄条項
「合意管轄条項」とは裁判になった場合に、どこの裁判所で裁判するかについての規定です。どこの裁判所で裁判できるかは、法律で決まっているのですが、お互いの合意で決めておくこともできます。
そして、お互いで合意した裁判所があれば、その裁判所で裁判をすることになります。当然ですが、裁判所については会社の所在地から近い方がよいです。自社の所在地の管轄裁判所を指定できれば、万が一訴訟になった場合、裁判所までの交通費や弁護士への日当を節約することができます。
ただ、この条項に拘りすぎて、契約自体が白紙になってしまうのは本末転倒なので、その辺りはどこまで交渉するか考えた方がよいです。
東京や大阪の裁判所では、建築・労働関係専門の部署があり、当該分野に精通した裁判官が審理をしてくれます。またIT紛争では、大都市部の裁判所の方が件数が多いので、その手の事件に裁判官も慣れている場合が多いです。その点も加味して決定するとよいでしょう。
執筆者プロフィール : 中野秀俊
グローウィル国際法律事務所 代表弁護士、グローウィル社会保険労務士事務所 代表社労士、みらいチャレンジ株式会社 代表取締役、SAMURAI INNOVATIONPTE.Ltd(シンガポール法人) CEO。
早稲田大学政治経済学部を卒業。大学時代、システム開発・ウェブサービス事業を起業するも、取引先との契約上のトラブルが原因で事業を閉じることに。そこから一念発起し、弁護士を目指して司法試験を受験。司法試験に合格し、自身のIT企業経営者としての経験を活かし、IT・インターネット企業の法律問題に特化した弁護士として活動。特に、AI・IOT・Fintechなどの最先端法務については、専門的に対応できる日本有数の法律事務所となっている。