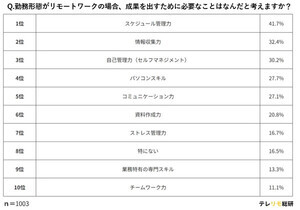テクノロジーが進化し、AIの導入などが現実のものとなった今、「働き方」が様変わりしてきています。終身雇用も崩れ始め、ライフプランに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本連載では、法務・税務・起業コンサルタントのプロをはじめとする面々が、副業・複業、転職、起業、海外進出などをテーマに、「新時代の働き方」に関する情報をリレー形式で発信していきます。
今回は、IT企業経営者としての経験も持つ弁護士・中野秀俊氏が、起業家が知っておくべき「著作権」の基本について語ります。
スタートアップ・ベンチャー企業は、これといった資産がないことが多く、自社コンテンツのみが命綱であることが多いため、それを守ることが企業経営で重要となります。また、もし他社の著作権を侵害してしまった場合は、法律的なダメージだけでなく、風評被害も受け、企業活動の維持が難しくなってしまうこともあり得ます。そのため、起業家は「著作権」について理解しておくことが非常に重要です。本稿では、そもそも著作権とは何か、どういう場合に著作権侵害になるのかを解説します。
「著作権」って何?
著作権とは、著作者が自ら創作した「著作物」を排他的に利用することができる権利です。この著作物とは、法律上「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています。これは、分かりやすくいうと、「オリジナルのコンテンツ」というイメージです。
何かしらのオリジナルのコンテンツを作成していれば、登録等の手続きをする必要はなく、創作した瞬間に、その著作物に著作権が発生するというのが著作権の特徴です。著作物の権利を持っている著作権者は、権利を独占するため、第三者が著作物を複製したり、変更したりすれば、そのような第三者の利用行為を差し止めたり、第三者に対して損害賠償請求したりすることが可能です。
他人のコンテンツを利用したい場合は?
では、他人のコンテンツを利用したい場合には、どうすればよいのでしょうか。原則的には、以下の対応が必要です。
1.権利者から許諾を得る
2.著作権法の例外規定に基づいた利用をする
2の「著作権法の例外規定」とは、著作者の許諾を得ることなく著作物の複製等の利用をすることができる場合として、著作権法で例外的に認められた規定です。その内容にはいくつかあり、「引用」(32条1項)もそのひとつです。
多くの経営者が「引用」であれば、著作物の利用が許されるというのは聞いたことがあると思います。しかし、どのような場合が「引用」として許されるのか、法律では具体的に規定されておりません。特に重要な要素は以下の2点であるとされています。
1.明瞭区別性(引用する側と引用される側か明瞭に区別されること)
2.主従関係(引用する側か主であり、引用される側か従たる関係にあること)
この主従関係については、どの程度の分量であればOKということは明確には決まっていないのですが、少なくとも、他人のコンテンツが半分以上を示してしまうと「引用」にはならない可能性が高いです。
契約書を締結する際の注意点とは
著作権は、登録手続き等は必要なく、当然のものとして著作者に生じます。これは、金銭を支払って第三者に創作業務を委託した場合であっても変わりはなく、原則として創作を行った業務の受託者に著作権が生じることになるのです。
委託者に帰属させたいのであれば、受託者から委託者に著作権が移転する旨の合意をとる必要があります。著作権を委託者・受託者のどちらに帰属させるのかについては、その著作物の内容(流用の可能性の有無・委託者による利用目的)や、支払われる対価等を踏まえたビジネス判断となります。
著作権を委託者に帰属させるために、受託者から委託者に著作権を移転させる旨を契約書に規定する場合は、「本業務の成果物に関する著作権(27条及び28条の権利を含む)は、納品と同時に受託者から委託者に移転する」などの規定を設けることになります。
また著作者には、著作者人格権として、公表権(18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条)が認められます。これらは著作者の人格的利益を保護した権利であり、たとえ契約書で合意したとしても著作者にのみ帰属し、著作者から第三者に移転することはできません。そこで、受託者から委託者に著作権を移転させるのであれば、著作者人格権については「行使しない」旨を定めておく必要があります。
執筆者プロフィール : 中野秀俊
グローウィル国際法律事務所 代表弁護士、グローウィル社会保険労務士事務所 代表社労士、みらいチャレンジ株式会社 代表取締役、SAMURAI INNOVATIONPTE.Ltd(シンガポール法人) CEO。
早稲田大学政治経済学部を卒業。大学時代、システム開発・ウェブサービス事業を起業するも、取引先との契約上のトラブルが原因で事業を閉じることに。そこから一念発起し、弁護士を目指して司法試験を受験。司法試験に合格し、自身のIT企業経営者としての経験を活かし、IT・インターネット企業の法律問題に特化した弁護士として活動。特に、AI・IOT・Fintechなどの最先端法務については、専門的に対応できる日本有数の法律事務所となっている。