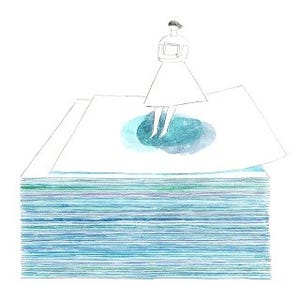人の集団の中から、外れたくなくても外れてしまう人がいるように、中にいなければ、と思っていなくても中に適応してしまう人もいる。寧々は、子供の頃から「普通」の範疇から外れることのない人間だった。
小学校では女の子同士でお人形を持ち寄って遊んだりしたし、中学校ではみんなで雑誌を読んで、どんな服がかわいいとかそんな話をした。高校に入るとみんな恋愛をするようになっていき、寧々も友達の紹介で、同じ高校の同級生の賢治とつきあうことになった。
知っている男の子の中で、誰がいちばんいいか、と訊かれたら、賢治だと言えた。賢治は水泳をしていて、寧々の高校には水泳部がなかったので、校外のプールに通っていた。かっこいい、と女子から言われていることもあったが、賢治は無口で、男子高校生らしいとっつきやすさ、いびつさがなく、大人びた雰囲気があった。女子から見れば、話しかけにくい存在だと思われているようだった。
寧々も賢治にそうした雰囲気は感じていたが、その無口さが不器用さから来るものだと知ってからは、好意を持つようになった。正直な気持ちをその場ですぐに言えない自分と似ている、と感じたからだった。
恋の話がしたくてたまらない友達が、賢治の友達に「寧々は賢治が好きらしい」と吹聴し、周りからくっつけられるような形で、寧々と賢治はつきあい始めた。学校の帰りに二人でファストフードを食べたり、メールをしたり、みんなと一緒に遊園地に行ったり、そういうことをした。
そして、クリスマスイブに会う約束をした。
夜遅くなると両親に叱られるので、イブの日は昼間から出かけた。賢治が「プレゼントは買ったりするな、会ったときに一緒に選ぼう」と言うので、寧々は小さなショルダーバッグだけかけて、寒くないようにマフラーをぐるぐる巻いて出かけた。
賢治と並んで歩き出すと、何かいつもと違う空気を感じた。
「どこに行こうか?」
寧々がそう切り出すと、賢治は少し困った顔になった。
「ごめん、そこの公園でちょっと話さない?」
賢治がそう言うのを聞いて、寧々は「ふられるのかもしれない」という予感がした。午後の公園の陽射しはあたたかく、賢治は寧々がいつも飲むミルクティーと、自分の分の温かいお茶を自販機で買ってきて、ベンチに座った。
「あのさ、なんか俺、変なこと言うかもしれないけど、聞いて」
寧々はミルクティーのふたを開けるのも忘れ、聞いた。
「俺はお前のこと、好きだと思う。可愛いと思うし、なんかしたいって、その、そういう気持ちもある。けど、こういうの、恋愛なのかな。どう思う?」
そう言う賢治の顔を見たら、寧々はそれが本気の言葉なのだとはっきりわかった。別れたいとか、別れるための言い訳とかではなく、賢治は本当にこのことで悩んでいるのだ、と。寧々は、今、自分も本当の気持ちを言わなければいけない、と思った。
「私は賢治のこと、好きだと思う。でも、賢治の言ってる意味は、たぶんわかると思う」
賢治は、照れを振り切るような真剣な顔で話し始めた。
「一緒にいて楽しいし、他の女の子が好きとか、そういうのはない。けど、なにがなんでも俺のものにしたいとか、お前しかいないとか、そういうすげえ強い気持ちみたいなの、俺はわかんないんだ。俺がおかしいのかもしれないけど、恋愛って、もう一生この人だけ、って思い込むような、激しいもんじゃないのかなって気がしてて……。そういうのじゃないのに、お前とつきあってて、いいのかなって、そう思ったんだ」
寧々は少し泣きそうになった。賢治が好きだと思ったし、寂しいと思った。けど、言葉にしなければ、と必死で口を開いた。
「私は、賢治が好き。今みたいなこと言ってくれる賢治のこと、ほんとに尊敬してる。でも、なんか……」
言葉に詰まった寧々の、その先を賢治は言った。
「俺たち、なんとなく『恋愛』っていうものがしてみたかっただけなんじゃないかと思うんだ」
寧々は、その通りだと思った。やっとふたを開けたミルクティーは、ぬるくなっていた。
公園を出ると、賢治と歩いてショッピングモールに行った。
「なんか、欲しいもの買おう。ほんとに欲しいもの」
賢治にそう言われると、寧々は自分が欲しいものがよくわからなくなった。いつもはここに来ると、なんでも欲しく思えた。友達と一緒に服を見ていたら、コートからバッグから靴まで全部欲しくなったし、クリスマスならアクセサリーがいいな、となんとなく思っていた。けれど、いつもなら「いいな」と思うものでも、「ほんとに」欲しいかと考えると、よくわからないのだ。
「私、ほんとに欲しいものって、あんまりないのかもしれない」
そう言うと、賢治は笑った。
「俺も、さっきから考えてるけど、わかんないな。ほんとって何なんだろうな」
「わかんないね」
薄闇が近づき、モールの外灯がともる。寧々は、普段は立ち寄らない店のショーウインドウに、それを見つけた。それは、黒い天鵞絨の生地のふちに、黒いファーがついている襟巻きだった。端のほうに星形のブローチがついていた。
大人っぽいデザインだし、高そうだった。友達の誰も、こういうものは持っていない。持っている服に合うかどうかもわからなかった。けれど、それは寧々にとって「特別なもの」だとはっきりわかった。寧々は叫ぶような気持ちで言った。
「私、あれが欲しい。ほんとに欲しい」
その襟巻きは、寧々の持っているお金だけでは足りず、足りなかったぶんを賢治が出してくれた。
「ありがとう」
「いいよ、俺、欲しいもの見つからなかったし」
賢治は、いつものように寧々を家まで送ってくれた。でも、これで「恋人同士」という関係は終わりなのだとお互いにわかった。
「私、ほんとかどうかわかんないけど、賢治のこと、前より好きになった」
寧々は勇気を出して、そう言った。賢治はあまり驚いた顔をしなかった。
「俺もそんな気がする」
でも、ここで「じゃあやっぱりつきあおう」と言うのは、たぶん違う、と寧々は気づいていた。
「もし大人になって、賢治が私にとってのたった一人の人だと思ったら、言う」
賢治はいつもの低い声で「おう」と呟くように言って、そっと続けた。
「俺、最初の相手がお前で、よかった」
じゃあな、と手を振る賢治に手を振り返しながら、寧々は寂しさと幸福感に包まれていた。
恋愛ではなかったけれど、お互いに最初の「特別な相手」になれたのだ。「ほんとの」相手になれたのだ、という思いを、寧々は襟巻きの毛皮に顔を埋めながら、うっとりと味わった。
<著者プロフィール>
雨宮まみ
ライター。いわゆる男性向けエロ本の編集を経て、フリーのライターに。著書に「ちょっと普通じゃない曲がりくねった女道」を書いた自伝エッセイ『女子をこじらせて』、対談集『だって、女子だもん!!』(ともにポット出版)がある。恋愛や女であることと素直に向き合えない「女子の自意識」をテーマに『音楽と人』『SPRiNG』『宝島』などで連載中。マイナビニュースでの連載を書籍化した『ずっと独身でいるつもり?』(KKベストセラーズ)を昨年上梓。最新刊は『女の子よ銃を取れ』(平凡社)。
イラスト: 安福望