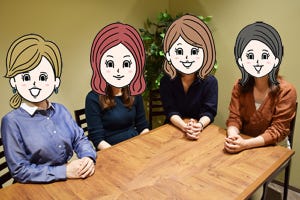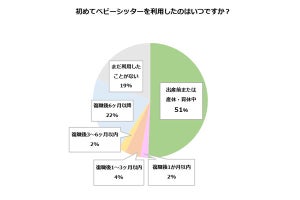新生活を前に、仕事と家事・育児の両立に不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はそんな時の不安解消に効果のある「時間割」についてご紹介します。
1日の過ごし方を可視化してみる
毎日、やることはそう違わないはずなのに、その時々の気分や思いつきで行動していることはありませんか?
筆者は、子どもが生まれた時から、その"行動のムラ"を減らすために、時間割を作って1日の過ごし方を可視化してきました。
子どもが小さい時には半年に1回程度、第一子が小学生になった今は1年に1回、時間割を更新しています。
この表は、筆者が第一子・第二子それぞれの仕事復帰時に作成した時間割です。
時間割作りは、その通りに生活することを目的にはしていません。
その都度「次は何をする?」と迷うことでエネルギーを消耗したり、やるべきことが終わらずにイライラしたりするのを避けるために作っています。
この時間割を定期的に見直すことで、自分の願うあり方に近付く毎日を過ごせているか、考える時間を持てるようになります。
時間割を作ることで得られる3つのメリット
時間割作りにはこんなメリットがあると考えています。
メリット1:行動を習慣化しやすくなる
次にすべきことがハッキリしていると、取りかかりやすいという経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。
バタバタと気忙しい毎日だからこそ、やるべきことを無駄なくできるよう、時間割で次の行動を明確にしておけるといいですね。
メリット2:優先順位をつけやすくなる
自分が使い方を決められる時間は何時間あるのか、具体的に把握できるのもメリットの1つです。
例えば、仕事・通勤時間が10時間、睡眠時間が6時間とすると、自分が使い方を決められる時間は8時間ということになります。
食事やお風呂などの生活に関わる時間やそれに伴う家事、子どもとの時間や自分時間など「すべきこと」や「やりたいこと」はたくさんありますよね。
そこに8時間という"枠"ができることで、その枠内に何を優先して入れるのかを具体的に考えやすくなります。
メリット3:パートナーと状況をシェアしやすくなる
自分が経験していないことについて理解するのは、誰にとっても簡単ではありません。
平日は家事や育児に関わりにくいパートナーがいる場合、時間割という客観的なもので過ごし方をシェアする方が、問題の共有や相談もしやすくなります。
仕事の都合などで、実際には家事シェアができない場合でも、パートナーが状況を理解してくれていると感じられれば、気持ちが救われることもあるはずです。
理想と現実のギャップをどう埋める?
実際に生活をしていると、時間割のようにはいかないことも多々あります。
そんな時には、実際の時間の使い方を記録してみましょう。意外と時間がかかっている予定に気づけるはずです。
何にどれだけの時間がかかっているのかを具体的に把握できると、それが妥当かの判断もしやすくなります。
・手放す
・家電を利用する
・他の人(サービス)を頼る
など、他の方法も選びやすくなりますよ。
そして、そもそも「やるべき」と思っていることが、本当に必要なのか、疑う視点も持てるといいですね。
そのうえで、自分にとって理想通りの時間が確保できなかった場合でも、「時間の質を上げる」という方法で満足度をアップさせることはできます。
例えば、15分でできるやりたいことリストを作っておいて、隙間時間を活用したり、自分の好きなアーティストの曲を流して子どもと一緒に楽しんだりと、限られた時間の中で小さな工夫をしてみましょう。
できないことではなく、できていることに目を向けよう
毎日追われるように過ごしていると、ついついできていないことにばかり目が向きがちです。
けれど、仕事も家事も子育ても多くのことをこなせているというのは、たくさんの「できていること」の積み重ねがあってこそです。
今できていることを過小評価せずに自信に変えて、よりよくなるための小さな工夫を見つけられるといいですね。