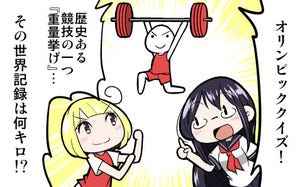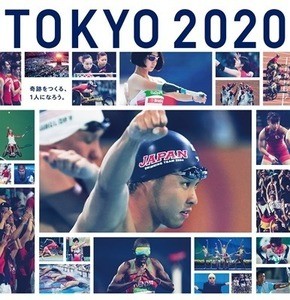東京2020オリンピック競技大会では、史上最多となる33競技339種目の開催が予定されている。本連載では、イラストを交えながら各競技の見どころとルールをご紹介。今回は「柔道」にフォーカスする。
熱い技の応酬と、相手の隙をつく冷静な駆け引き。一瞬たりとも気が抜けない4分間。
日本発祥のスポーツ、「柔道」。オリンピックでは東京1964大会で初めて正式競技に採用された。
試合では、白か青の柔道衣を着用した選手が、10メートル四方の畳の上で戦う。どちらかの選手が「一本」をとれば、その時点で試合は終了し勝敗が決する。技が決まり相手を制することができても、「一本」となるすべての要件を満たさない時は「技あり」となる。
技は100種類。68の「投技(なげわざ)」と32の「固技(かためわざ)」に分けられる。「投技」には背負投(せおいなげ)や体落(たいおとし)などの手技(てわざ)、袖釣込腰(そでつりこみごし)や払腰(はらいごし)などの腰技(こしわざ)、大外刈(おおそとがり)や内股(うちまた)などの足技(あしわざ)、そして巴投(ともえなげ)に代表される捨身技(すてみわざ)がある。
また、「固技」は一般に寝技(ねわざ)ともよばれる抑込技(おさえこみわざ)、送襟絞(おくりえりじめ)のような絞技(しめわざ)、腕挫十字固(うでひしぎじゅうじがため)などの関節技(かんせつわざ)に分けられる。
一瞬のうちに技が繰り出され、勝負が決する柔道。ポイントで負けていても、終了数秒前の大逆転があり得る。目が離せない競技である。
柔道における最高の判定は一本。主審が一本を宣告した瞬間、試合は終了し勝負が決する。すべての柔道選手が狙うのが一本だ。一本をとることは非常に難しく、選手はそのために死力を尽くす。
投技の一本は、インパクト(強さ、速さ、背中をつける)がある形で相手を投げた場合に与えられる。豪快に投げて一本が決まる瞬間は見ていてとても美しく気持ちがいい。十分に相手を制して投げた一本のインパクトにおける条件のうち、どれか1つが欠けていた場合は技ありになる。
柔道の投技は、ただ技を掛ければ相手が倒れてくれるようなものではない。まずは相手の体勢を崩すことから始まる。そのためにまず行われるのが、組み手争いである。自分の有利な組み手になれば、相手を崩し、技に持ち込みやすいからだ。逆に、相手にとって有利な組み手を取られると自分が危なくなる。組むことを嫌がる選手がいるのは、こうした理由からである。
固技では、技の要件がそろった瞬間に主審が「おさえこみ」と宣言し、そこから10秒で技あり、20秒で一本になる。選手同士の足が絡まった状態では「おさえこみ」とならないため、逃げたいとする選手は足を絡めようとし、技を掛ける側は足を抜こうとする。重量級では、「おさえこみ」から抜けることがなかなか難しい。
固技のうち絞技や関節技では、技を掛けられた選手がダメージを受けることがあるため、「まいった」をすることがある。この時は、技を掛けた選手に一本が与えられる。
どちらの選手も一本をとれずに4分の試合時間が終了した時に、「技あり」を決めていた場合は優勢勝ちになる。優劣がつかない場合は延長戦を行う。
選手は皆、一本をとりたい。だが、一本にこだわるあまり相手にチャンスを与えてしまうこともある。勝つためにはあえて美しくない戦い方をする選手もいる。
柔道の勝負は熾烈を極める。みなぎる気迫、一瞬で決まる豪快な投げ、そしてすべての力を出し尽くす激しい戦いからは、目を離せない。
イラスト:けん