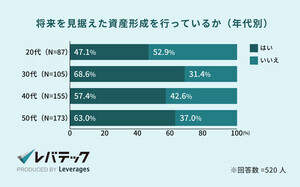制度改正により投資メリットが大幅に増え、昨年より大人気となった新NISA。しかし、この制度を最大限に活用するには定められた上限額(年間投資枠)と限度額(非課税保有限度額)をただしく把握して、無理のない範囲で最適な計画を立てる必要がある。しかし、投資になれていない方には、両金額をなかなか理解しづらい側面も。
そこで本稿では、新NISAなどの最新投資情報をお送りする『投資情報メディア』の執筆陣であるFP松岡紀史氏による、年間投資枠と非課税保有限度額についての解説をお送りする。
2024年1月から始まった新NISAは、2023年までの旧NISAと比べ、1年間に投資できる金額と非課税で保有できる金額が大きく拡大された。また、旧制度のつみたてNISAと一般NISAにあたる2つの投資枠を併用できるようになったことにより、さらに投資の自由度が上がっている。
ここでは、新NISAの年間投資枠と非課税保有限度額がどのように拡大されたのか、旧制度と比べながら詳しく解説していこう。
新NISAの上限額・限度額はいくら?
2024年に始まった新NISAでは、2023年までの旧NISAと比べると、非課税で1年間に投資できる上限額と、制度全体で保有できる限度額が拡大され、非課税で保有できる期間も無期限化されている。
| 新NISA(2024年以降) | 旧NISA(2023年まで) | |||
|---|---|---|---|---|
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | つみたてNISA | 一般NISA | |
| 制度の併用 | 併用可 | 併用不可(選択制) | ||
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 | 40万円 | 120万円 |
| 非課税保有限度額(総額) | 1,800万円 (うち、成長投資枠は1,200万円まで) |
800万円 | 600万円 | |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 最大20年 | 最大5年 | |
出典:金融庁「NISAを知る」
新NISAでは、つみたて投資枠で年間120万円、成長投資枠で年間240万円まで投資が可能である。さらに、新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能であるため、年間で最大360万円の投資が可能となっている。
旧NISAでは制度の併用ができず、年間で投資できる上限額の最大値は一般NISAを利用した場合の120万円であったため、新NISAでは3倍に拡大されたことになる。
また、非課税保有限度額は1,800万円に変更された。旧NISAでは、非課税投資枠で保有できる最大額がつみたてNISAを利用した場合の800万円(年間40万円、最大20年間保有可能)であったため、これも2倍以上に拡大されている。
新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になったため、1,800万円の非課税保有限度額の中で、つみたて投資枠の商品と成長投資枠の商品をどちらも保有することができる。ただし、成長投資枠は1,200万円までという制限がある。
新NISAの年間投資枠の拡大について
新NISAでは、旧NISAに比べ、年間投資枠が大幅に拡大されている。したがって、これまでよりも、より多くのお金を非課税での運用に回せることが可能になった。
ここでは具体的にどのような変更点があったのかを見ていこう。
年間投資枠とは?
NISA制度における「年間」とは、1月から12月までを指す。つまり、年間投資枠とは1月1日から12月31日までに、いくらまで投資できるかという枠のことである。この枠内で投資した金融商品であれば、運用益に税金がかからず運用が可能である。
株や投資信託の売買は、①注文を出す→②取引が成立する(約定)→③取引の決済をする(受渡)という手順を踏むが、実際に取引が完了するタイミングは③の受渡日になる。
したがって、年末ギリギリに注文し、受渡日が年を越えて翌年になった場合、年間投資枠は翌年のものが使われる点に注意したい。
新NISAの年間投資枠はいくらになった?
新NISAでは、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円に設定されている。これは、旧NISAのつみたてNISA(40万円)の3倍、一般NISA(120万円)の2倍に拡大されたことになる。
さらに、新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠が併用可能であるため、年間最大360万円までの投資が可能だ。
ただし、必ずしも両枠を併用する必要はなく、つみたて投資枠または成長投資枠のどちらかのみを利用することもできる。
余った年間投資枠は持ち越せない
年間投資枠は、つみたて投資枠・成長投資枠ともに年をまたぐとリセットされる。
例えば成長投資枠でいうと、2024年に240万円分を使い切っても、2025年の年間投資枠は240万円に復活する。また、2025年に200万円金融商品を購入し、40万円分の枠が未使用だったとしても、2026年の年間投資枠は変わらず240万円になる。つまり、未使用だった40万円を繰り越して2026年に280万円を投資することはできない。
年間投資枠にこだわらない金額の設定を
年間投資枠が繰り越せないとなると、できるだけ投資枠を上限まで使い切りたいと考える方もいるかもしれない。
旧NISAであれば、一般NISAで年間120万円、つみたてNISAで40万円でしたので、少しまとまった資金を投資に回したり、月々3万円程度積立投資をおこなったりすれば、年間投資枠を使い切ることが可能だった。
しかし、新NISAでは年間投資枠が拡大され、すべて使い切ることのハードルが上がっている。実際、国税庁が2023年に発表した「令和4年分 民間給与実態統計調査」 によると、日本人の民間の平均給与は457万6,000円となっている。この実態を考えると、年間360万円を投資に回して問題なく生活できる人は多くないはずだ。
したがって、新NISAでは年間の投資枠を使い切ることにこだわらず、あくまで余剰資金で投資をおこなうことが大切になる。長期的な運用を見据えて無理のない投資額を決めるのがおすすめだ。
非課税保有限度額の新設について
新NISAでは、年間投資枠の拡大だけでなく、非課税保有限度額が新設されている。2023年までのNISAに比べて、非課税で保有できる資産が増えるため、NISA制度をよりさまざまな目的のために利用しやすくなったと思われる。
ここでは具体的に何が拡大されたのかご紹介しよう。
そもそも非課税保有限度額とは?
非課税保有限度額とは、NISA口座全体で保有できる金額の上限のこと。年間投資枠は1年間に非課税投資枠を使って投資できる金額の上限だったが、2024年からのNISAでは、投資を積み重ねて一人いくらまで非課税投資枠で金融商品を保有できるのかも定められている。
NISAの非課税保有限度額までの投資であれば、そこから得た売却益や配当・分配金に対して、税金はかからない。
新NISAの非課税保有限度額はいくらになった?
新NISAでは、非課税で保有できる投資総額の上限が 1,800万円 になった。これは、旧NISAの最大 800万円(つみたてNISAの場合)と比べて 1,000万円も増加(約2.3倍) したことになる。
また、新NISAでは つみたて投資枠と成長投資枠を組み合わせて利用できる ため、より柔軟な投資計画が立てられるのも大きなメリットとなっている。
なお、旧制度のつみたてNISAや一般NISAで保有していた金融商品は、新NISAとは別枠で管理されるため、人によってはさらに多くの金額を非課税で保有できることもある。
例えば、2023年までにつみたてNISAで100万円の金融商品を購入していたとすると、その100万円は新NISAの非課税保有限度額とは別に管理される。したがって、もしこのつみたてNISAの100万円を保有し続け、新NISAで1,800万円分新規に投資すると、合計1,900万円を非課税で保有できる可能性がある。
新NISA非課税保有限度額は?
新NISAでは1,800万円の非課税保有限度額を、つみたて投資枠と成長投資枠の両方で使うことができる。ただし、成長投資枠で利用できるのは1,800万円のうち1,200万円以内という制限がある。
つまり、成長投資枠だけで1,800万円保有することはできず、1,800万円を最大限活用したいのであれば、最低600万円はつみたて投資枠で保有する必要がある。逆に、つみたて投資枠だけで1,800万円保有することは可能だ。
非課税保有限度額は再利用が可能
新NISAでは、非課税保有枠の金融商品を売却すると、売却した商品の購入時の価格(額)分の非課税保有限度額が再利用できる。
例えば、新NISAで次のような投資をおこなっているとした場合
| 利用枠 | 商品 | 購入時の価格(額) | 売却時の価格(額) |
|---|---|---|---|
| 成長投資枠 | 株式A | 600万円 | 400万円 |
| つみたて投資枠 | 投資信託B | 800万円 | 1,200万円 |
非課税保有限度額は購入時の価格(簿価)で管理される。したがって、売却直前の非課税保有限度額の利用金額は、購入時の600万円+800万円で1,400万円となり、この時点では非課税保有限度額まで400万円の余裕があることになる。時価の400万円+1,200万円で1,600万円とはならないことに注意したい。
再利用できる非課税保有限度額も簿価で管理される。例えば株式Aを400万円で売却すると復活する非課税保有限度額は600万円となり、投資信託Bを1,200万円で売却しても復活するのは800万円となる。
『投資情報メディア』より、記事内容を一部変更して転載。