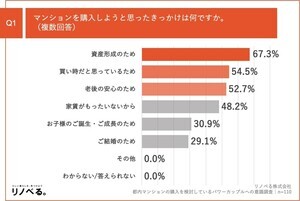パワーカップルならぬ、「パワーファミリー」という言葉をご存知でしょうか。世帯年収1,500万円以上の共働き家庭であるパワーファミリーは、インフレや価値観の変化が進む時代の”新たな消費のけん引役”として注目されています。
では、パワーファミリーとは具体的にどのような人たちで、パワーカップルとはどう違うのでしょうか。今回は、パワーファミリーとパワーカップルの違いや、パワーファミリーの消費に対する価値観についてご紹介します。
■パワーファミリーとパワーカップルの違い
収入が多く、消費意欲の高い世帯として注目されてきたパワーカップル。しかし最近では、「パワーファミリー」という言葉も誕生し関心を集めつつあります。パワーカップルとパワーファミリーはどこに違いがあるのか、見ていきましょう。
<パワーカップルとは>
パワーカップルとは、いわゆる「夫婦ともに高収入な共働き家庭」を指す言葉ですが、明確な収入の定義はありません。各機関やメディアによって独自の考え方があり、たとえば、ニッセイ基礎研究所では「夫婦ともに年収700万円以上の世帯」をパワーカップルとして定義しています。
では、一般的な共働き家庭の収入はどのくらいなのでしょうか。総務省統計局の「家計調査報告 (家計収支編) 二人以上の世帯」の2023年調査によると、共働き世帯の1ヶ月の実収入は69万2,685円、年収に換算すると831万2,220円になります。
このうち、「世帯主が夫の世帯」の夫の平均収入は47万475円、妻の平均収入は17万9,939円です。これを年収に換算すると、夫の年収は564万5,700円、妻の年収は215万9,268円です。
パワーカップルに唯一の定義はありませんが、先述のとおり、ニッセイ基礎研究所では「夫婦ともに年収700万円以上」が指標となっています。一般的な共働き世帯と比べてみても、パワーカップルはかなり収入の多い世帯と言えるでしょう。
<パワーファミリーとは>
一方、パワーファミリーとは、日経ビジネスが定義した言葉で、「インフレ下でも消費意欲が衰えず、高い購買力が見込める世帯年収1,500万円以上の共働き家庭」を指します。
総務省の統計によると、夫婦それぞれが年収700万円以上の世帯(世帯年収1,400万円以上)の数は、2023年には40万世帯と10年前から倍増しています。このことから、世帯年収1,500万円以上のパワーファミリーの数も同様に伸びていることが推測できます。
さらに注目したいのは、この40万世帯のうち6割は子どものいる世帯であるということです。これまでは、子どものいない共働き夫婦である「DINKS」が消費の主なけん引役とされていましたが、実態としては子育て世帯が多く関連支出も多いのです。
このことから、世帯年収1,500万円以上で子どものいる世帯は新たに「パワーファミリー」と名付けられました。つまり、パワーカップルは子どもの有無を問わず使われるのに対し、パワーファミリーは「子どものいる世帯」を指すという違いがあります。
■パワーファミリーは、価値を感じるものにお金を使う
世帯年収1,500万円以上と、一般家庭に比べてかなり高収入なパワーファミリー。ただし、パワーファミリーは収入が高くても闇雲にお金を使うことを嫌い、「本当に必要なものや価値を感じるものにお金を使い、節約できるところは節約する」という堅実さがみられます。
野村総合研究所の「生活者1万人アンケート調査(2021年)」によると、パワーファミリーは「国内旅行」「趣味・レクリエーション関連」「子どもの教育・学習関連」「投資」などの分野に興味があり、全体と比較して「積極的にお金を使いたい」と答えた割合が多くなりました。
たとえば、「子どもの教育・学習関連」に積極的にお金を使いたいパワーファミリーは31%で、全世帯の平均より10ポイントも高い結果でした。パワーファミリーの多くは、親自身が良質な教育を受けてキャリアを築いてきたことから、「子どもにも同じような教育を受けさせたい」と考える傾向があるようです。
また、パワーファミリーは「投資」に関しても非常に勉強熱心で、積極的に資産運用を行うという特徴があります。スマートバンクが運営する家計簿アプリ「B/43(ビーヨンサン)」の利用者を対象としたアンケート(共働きの既婚者、世帯年収1,400万円以上)によると、パワーファミリーの1ヶ月当たりのNISA積立投資額は、5万~10万円未満が40%と最多でしたが、10万円以上という世帯も33%ありました。
一方、前出の野村総研のアンケートによると、「食料品関連」に積極的にお金を使いたいと答えたパワーファミリーの比率は40%で、全世帯平均より低い結果です。その代わり、休日の外食や旅行・趣味には惜しまずお金を使う「メリハリ消費」の傾向が見られます。
さらに、「多少値段が高くても、利便性の高いものを買う」と答えたパワーファミリーは6割にものぼり、全世帯平均の約4割を大きく上回っています。パワーファミリーは、ただ消費意欲が高いだけでなく、「自分なりの信条を持ち、価値を感じるものにお金を投じる」という共通の消費志向があるようです。
■今後はパワーファミリーが主流になる可能性も
世帯年収1,500万円以上のパワーファミリーは、現時点では全世帯のわずか3.5%に過ぎず、世帯年収1,000〜1,500万円未満の層を含めても全世帯の12%にとどまります。しかし、持続的な経済成長を背景に、将来的にはこれらの層が日本社会の主流となる可能性も指摘されています。パワーファミリーの存在感は、今後ますます大きくなるかもしれません。