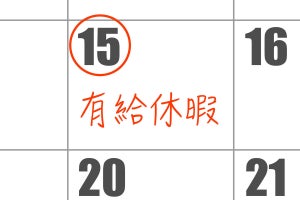心身のリフレッシュを図るために労働者の権利とされている年次有給休暇。雇用形態に関わらず全ての労働者が対象となる制度ですが、要件や付与日数について知らない人も多いでしょう。
そこで本記事では、年次有給休暇制度の概要やポイントをくわしく解説。また、労働者としてだけでなく事業主の立場として知っておきたい注意点などもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
年次有給休暇とは?
年次有給休暇とは「賃金が支払われる休暇日」のことで、労働基準法第39条で定められた権利として対象の労働者に付与されるものとなります。
特別な理由がある場合を除いて、雇用主側は労働者の有給休暇取得を拒否することはできません。
年次有給休暇が付与される要件
年次有給休暇が付与される労働者の条件は以下の通りです。
- 雇い入れの日から6ヶ月継続して勤務している
- 全労働日の8割以上出勤している
上記の法令上の要件を満たしていれば、正社員やパート・アルバイトなどの雇用形態を問わず全ての労働者が対象となります。
年次有給休暇の付与日数
年次有給休暇の日数は、労働者の勤続勤務年数に応じて変化します。
また、正社員・フルタイム勤務か、パート・アルバイトかによっても付与のされ方が異なりますので、日数の算出方法をくわしく確認しておきましょう。
通常の労働者(正社員・フルタイム勤務)の場合
正社員やフルタイム勤務といった通常の労働者の場合は、入社6ヶ月時に10日間の有給休暇が付与されます。
その後は勤続勤務年数に応じて付与日数が変化していき、勤務年数が長ければ長いほど付与される年次有給休暇の日数が多くなります。
| 年次有給休暇の付与日数(通常の労働者の場合) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤続年数 (年) |
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
| 付与日数 (日) |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パート・アルバイトの場合
パートやアルバイトで、週所定労働日数4日以下(週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は1年間の所定労働日数が216日以下)かつ労働時間30時間未満の場合は、勤続年数に応じて下記の年次有給休暇が付与されます。
正社員やフルタイムの人とは算出方法が異なりますので、下記表で確認しておきましょう。
| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務期間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 以上 |
|||
| 付与日数 | 4日 | 169 〜 216日 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121〜 168日 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
| 2日 | 73〜 120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
| 1日 | 48〜 72日 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | |
年次有給休暇制度のポイント
年次有給休暇制度には、付与条件や日数の算出方法以外にもいくつか覚えておきたいルールがあります。
知っておくと制度をより活用できるようになりますので、ポイントを押さえておきましょう。
半日や時間単位での取得も可能
一般的には1日単位で取得する年次有給休暇ですが、会社が半日単位や時間単位の年次有給休暇制度を導入している場合は、半日単位や時間単位で取得することも可能です。
繰り越しができる
正社員であれば最低でも年に10日は付与される年次有給休暇ですが、実際はなかなか使いきれないという人も多いでしょう。
しかし、年次有給休暇には2年間の請求権があるため、残った年次有給休暇は次の1年間まで繰り越しをすることが可能です。
ただし、付与されてから2年以上過ぎた場合は完全に時効消滅し、累積されることはありません。権利を無駄にしないためにも、できるだけ早めに請求することを心がけましょう。
取得理由は原則問われない
年次有給休暇を取得する際、上司や総務などが取得理由を聞いたり申請書の提出を求めたりするという会社は決して少なくないでしょう。
しかし、取得理由を告げないことが原因で会社側が有給休暇を取得させないという措置は労働基準法に違反するため、特に理由を告げる必要はありません。
申請においては、取得するという旨を伝えたり「私用のため」といっておいたりするだけで十分ですので、覚えておくようにしましょう。
買い取りは基本不可
仕事が忙しかったり取得のタイミングがつかめなかったりする人の中には、年次有給休暇の買い取りを望む人も多いでしょう。
しかし、労働者の休息という本来の趣旨に反するため、年次有給休暇の買い取りは基本的に法律違反となります。
ただし、退職時に有給休暇を消化しきれない場合や時効により消滅した年休を会社が買い取りを認めて制度化している場合は処理が可能なケースもあるため、就業規則などを事前に確認しておくといいでしょう。
年次有給休暇の注意点
半日や時間単位での取得も可能など、自分の都合に合わせて活用できる年次有給休暇。使い勝手のいい制度ですが、例外的なルールや細かな規定などを把握しておかないと、希望の日程で休暇が取れない可能性もあります。
ここからは年次有給休暇の注意点を解説しますので、制度をうまく活用するためにもしっかり理解しておきましょう。
また、労働者はもちろん事業主も把握しておくべき罰則などについてもあわせて紹介しますので、参考にしてみてください。
時季変更権
会社側は、基本的には労働者が取得したい日に年次有給休暇を使えるように配慮する必要がありますが、労働者が請求した時季に休暇を与えることが正常な事業運営を妨げる場合のみ、他の時季にその付与を変更する権利を持っています。
このように会社側が時季指定できる権利を「時季変更権」といい、事業所の規模や本人の業務内容などからその相当性が総合的に判断されることとなります。
したがって、労働者側は状況によっては希望の日程で年次有給休暇が取れない場合もあるため、注意するようにしましょう。
計画的付与
計画的付与とは、会社側があらかじめ休日を指定し、その日を年次有給休暇として労働者に付与する方法です。
年次有給休暇は、時季指定される場合を除いていつ取得しても問題ありませんが、実際は日々の業務に追われ取得のタイミングをつかめない人も少なくはありません。
そのような状況を改善するために事前に取得日を割り振る方法が計画的付与であり、ゴールデンウィークや年末年始の前後に有給休暇を付与して大型連休とすることなどがこれに当たります。
年5日の年次有給休暇取得が義務化
2019年4月から、労働基準法の改正により、全ての事業主が年10日以上の年次有給休暇を付与する必要がある労働者に対して、年5日の年次有給休暇を取得させることが義務づけられました。
これは取得率が低調な状況を改善するために制度化されたものであり、取得させなかった場合は企業側に30万以下の罰金刑が科されます。
違反対象となった労働者1人につき1罪として扱われるため、事業主側は注意して管理しなければなりません。
なお、事業主には労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければならないという義務もあります。
管理を怠ってしまうと監督署からの是正勧告や罰金支払い、訴訟リスクなどが発生するため、適切に労働者の休暇日数を管理する必要があることを覚えておきましょう。
制度の概要や注意点を理解して正しく活用しよう
働き方改革が叫ばれているものの、世界的に見てもまだ低水準である日本の年次有給休暇取得率。実際制度についてよく知らなかったり、どう取得すればいいのかわからなかったりする人は多いでしょう。
しかし、年次有給休暇は労働者の権利として当たり前に取得できるものであり、制度の概要や要点を理解すればすぐに活用することができます。
使用する上でのポイントや注意点をしっかり押さえ、心身の健康やゆとりのあるライフスタイルを送るためにも積極的に使用していきましょう。