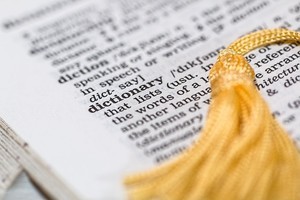令月という言葉をご存知でしょうか? 元号「令和」の由来となった言葉ですが、日常生活で使用する機会はあまりないかもしれません。本記事では、令月という言葉の意味や使い方、類義語についてくわしくご紹介します。
令月とはどういう意味?
令月には「めでたい月、何をするにもよいとされる月」という意味と、「陰暦(旧暦)における2月の別称」という意味のがあります。読み方は「れいげつ」です。
令月という言葉そのものの語源や由来は正式にはわかっていませんが、万葉集の『万葉集』巻五「梅花(うめのはな)歌三十二首(うたさんじゅうにしゅ)并(ならびに)序(じょ)」の一節に初春令月という言葉が載っていることから、古くから歌に使われていた言葉のようです。
令月とは具体的に何月のこと?
令月は陰暦(旧暦)における2月の別名としても使われていますが、「めでたい月、何をするにもよいとされる月」という意味でも使われます。この場合は、時期にかまわず自分にとっておめでたい月を令月と呼ぶことができます。書き手によっては、2月と意図していない場合もあるので注意が必要です。
令月の使用例
令月がどのように使用されているか、例文を含めご紹介します。令月は、「嘉辰令月(かしんれいげつ)」という四字熟語としても使用され、2月に生まれた子供の名前の由来になることもあります。
令月の例文
1、出産予定日が令月にあたり、両親がめでたいと喜んでくれた
2、令月に生まれた女の子が、「令子」と名付けられた
3、今月は令月なので、何かいいことが起きるかもしれない
4、今月は運が良すぎるので、令月かもしれない
このように、令月は「めでたい月」という意味で使われることが一般的です。 例文1から3は、令月=2月として書かれていますが、例文4では、今月を自分が勝手にめでたい月としていることが見てとれます。このように2月以外の使い方をしても大丈夫なのが、この令月という言葉の面白いところです。
「嘉辰令月」は「めでたい日」を表す四字熟語
令月を使った四字熟語に「嘉辰令月(かしんれいげつ)」があります。令月が縁起のいい月、または2月を指しますが、嘉辰令月には「めでたい月と日」という意味があり、月というくくりではなく特定の月の中の一日を指す言葉となっています。
嘉辰令月という言葉を分解して見てみると、「嘉」と「令」には「めでたい」「よい」という意味があり、「辰」は日のこと、「月」はそのまま「月」という意味なので、合わせて「めでたい日、めでたい月」となります。
令月は2月ともとれますが、「嘉辰」は特定の日を指すわけではないので、「嘉辰令月」という四字熟語として使う場合には、自分たちで選んだおめでたい日程をピンポイントで指すことができます。
・嘉辰令月を選んで、結婚式をおこなう
・一生に一度のマイホームを購入する日は、嘉辰令月を選ぼう
このように、とにかくおめでたい月日、縁起のいい日程としておめでたい行事とともに使われることが多い四字熟語です。
令月の「令」は子供の名前の由来にもなっている?
令月の「令」はめでたい意味を持つことから、子供の名前にもよく取り入れられている漢字です。2月生まれの子に「令」という漢字の入った名前をつけたり、令和に生まれた子に「令」という漢字の名前をつけたりと、人気の名前となっているようです。
女の子の名前の例としては、「英令奈(えれな)」「令衣(れい)」「令華(れいか)」などがあり、男の子の名前の例としては、「令凰(れお)」「令(はる、りょう)」「令真(りょうま)」などの名前があげられます。
令和の由来とは?
2019年5月1日に「平成」の次の元号が「令和」と発表されたことで、多くの人が注目したのが「令和」の由来。
首相官邸のホームページには、「令和」という元号は、万葉集にある「初春(しょしゅん)の令月(れいげつ)にして 気淑く風和らぎ 梅は鏡前の粉を披(ひら)き 蘭(らん)は珮後(はいご)の香(こう)を薫(かお)らす」という歌が由来であると書かれています。
令和という元号は、この歌に使用されている令月の「令」と「風和らぎ」というフレーズから作られたもので「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」という意味が込められているということです。
この「万葉集」とは、7世紀後半から8世紀後半にかけて作成され、現在に至るまで長年にわたって詠まれてきた、4,536首の歌を収める現存する日本国最古の歌集です。令和の元となった歌についてくわしく見てみましょう。
題名
巻五「梅花(うめのはな)歌三十二首(うたさんじゅうにしゅ)并(ならびに)序(じょ)」
意味
万葉集の五巻目、三十二首ある「梅花の歌」と序文
漢文
初春令月、気淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香
書き下し文
初春(しょしゅん)の令月(れいげつ)にして、気淑(きよ)く風(かぜ)和(やわら)ぎ、梅(うめ)は鏡前(きょうぜん)の粉(こ)を披(ひら)き、蘭(らん)は珮後(はいご)の香(こう)を薫(かお)らす
現代語訳
新春の好き月に、空気は澄み風がやわらかくそよぐ中で、梅は鏡の前で白粉をまとった美女のように白く咲き、蘭は香水のように良い香りを漂わせている
上記でご紹介した題名と漢文の間に実はもう1文、「天平二年正月十三日に、師(そち)の老(おきな)の宅(いへ)に萃(あつ)まりて、宴会を申(ひら)きき」という文が挟まれています。
この文が、この歌の背景を表した1文となっており、「天平二年正月十三日に大宰師である大伴旅人(おほとものたびと)という人物の邸宅に集まって、宴会を開いた」という意味を持っています。つまり、この歌はこの宴会の様子を歌った歌であるということがわかります。
令月の類義語
おめでたい意味が強い、縁起のいい令月という言葉ですが、類義語にはどのようなものがあるのか見ていきましょう。
■吉日
「祝事など、何かをするにはいい日、縁起のよい日」という意味の「吉日(きちじつ)」。吉日は主に大安を指すことが多いです。
「思い立ったが吉日」という言い回しを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。「思い立ったが吉日」とは「何かしようと思い立ったら、その日を吉日として即行動にうつすのがよい」という意味のことわざです。
令月がめでたい月を指しているのに対し、吉日はめでたい特定の日を指しています。月と日という違いはありますが、どちらも縁起がいいときをあらわす言葉として使われています。
■佳日
「よい日、めでたい日」という意味を持つ「佳日(かじつ)」。「嘉日」と書くこともあります。佳日は、吉日と同様の意味で、結婚式やお祝い事をする縁起のいい日を指します。
■好日
「晴れて気持ちのよい日、平穏ないい日」という意味を持つ「好日(こうじつ)」。佳日や吉日と少しだけニュアンスが異なり、縁起のいい日というよりは、気持ちがよく平穏な日を意味します。好日は、日常に頻繁にやってくる日という印象です。
令月という言葉の意味を正しく理解しよう
令月とは、めでたい月、縁起のいい月をあらわす言葉です。なかなか日常では使用することはない言葉ですが、元号の元になっていたり、子供の名前の由来になることがあったりと、気づかないうちに自然と目にしていることも少なくありません。おめでたい意味を持つ言葉の一つとして知っておきましょう。