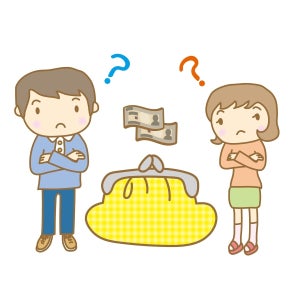国民年金は、20~60歳までの40年間のうち10年以上保険料を納めることで老齢基礎年金を受け取れる制度。もし、会社を退職したり、倒産やリストラ等で失業したり、事業を辞めたらどうすればよいのでしょう。そうした場合は年金の免除を受けることができます。
今回は、年金免除を受ける時の条件や申請方法、手順について解説します。
失業したら年金は免除されるの?
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度の手続きを行うことで、保険料の納付を免除することができます。
免除される額は、前年所得の基準(本人・世帯主・配偶者で判断)により、本人が申請を行うことで、全額、4分の3、半額、4分の1の額が免除されます。猶予についても、20歳から50歳未満の方で、前年所得の基準(本人・配偶者で判断)により、本人が申請を行うことで、保険料の猶予を受けることができます。
保険料の免除・納付猶予を行うことのメリットは、その期間については、年金の受給資格期間や年金額に反映させることができます。ただし、その期間は老齢基礎年金の年金額を計算するときには、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となってしまいます。
しかし、後述する保険料の追納を行うことにより、老齢基礎年金の受給額を増やすことはできます。保険料を未納している場合には老齢だけでなく、障害や死亡を理由とした年金を受給できない可能性もあるので注意する必要があります。もし、未納期間がある場合には納付状況を確認することをお勧めします。
年金免除の方法や手順
失業した場合には、失業等による特例免除を受けることができます。手続きには、雇用保険の被保険者であった方は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写しが、また、事業の廃止(廃業)や休止の届けを行っている方は、履歴事項全部証明書や税務署等の異動届出書、個人事業の開廃業等届出書等の添付書類が必要となってきます。
さらに必ず必要な書類として、年金手帳または基礎年金番号通知書が必要となってきます。
申請書の申請先は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口となります。詳細は、ご自身が住民登録している地域の市役所等の担当窓口でご確認ください。
年金保険料の追納制度
保険料免除・納付猶予は、10年以内であれば、追納して老齢基礎年金の受給額を満額まで増額することができます。追納した場合には、その期間は納付期間として扱われることになります。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。さらに、承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付することになります。申請には、年金事務所で行い、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。
国民年金保険料を追納した場合の例
課税所得金額が約300万円の場合
追納保険料額の年間合計が約40万円の場合は、所得税・住民税が約8万円減額されることになります。(所得税の税率10%、住民税の税率10%)
全額免除期間が2年間ある場合の年金受給額(平成21年4月以降)
つまり、2年間の国民年金保険料を追納することにより年間19,502円の年金受給額が増額されることとなります。
令和元年度中に追納する際の保険料
| 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度の月分 | 15,280円 | 11,450円 | 7,640円 | 3,810円 | |
| 平成22年度の月分 | 15,540円 | 11,650円 | 7,770円 | 3,880円 | |
| 平成23年度の月分 | 15,320円 | 11,490円 | 7,660円 | 3,830円 | |
| 平成24年度の月分 | 15,170円 | 11,380円 | 7,590円 | 3,790円 | |
| 平成25年度の月分 | 15,150円 | 11,360円 | 7,570円 | 3,790円 | |
| 平成26年度の月分 | 15,300円 | 11,470円 | 7,640円 | 3,820円 | |
| 平成27年度の月分 | 15,620円 | 11,710円 | 7,810円 | 3,910円 | |
| 平成28年度の月分 | 16,280円 | 12,200円 | 8,140円 | 4,060円 | |
| 平成29年度の月分 | 16,490円 | 12,370円 | 8,240円 | 4,120円 | 追納加算額はありません |
| 平成30年度の月分 | 16,340円 | 12,250円 | 8,170円 | 4,080円 | 追納加算額はありません |
※日本年金機構HP参照
年金免除の利用の仕方
免除の制度は、生活保護法の生活扶助を受けている人、障害年金(1級、2級)を受給している人、経済的な事情で保険料の支払いが困難な人、学生等が利用することができます。免除を受けることで、老齢基礎年金をもらうための加入期間に加算できます。
この加入期間は、平成29年8月から原則10年以上となっています。家計が苦しく、保険料を支払うことができなくても、手続きが面倒だからと放置することだけは避けましょう。未納のまま放置すると、2年が経過すると時効により保険料の納付ができなくなってしまいます。
年金免除の利用に関するまとめ
国民年金保険料の免除制度や納付猶予制度を受けるには所得要件等の条件があります。国民年金の免除は申請や届け出を行わないと受けられないので、免除が受けられるのを知らないために未納状態にしている方もおられると思います。
例えば、平成31年4月より国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の国民年金保険料が免除できることになりました。この期間の保険料は納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。国民年金の免除は申請や届け出を行わないと受けることができません。
免除のうち、申請免除(申請による免除)には、特例があり、例えば失業した場合には、本人の所得を除外して配偶者・世帯主だけの所得で判断されます。さらに、震災や火災等で損失があったときにも同様の特例があります。
もし、保険料を未納のまま放置している方も年金事務所で相談することで何か受けられる制度があるかもしれません。どうしても国民年金保険料を納めることが難しいという方は、年金事務所に一度ご相談することをお勧めします。