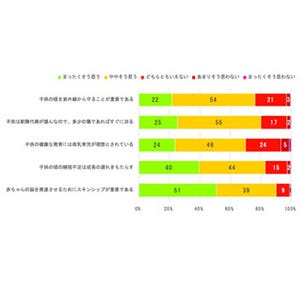保育園から子どもが発熱したとの連絡が入り、"朝は元気だったのにどうして? "と不思議に思うお母さんも多いのではないだろうか。わが子の急な発熱は誰だって動揺してしまうもの。初めての経験なら、なおさら不安になることだろう。今回は、子どもの急な発熱の原因と対処法について、まえだこどもクリニックの院長・伊庭大介先生に伺った。
原因の多くは「風邪」
子どもの平熱は36度前後。体温を測ってみて、37.5度以上ある場合は、発熱と捉えていいでしょう。ただし新生児の場合は、体温調整機能が未熟なため、衣類や環境の温度の影響を受けやすく、薄着にさせたら下がるというケースもあります。
子どもの発熱の多くは、風邪が原因。つまり、大人と同じで風邪の症状の一つとして発熱していることが多く、咳(せき)やくしゃみに始まり、頭痛や吐き気を伴うこともあります。赤ちゃんの場合は、生まれてから5カ月目ぐらいまでは、お母さんの体から移行した抗体が残っているので、感染症にかかりにくいとされています。個人差もありますが、徐々にお母さんからの抗体が少なくなり、5~6カ月頃から風邪などにかかり始めることが多いようです。
脳炎や髄膜炎など感染症の可能性も
一概に"子どもは発熱が多い"というわけではなく、人と接する機会が多ければ、風邪による発熱頻度も高くなるもの。もともと抗体がある子どもや、外で遊んだり人と接したりすることが少ない子どもは、発熱が少ない可能性もあります。逆に保育園に通っている子どもは、1カ月に何度も発熱してしまうなんてことも。
風邪のほかに、脳炎や髄膜炎、腹膜炎、中耳炎、尿路感染症(尿の通る経路に炎症が起きる病気)といった感染症も発熱の原因に。また、全身の血管に炎症が生じる川崎病、複数の臓器に炎症を引き起こす膠原(こうげん)病、悪性腫瘍など、さまざまな病気の可能性も考えられます。
すぐ病院に連れていったほうがいい?
熱があるからといって、必ずしもすぐ病院に行かなければならないというわけではありません。重要なのは容体です。熱があっても元気に動いていたり、スヤスヤと眠っていたりするようであれば、様子を見ても良いのです。反対に、一晩中グズッているなどつらそうな症状が見られるときや、2~3日熱が下がらないときには、病院に連れていきましょう。
とはいえ、夜間に発熱した場合は、すぐに病院に連れて行けるとは限りません。重症の場合は、救急車を呼ぶことも頭をよぎると思いますが、できるだけ落ち着いて判断することが大切です。もし救急車やタクシーで夜間救急病院にかけつけたとしても、小児救急は混んでいる可能性があります。軽度の症状と判断されれば、診察までに2~3時間待たされることも。お子さんも疲れてしまうと思いますので、容体が安定しているのであれば、翌日の午前中などに、かかりつけの医師に診てもらっても良いでしょう。
ただし、痙攣(けいれん)を起こした場合は、速やかに医師に診てもらうこと。痙攣が治まり、意識もあるようでしたら車やタクシーで病院に連れて行きましょう。痙攣が治まらない、または痙攣が治まっても意識が戻らない場合は、すぐに救急車を呼んでください。
自宅で看病するときの注意点
自宅で様子を見る場合は、水分補給を忘れずに。食欲があるようなら食事は普段と同じものでも問題はありませんが、嘔吐や下痢、腹痛がある場合は、おかゆなど消化の良いものを与えてください。食べ過ぎると、咳をしたときに吐いてしまうこともあるので注意が必要です。
また、発熱しているときは、汗をたくさんかいて暑いときと悪寒がするときとがあります。暑そうな場合はタオルなどで冷やして気持ちよくしてあげる、手足が冷たく寒くて震えているようであれば布団を重ねて温める、といったように状態に応じて看病をしてあげてください。ぬるま湯のおしぼりで体を拭いてあげると、体温が拡散されるので少し熱が下がります。
病院での治療法は?
病院では、基本的に月齢が3~4カ月にならないと、解熱剤は処方しないところがほとんどです。解熱剤を出せる場合は、粉薬やシロップ、座薬などから合ったものを選び、一度に5~6回分を処方します。解熱剤は、6~8時間おきに1日3回まで飲ませることができます。ただし、熱があってもニコニコしていたり機嫌よく遊んでいる状態であれば、解熱剤はむしろ使わないほうがいいでしょう。
注意したいのは、解熱剤は"熱を下げるための薬"ということ。解熱剤で熱の症状が治まったからといって、他の病気を見落とす可能性もあります。発熱しているかだけではなく、お子さんの些細な変化に気づくことが大切です。
乳幼児を過ぎて外で遊べる年齢になれば、自然と人との接触も増えていく。大人と違って、子どもは遠慮して咳やくしゃみをすることがないため、風邪による発熱を100%予防するのは難しいという。だからこそ、発熱一つに過剰に反応するのではなく、わが子の体調の変化に日々目を配り、冷静な対処をできるように心がけたいものだ。
※画像と本文は関係ありません
記事監修: 伊庭大介(いば・だいすけ)
まえだこどもクリニック院長。1999年に杏林大学医学部を卒業後、同大学医学部小児科医局に勤務し、2002年には同大学医学部小児科教室助手を務める。その後、賛育会病院新生児小児科勤務を経て、2012年より医療法人社団育真会 まえだこどもクリニック院長として、一般診療のほか、予防接種、乳児検診・育児検診、アレルギー診療など小児科全般の診療に携わる。