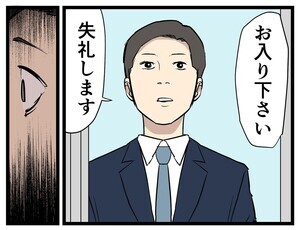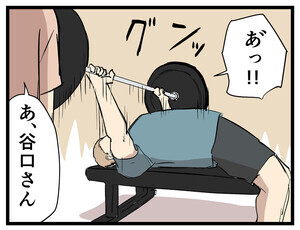まみ「そうそう、『アナと雪の女王』観たんですよね」
アヤ「神田さやか天才だったね」
まみ「あれ、私は号泣したんです。長女の置かれる環境っていうのがあまりにもリアルで、見てて初めてわかったことがすごくたくさんあって。私の場合は弟がいたんだけど、子どもで3、4歳違うってすごい体格差があるんだよね。体力も違うし。
私がちょっとしたいたずらのつもりでしたことで、弟がけがしちゃうってことがあったんですよね。打ち所が悪ければ大けがになってた。それで怒られたことがあったんですよ。
そのことを映画を見ててはっと思い出したの。私はその時から、何も考えずに、危ないことを予想せずに、無邪気な子供の遊び方をすることができなくなった」
アヤ「子供のとき?」
まみ「子供のとき。画用紙からはみ出すような絵を描くような子どもがいるけど、私はあんなことできないし、しようとも思ったことない」
アヤ「弟さんはどうしてるんですか」
まみ「弟は覚えてないと思いますよ。そう、覚えてないんだよね。大したことじゃないの。
でも、自分のほうは覚えてる。傷つけてしまったし、これ以上傷つけちゃいけないって思ってるから、それで自分を抑圧しちゃうんだよね。自分が何かすると悪いことが起きるから、してはいけないって。解放されるのはひとりの国だけ。上京して、家族と関係ない部屋を持ってから、やっと好きにできたんですよ。実家にいると、変な服を着たときの風当たりがすごかったからね。『なんで牛の柄着てるんだ!』って怒られたり」
アヤ「牛って言われると(笑)」
まみ「『せめてホルスタイン柄って言って!』みたいなね(笑)。
田舎だから保守的なんですよ。私はそのときビジュアル系のバンドにはまってて、ホットパンツとかはいてたんですけど、親が怒るんですよ。学校でXファンの友達と『なんで網タイツはいただけでお父さんって怒るんだろうねー』って愚痴り合ったりしてて」
アヤ「かわいいね」
おしゃれな人になりたかった
まみ「家では、そういうのがほんと鬱陶しかったです」
アヤ「才能を持て余したエルサだったんだ」
まみ「持て余してるのは牛柄だけだけどね(笑)。
そのときは親に負けたくない気持ちが強かったし、それがありのままの自分になりたいっていうことだったかというと、少し違ってた気がする。『おしゃれな人になりたい』って思ってた。ストリートスナップに載るような」
アヤ「東京出てきてから?」
まみ「東京出てきたら、叶ったの。CUTiEのストリートスナップに載ったんですよ」
アヤ「国会図書館に見に行こうかな」
まみ「すごい写真なの。ドラゴンの刺繍が入った黄色のベロアのTシャツに、赤いパンツはいてる」
アヤ「それ晒しじゃない?」
まみ「うわあって感じなんだけど、そのときは自分でかっこいいと思ってた」
アヤ「はじめて他者に、しかもおしゃれ媒体に、自分のファッション性を承認されたんだ」
まみ「それが私のエルサ状態だった。レリゴ~♪って。すごい迷走してましたね。変だってわかってるんだけど、変わってるってことで目立つ以外に、おしゃれな人に対抗する手段がわからないの。で、女っぽいことに抵抗があって、お化粧とかはできてないから、バランス悪いんですよ。すっぴんでドラゴンの刺繍って、どう考えても顔が負けるでしょ」
アヤ「惨敗だよね。それ見たい」
まみ「私も、当時H&Mや伊勢丹に一緒に行ってくれる友達がいてくれたらよかったな。そういう変わった服も、店の雰囲気に押されて買ってるんですよね。どの服が好きとかじゃなくて、『ここの服を買えばおしゃれになれる』と思って、その『おしゃれになれる代』を払ってた。ブランド名で買ってたんだよね。アーペーセー(A.P.C.)の服を買ってればおしゃれになれるって」
アヤ「アーペーセーってわかってないかも」
まみ「世代が違うからかな? 私が学生時代はおしゃれだったの、アーペーセー。エーピーシーで書くんだよ。それを『アーペーセー』って読めるだけで、もうおしゃれ特権階級って感じがした」
アヤ「あっ、あれアーペーセーって読むんだ!」
まみ「そう、フランス語読み」
アヤ「へんなの」
まみ「アーペーセーの店に来てる人たちはみんな堂々としてるし、これを着れば私も仲間入りできるって思ってて」
アヤ「その堂々ってほんとに堂々なのかな。それとも私たちみたいに内心実は虚勢張って頑張ってんのかな。店員が堂々としてんのはそもそもなんなんだろう」
まみ「店員さんは着慣れてるからかな」
アヤ「そっか」
まみ「自分の店では、モデルを兼ねてるようなものだから、堂々としていられるんじゃない?」
アヤ「おしゃれってほんとにどこまでいけばいいんだろうね……」
まみ「まず自信を持ちなさいってことをすごく言われるじゃないですか。でも、持ちようがなくないですか」
アヤ「自己肯定なんか無理なのかな」