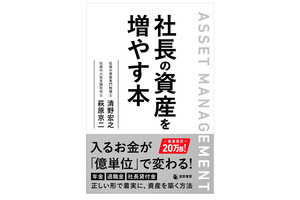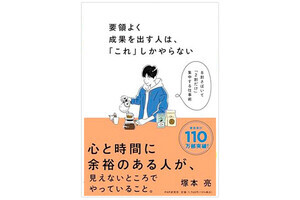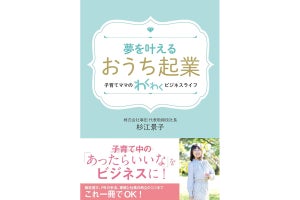日経BPは、このほど『若手はどう言えば動くのか? ~相手を「腹落ち」させたいときの伝え方~』(1,980円/ひきたよしあき著)を発売した。本書は、若手の成長を促し、チームの貴重な戦力になってもらうための「伝え方」を詰め込んだ一冊である。
著者は、大阪芸術大学放送学科客員教授、早稲田大学招聘講師であり、SmileWords代表取締役のひきたよしあき氏。同氏は、コミュニケーションコンサルタントとして上場企業や行政機関などでコミュニケーションスキルの指導を行っているほか、政治、行政、大手企業のスピーチライターとしても活動している。
今回は、本書の中から若手に対する指導についてを抜粋。パワハラや、相手が傷つくことを恐れて、指導に迷うリーダーも少なくないだろう。ここでは、威圧的にならず"しっかり伝わる注意の仕方"を紹介しているので、ぜひ参考にしてほしい。
■威圧的にならずしっかり伝わる! 注意の仕方、叱り方
【Case19】
パワハラだと言われるのが怖くて、やんわりとしか指導できません
【お悩みへのAnswer】
「守ってほしいポイント」を絞って、事前に周知しておく
■若手に 「猫なで声」 核心を突けない発言が増加
ここ10年弱の間に「働き方改革関連法」や「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」など、働き方に関する法律が次々、施行されました。部下を持ち始めたばかりの人からその上の上司まで、会社全体が、どのように若手を指導していいか分からない…それが正直なところではないでしょうか。
「こう言うとパワハラになるかな?」と思って、言いたいことが言えない。猫なで声でのふわふわした発言が増えるから、若手も「こんな会社で大丈夫かな」と不安になる。悪循環になってしまいます。
しかし、本当に強く注意するだけでパワハラになるのでしょうか?厚生労働省の「職場におけるハラスメント対策パンフレット」(2024年11月)によれば、職場におけるパワハラとは、
1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
3. 労働者の就業環境が害されるもの
であり、1から3までの3つの要素をすべて満たすものだとされています。さらに
「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません」
とも書かれています。具体的には、
「遅刻等社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をする」
「その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をする」
などが、パワハラには該当しない例として挙げられています(個別事案により判断は異なる)。
ただし、パンフレットにはこうも書かれています。「労働者に問題行動があった場合であっても、人格を否定するような言動等業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動がなされれば、当然、職場におけるパワーハラスメントに当たり得ます」。
暴言や暴力、人格否定など、相手を傷つける行為を慎むべきなのは言うまでもありません。また、自分では許されると思って発した言葉でも相手は違う受け止め方をする可能性があるため注意が必要です。まずはこの原則をしっかり頭に入れておきましょう。
■「ここだけは重視する」というポリシーを日頃から伝える
その上で、業務に必要な注意をどう伝えればいいのか。そもそも、声を荒げたり、普段から高圧的な態度を取ったりする必要は全くありません。私がおすすめしたいのは、普段は優しいけれど、必要な注意はしっかり伝える、「虎の尾を持つキャラクター」に変わることです。
私の知り合いに、大手メーカーの幹部Yさんがいます。笑顔を絶やさない穏やかな人で、「こんなに優しくて、部下をまとめることができるのかな」とチラッと思うこともありました。ある時打ち合わせをしていると、Yさんの部下が会議に遅れてきた。するとYさんはビシッとした声で、
「いつも私は、時間は守るように、と言っているでしょう。遅れる場合は連絡を入れてください!」
と言ったのです。部下は神妙な顔をし、頭を下げました。別の機会にその部下から話を聞くと、
「Yさん、他のことでは優しいんですけど、『時間を守る』が持論らしく、これを破ると厳しく注意されるんです。いわゆる虎の尾を踏んだ状態です」
とささやいてくれました。
これが、Yさんが多くの部下をまとめる秘訣だったんですね。「時間を守る」という持論を日頃から周りの人に伝えている。それを虎の尾にして、踏んだ人は注意する。すると部下は、上司の優しい人柄の中に、厳しさを見ます。
ここのポイントは3つあります。
1.虎の尾(=曲げられないポリシー)を、普段から周囲に伝えておく
急に怒っては相手も驚いてしまいます。「この点については守ってほしい」というポイントを普段から伝えておくことで、相手がその「虎の尾」を踏んだ場合に、しっかりと注意することが可能になります。
2.「虎の尾」の数は絞る
「取引先に迷惑をかけないでほしい」「完成させる前に必ず確認に来てほしい」など、「これだけは守ってほしい」と思うポイントを1〜2個に絞りましょう。その際、重箱の隅をつつくような細かい内容は避けるべきです。
3.「傷つきました」と言われても持論を曲げない
若手のなかには、強く注意するとすぐに「傷つきました」「辞めたいです」などと、へそを曲げる人もいます。しかし「絶対に守ってほしい」ポイントを事前に伝えていたのですから、持論を曲げず、虎の尾は虎の尾として持ち続けてください。
■若手に効く、「外に出たときに通用できる人になってほしい」
先ほどの幹部Yさんには当時、小学生の娘さんがいました。のんびりした子で、何をやっても時間ギリギリになっていたそうです。
「私は、子どもの教育も、部下の指導もあまり変わりがないと思っているんです。要は、外に出たときに恥ずかしくない人間になってほしいということ。部下には、社内ではなく、社外に出たときに通用する人間になってほしいと考えているんです」
この考え方が、若手の共感を呼ぶようです。Yさんは、社内で出世する人材よりも、どこの会社でも通用する人材を育てるほうが大切だと思ってきたと言います。
「だから、時間を守るとか、服装とか、会話のマナーとか、人としての基本的なところにうるさくなってしまうんですよ」
と笑う姿を見て、「社会に通用する人間」を育てる気概が伝わってきました。
親が子どもを育てるという視点に立てば、「やんわりとしか指導できない」なんて甘っちょろいことは言っていられません。まず若手に、
「私はあなたを、この会社の中だけでなく、外に出ても立派に通用する人間になってほしいと思っている」
と宣言をする。若手が気にしている「同級生はもっとスキルを身につけているのではないか」とか「ネットを見ると、同じ年でキラキラしている人がいて焦る」といった気持ちに応え、「私が指導するのは、社外に出たときに役立つことだ」と分かってもらう。ミドル世代と若手が共通の目的意識を持てば、当たり障りのない指導から脱却できるのではないでしょうか。
やんわりとした指導は、法律が改正されるばかりで現場では会社の若手教育の方向が定まらないのが大きな原因です。
あなたのせいではありません。こういう時期だからこそ、「会社」ではなく「社会」という単位で、1人の人間を育てる気持ちで若手に向かっていってほしい。そういうリーダーを、人生の先輩を、若手も求めているはずです。
まとめ:「会社の外でも通用する人間を育てる」気持ちで、若手に向かっていこう
書籍『若手はどう言えば動くのか? ~相手を「腹落ち」させたいときの伝え方~』(1,980円/ひきたよしあき著)
ここで伝えた内容以外にも、本書では若手を動かすための「言葉の選び方」や「自分で考えて動く若手の育て方」などを詳しく解説している。気になる方は、ぜひチェックしてみてほしい。
イラスト/こつじゆい