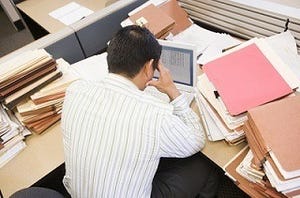前回は「仕事を始める前にするべきこと」というテーマで、仕事を任されたときにすぐに作業に着手してはならないというお話をしました。今回は、定時上がりを実現するために「出社してすぐにやるべきこと」をお伝えします。
出社してすぐに目の前の仕事に着手してはならない
出社したらPCを起動してメールをチェック、急ぎの案件があればすぐに返信して残りは一旦、後回し。そういや昨日作り終えられなかった報告資料があったから続きをやらなきゃ。でも先輩から依頼されていた市場調査の件もあったな。とりあえず、すぐにできそうなところから手を付けるか。
出社後、このような感じで働き始めてはいませんか?
次から次へと仕事を見つけ、すぐにできることからスピーディーにこなしていく。傍から見ると「仕事ができる人」に見えるかもしれません。しかし、こういう人こそ「定時」に帰れない落とし穴にはまってしまう危険性が高いのです。その危険性と対策について、3つの観点からお伝えします。
その1:その日の仕事の全体像を把握する
出社してすぐに目の前にある仕事から片づけるという姿勢を取っているということは、裏を返すと目の前にない仕事が放置されるということになります。ある仕事が目の前になかったとしても、それをしなくて良いということにはなりません。
そのため、その日の仕事の全体像を見通さないまま時間が過ぎていくと、夕方になって上司から「先週頼んだ例の件、今日が締め切りだけど、まだ終わってない?」と聞かれて慌てふためき、がっつり残業するはめになりかねません。
そうならないために出社して真っ先にやるべきことは、「その日にすべき仕事の全体像」を明確にすることであり、可能ならやるべきことをリスト化することです。それによってその日の仕事を可視化し、作業の漏れを予防することができます。
また、リスト化する際は思いつくままに記述するのではなく、大まかな業務区分から細かいタスクへと落とし込む方法をお勧めします。例えば経理であれば「決算関連業務」「債権・債務管理業務」等の業務区分を先に書き出しておき、その下に「伝票入力」「売掛金計上」等のタスクを挙げていくのです。そうすることで、作業漏れの予防効果を高められます。
なお、作成した業務区分に該当しないタスクを思いついた際には、つい「その他」という区分を作って、そこに入れてしまいたくなりますが、それを続けると「その他」が肥大化して業務区分の意味がなくなってしまうので、できる限り「その他」以外で的確な業務区分を追加するか、既存の業務区分を見直して、そこに入れるようにしましょう。
その2:仕事に優先順位を付ける
目の前にある仕事から手を付けることの危険性は、仕事の全体像が見えないことだけに留まりません。それは優先順位を全く考慮せずに仕事を進めていることに他ならないのです。その弊害は、急ぎの対応に間に合わなくなってしまったり、逆に急ぎの案件だけに受動的に対応するばかりで長期的に重要な仕事がなおざりになってしまったり、というような形で表れます。
極端な例ですが、先に目について着手した仕事の期限が3日後で、それが終わってほっとしたところで、当日中が期限の仕事の存在に気が付いたときは、すでに定時間際だったとか、「急ぎではないから」と部下の育成に必要なスキル評価レポートの作成が、いつまでたっても手付かずのまま残ってしまうなどということが起こってしまいます。
そうならないために、仕事の優先度を「緊急度」と「重要度」の2軸で評価しましょう。そして「緊急度と重要度が共に高いもの」を優先度"高"、「緊急度か重要度のいずれか一つが高いもの」を優先度"中"、そして「緊急度と重要度が共に低いもの」を優先度"低"と定義し、基本的には優先度が高いものから順に取り掛かります。その際、パソコンやノート、またはホワイトボードなどに2軸のマトリクスと、そこに仕事を割り振った図を記入しておくと、仕事の合間に確認しやすくなるのでお勧めです。
また、ノートに記入する際は消せるボールペン、ホワイドボードでは付箋を使うと新しくタスクを追加する際にも修正や調整ができて便利です。
その3:時間配分を決める
出社してすぐに目の前の仕事に取り掛かることの3つ目の危険性は「何の仕事にどれだけの時間をかけるのか」という時間配分が見えないままに仕事を進めることにあります。
例えば一日の勤務時間が8時間とすると、当たり前ですがすべての仕事にかける時間の合計が8時間以下でなければ定時には帰れません。そして休憩や集中力が切れる時間、移動時間なども考慮すると実質的に使える時間は8時間より大分短くなるはずです。
この8時間弱という貴重な時間の範囲内で、「その日にやるべきこと」を「優先順位に従って」進めていく際に「各々、どれだけの時間がかかりそうか」を予めざっくりと見積もるのです。その合計が8時間の枠に収まるのであればそれでよし、枠を超えるのであれば短縮化する術はないか、または優先度の低いタスクを後回しにできないかを考慮し、それも難しければ他に余裕のありそうな人に手伝ってもらえないか、と可能性を探っていきます。
なお、時間配分の合計が勤務時間と同等と見積もった場合は大抵、残業が発生します。通常、仕事をしていると出社時には想定していなかった案件が急に飛び込んできたり、作業中に思わぬトラブルに見舞われたりするなど、イレギュラーな仕事が発生するからです。そのため時間配分を考える際には、勤務時間が8時間なら合計7時間で済むような時間配分にするなど余裕を持たせることが重要です。
以上3点、出社してすぐに動き出すことの危険性と対応策を「仕事の全体像」「優先順位」「時間配分」の観点からご紹介しました。出社したら仕事に取り掛かる前に、これら3つに対応することで定時帰りを達成してもらえれば幸いです。
著者プロフィール:相原秀哉(あいはら ひでや)

|
株式会社ビジネスウォリアーズ代表取締役
慶應義塾大学大学院修了後、IBMビジネスコンサルティングサービス(現日本IBM)入社。グローバルスタンダードの業務改革手法、Lean Six Sigmaを活用したコンサルティングを得意とし、2012年に日本IBMで初めて同手法の伝道師 "Lean Master"に 認定される。その後、幅広い組織や個人の生産性向上に寄与するべく独立。生産性向上による働き方改革コンサルティングや、コンサルティングスキルを実践形式で学べるビジネスブートキャンプを手掛ける。