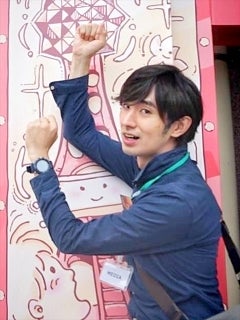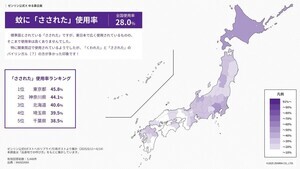沖縄本島から南西に約430km、そこには大小19の島々からなる八重山諸島が点在している。西表島、石垣島、与那国島、波照間島……。それぞれの島はお互いに影響を受けながらも、独自の文化を育んできた。さて先日、西表島を訪れて沖縄離島の素晴らしさに圧倒された筆者。東京の寒さが佳境を迎える2月初旬、カチンコチンに冷え切った身体を南の島で解凍しようと、再び八重山諸島に足が向いた。今回の目的地は赤瓦の屋根、水牛車、ハイビスカス、星砂浜などで知られる竹富島だ。
羽田からの直行便で新石垣空港(南ぬ島 石垣空港)に降り立つと、すでに空気が温かく柔らかい。上着のコートも必要ないようだ。そこから石垣島のフェリー乗り場までバスで移動し、さらに高速船に乗るとわずか乗船10分で竹富島に到着した。なるほどアクセスが抜群に良い。
フェリー内で開いたガイドブックによれば、竹富島は平坦な土地が続く周囲9.2kmの小さな離島。島内には山も川もないという。大自然のスペクタクルが待ち受けていた西表島とはまるで正反対だ。移動はレンタサイクルが適しているということで、下船し、港からほど近い場所で自転車を借りる。
2月というのに穏やかな気候。頬をなでる南風が心地良い。少し走ったところで、赤瓦屋根の町並みが始まった。屋敷の塀は、大きな琉球石灰岩を手積みしたもの。門に、屋根に、表情豊かなシーサーが鎮座している。
集落は、まるごと国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されているという。道端には綺麗な花。テンニンギクだろうか。白い砂の道をシャリシャリ言わせながら、ただ黙々と自転車を走らせていく。
青い海も見てみたい。そこで一路、海岸線に向かう。地図を確認すると、ただひたすらに続く1本道。方向音痴の筆者でも道に迷う心配はなさそうだ。
到着したのは、星型の砂が堆積するカイジ浜(星砂浜)。透き通るような青い海と白い砂浜が視線の先に見えてきた。
誰もいないサンゴの浜辺で、ただただ打ち寄せる波の音を聞く。なんとも贅沢な時間。
そこから自転車で5分、観光客に人気の海水浴場「コンドイ浜」にも足を運んだ。
水牛と祭りと観光客と
「竹富島を訪れた観光客の皆さんの多くは、フェリーの最終便で帰ってしまうんですよ。だから昼間は賑わうこの砂浜も、17時過ぎには静かになる。ここに暮らす島民は夕方に訪れて、おにぎりでも食べながら、落ちる夕日をのんびり眺めて過ごしています」と話すのは、一般財団法人 竹富島地域自然資産財団の理事長 上勢頭篤さん。"癒やしのコンドイ浜"と表現する。
温暖な気候は、住んでいる人の気質にも影響をおよぼすのだろうか。語り口が穏やかだ。「歴史の古い海岸です。この砂浜にはカントゥイナーと呼ばれる"ニーラン神"の入る石があります。いわゆるニラカナイ信仰です。現在も旧暦8月8日の朝早く、竹富公民館と神司はカントゥイナーに参詣し、『新しい世が迎えられますように』と祈り、トンチャー(歌謡)を謡います」。
...アガートー カーラー クールー フーニーヤー...
...バーガーイーヌー トーンーチャーーマー...
夕暮れの迫る白い砂浜で、その神事で謡われる一節を披露してくれた。
竹富島には、島内最大の神事「種子取祭」(たなどぅい)がある。実に600年の歴史があるそうだ。そして驚くのは、島内で行われる祭事・行事の多さ。年間で20近くも実施されている。なかには何日間も続く祭りもあるため、島ではほぼ毎月、何らかの祭事・行事をしている計算になる。
ところでその昔、島民は祭りの際に海岸の白い砂を水牛車で運び、家々に蒔いていた。このとき「ついでに人も乗せてくれ」という要望があった。これが後に、水牛車観光へとつながったという。
話はさらに遡る。現在、島内のあちらこちらで見かける水牛だが、本来、竹富島には1頭もいなかったそうだ。上勢頭さんによれば、竹富島は稲作に不向きな土地だった。そのため人々は、近隣の由布島に耕作地をもうけていた。ところが昭和44年にエルシー台風が八重山諸島を襲う。「うちのジーチャンの時代です。人も動物も、水没する由布島から逃げ延びました。そのとき、竹富島に水牛が来たわけです」と上勢頭さん。歴史の生き証人から、こうした話を聞けるのが嬉しい。
やがて水牛車が島の集落を練り歩くようになった。コロナ前の観光最盛期には、水牛車で渋滞が起こるほどの賑わいを見せたという。しかし観光客が増え過ぎたため、マナーの問題、ゴミの問題、騒音の問題が発生した。幸い、いま町はコロナ禍により一時的に静けさを取り戻しているが……。このタイミングで竹富島は「島内観光のあるべき姿」を見つめ直している。
「これまでも種子取祭のハイライトにあたる2日間は観光業をストップさせていましたが、今年は別の祭りの開催時にも(年4回ほど)町の文化を保護するため、観光客の受け入れ方を検討しようかという話が出ています」(上勢頭さん)。
この日、宿泊したホテルでは夕食に石垣牛のすき焼きをいただいた。これが肉厚で脂がのっており格別。キンキンに冷えたオリオンビールも身体中に染み渡った。東京の喧騒を忘れ、島内のゆっくりとした時間の流れに身をまかせる。頑張った自分にご褒美の時間だ。
夕食後は、満天の星空を求めて「星空ナイトツアー」に繰り出した。次回に続く。
取材協力: 竹富町