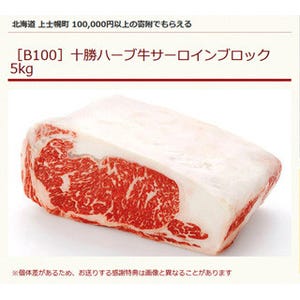新連載「主婦が新聞読んで聞いてみた」では、商社出身のフリーライターで主婦の楢戸ひかる氏が、新聞を読んで疑問に思ったテーマを、主婦目線で調べて読者の方々と共有します。
最近、よく見聞きする「マイナンバー」という言葉。何となくは知っているけれど、実態となると、おぼつかない。秋には制度が始まると聞いたので、疑問に思っている点を内閣府マイナンバー制度コールセンターに電話で聞いてみた。
――そもそも、マイナンバーって、何ですか?
社会保障と税金、災害対策に使う番号で、12桁の数字で構成されています。日本国内に住民票がある全ての人に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として、引越をして住所地が変わっても、一度指定されたマイナンバーは、生涯変わりません。
――なぜ住民票コードをそのまま使わないのですか?
「住民票コード」はもともと今回のような利用を想定しておらず、運用の大幅な改変が必要になることや、パブリックコメントの多数意見が「新しい番号の利用」だったことが主な理由です。
――マイナンバー制のメリットは何ですか?
期待される効果は、大きくわけて3つあります。
- 所得や行政サービスの受給状況を把握しやくなります。
マイナンバーで管理することにより、負担を不当に免れることや、給付を不正に受け取ることを防止するとともに、本当に困っている方に、きめ細やかな支援を行えるようになります。これは、公平公正な社会の実現の役立つものです。
- 書類作成の手間が削減されます。
行政の手続きが簡素化され、国民の皆様が、行政書類を作成する負担が軽減されます。たとえば、平成29年1月~7月を目途に、社会保障や税、災害対策の手続で住民票の写しなどの添付が不要になります。また、行政機関が持っている自分(個人の)情報の照会が楽になったり、予防接種など行政から受けられるサービスの通知なども、各人が受け取れるようになります。
- 行政機関や地方公共団体の作業軽減化につながります。
データの照会や転記、作業の重複などのムダが減り、公務員の労力が大幅に削減されることで、税金のムダ使いが減ります。
――いつから始まるんですか?
2015年10月5日の住民票をもとに、附番されます。それ以降に住民票の住所の世帯主宛に、家族全員の紙製の通知カードが送られてきます。制度自体の運用は、2016年1月からです。
――私達は、どんな時に使う機会があるのですか?
社会保険分野、たとえば年金資格取得や確認給付、雇用保険の取得や確認給付、ハローワーク、医療保険の保険料の徴収、福祉分野の給付、生活保護などを受ける際に、申請書にマイナンバーの記載が必要になります。税金の場合は確定申告書時に、災害の際は災害者生活再建支援金の支給などの際に、マイナンバーの記載が必要です。
――自分のマイナンバーは、どのように保管すればいいのですか?
むやみに人に見せたりするものではないので、送付された通知カードを自宅で大切に保管して下さい。
――個人情報の流出が話題になっていますが、大丈夫なんですか?
マイナンバーについては、制度上の保護措置と、システム上の安全措置という二つの観点から対策を講じています。
- 制度の保護措置
マイナンバーの利用範囲に法律上の規定を設けるとともにそれに違反した人には厳しい罰則を設けています。法律上の規定とは、「誰が、どんな時にマイナンバーを扱えるのか」を規定しているということです。罰則の中で一番重いものは、4年以下の懲役または200万以下の罰金となります。
- システム上の安全措置
マイナンバー制度では、個人情報が同じところで管理されることはありません。例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は市役所に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理されます。このように、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」の仕組みを採用しており、マイナンバー(個人番号)をもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはありません。それゆえ、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。
主婦的感想
内閣府に「マイナンバー制度コールセンター」が設置されているということに、まず驚いた。「マイナンバー制度コールセンター」は、法人用と個人用に分かれており、私は個人用の方に何度が問い合わせをしたが、毎回、すぐに繋がった。
疑問に思っている点を、個人として問い合わせできる窓口があるのは、国と直接、繋がっているようでうれしい。国民にマイナンバー制度を浸透させたい、という国の『本気』が伝わってきた。
筆者プロフィール: 楢戸 ひかる(ならと ひかる)
1969年生まれ 丸紅勤務を経てフリーライターへ。中学生と小学生の男児3人を育てる主婦でもある。メルマガ「主婦が始める長期投資」(メルマガ申し込みは、「主婦er」より)を書き始めて、視野の狭さを痛感。新聞を真面目に読もうと決意し、疑問点は取材に行く所存。