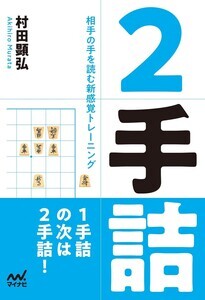史上最年少名人・七冠という偉業を達成し、無人の荒野を進むかのように歴史を塗り替え続けている藤井聡太竜王・名人。日本将棋連盟が刊行する『令和5年版 将棋年鑑 2023年』の巻頭特集ロングインタビューの取材に際して、藤井竜王・名人の回答からにじみ出た言外のニュアンスからインタビュアーが感じた藤井像に迫ろうという連載の第4回です。
今回は研究・実戦についての考え方を掘り下げて聞いた部分をご紹介します。藤井竜王・名人の将棋観を感じ取ってください。
藤井竜王・名人にとってAI研究は負担ではない!?
今回、藤井先生にインタビューするにあたって、ぜひ聞いてみたいことがありました。
それは「AI研究の負担について」です。
現代将棋では相手より1手でも研究手順が長ければ、つまりAIが示す最善手や評価値を少しでも先まで知っていれば、それだけで有利と言われます。 しかしそうなると、将棋が「研究合戦」のような状態になってしまい、棋士は日々研究に追われることになります。現代の棋士にとって宿命のようなものかもしれませんが、この大変さについて藤井先生はどう考えているのか聞きたいと思っていました。
――思うのですが、相居飛車の場合、同じ戦法を先手でも後手でも指すことになりますよね。
藤井「はい」
――そうすると、同じ戦法の中で先手番の研究と後手番の研究を並行して行う感じになるのでしょうか。
藤井「定跡を考えるというのは先後どちらの立場でも有力な手を考えるということなので、どちらかをよくしようという意識はないです。特に角換わりなどはシンプルに『定跡を考えている』という側面が強いです」
――定跡を考えている……。なるほど。どちらかの手番に偏って考えているわけではないのですね。AIが登場したことで今の棋士は研究が大変になったということを耳にしますが、藤井先生もそう感じますか?
藤井「それは特にはないです」
――えっ! そうなんですか。
藤井「自分の場合、一局ごとに作戦を立てるということはしていないので」
驚いたことに藤井先生は、研究を大変だと感じていませんでした。
研究が大変なのは当然で、その中でどうやって工夫してやっているか、という話になると思っていたので、「そもそも大変だと思っていない」というのには衝撃を受けました。
話の続きをご覧ください。
――常に満遍なく定跡を考えている、ということでしょうか。
藤井「そうですね。直近の対局にそれほど関係なく定跡の作成と更新をしているという感じです」
――すごく大変なことをしているのに藤井先生が大変だと思っていないだけ、という可能性もあるのかなと思ったのですが。
藤井「いや、一局ごとに作戦を考える方に比べれば、自分のほうがやることは少ないはずです。作戦の意図というか趣旨を生かすにはある程度深い理解が必要なので、毎回違う作戦をしようと思うとそこでの大変さは出てくると思います。自分の場合は定跡作成は定跡作成として行っていて、実戦で有利に立つためにやっているということではないので、そこは負担ということはないです」
つまり、藤井先生は〇〇戦の第△局はこの作戦で行こう!そこで優勢になるように研究しておこう!という動きをしていないのですね。 自分の中でひたすら「定跡作成」をしていると。