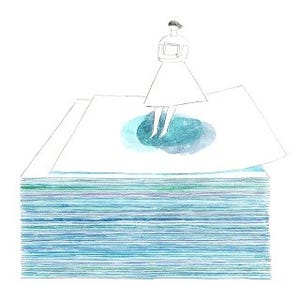待ち合わせの場所に立っているとき、紅緒の前髪を小さな雫が揺らした。雨が降ってきたのだ。雅弘からは少し遅れるというメールが来ていた。紅緒は周りを見回し、近くのゲームセンターの軒先に入り込んだ。
うるさいゲーム機に囲まれて、自分がひどく場違いなところに迷い込んだような心細い気持ちになったとき、何か知っているものが目に留まった。
コインを入れてレバーを回す、ガシャポンの機械。そこに、紅緒が子どもの頃に観ていた、普通の女の子が戦う女の子へと変身するときに使うコンパクトがあった。 確か、昔、買ってもらったことがあったな、と懐かしく思って見ていると、後ろから肩を叩かれた。
「遅くなってごめん、降ってきたな」
会社帰りのスーツ姿の雅弘は、いつも、笑ったときだけ元気に見える。営業用の顔が貼り付いてしまったのかもしれない。元気に見せる癖だけが、顔についてしまっている。 「これ、懐かしくて」
紅緒がガシャポンを見せると、普段、チープなものを嫌う紅緒がそんなものを見ていたことがおかしかったらしく、雅弘は本当に愉快そうな顔になった。笑顔が本物になっていった。
「買ってやるよ。どれが欲しいの? 種類があるんでしょ。出るまで回そう」
完全に面白がっている。紅緒はいちばん初期のコンパクトが欲しい、と言った。昔持っていたものと同じものだ。雅弘がコインを入れ、紅緒がレバーを回す。四度目でやっと、目当てのものが出てきた。
そっと開くと、ミニチュアながらちゃんと鏡がついていて、中には小さなものなら入れられるくらいのスペースがあった。
あまり感情を顔に出さない紅緒の、うれしがっている気配を雅弘は敏感に察知する。コンパクトを手に取ってじっと眺めている紅緒のことを、雅弘は見つめ、「もう出ちゃったのか。もっとたくさん回しても良かったのに」と、両替して余ったコインを残念そうに見つめた。
その夜、雅弘の部屋で、紅緒は外したピアスをコンパクトの中に入れた。誕生石のトパーズの小さなピアスで、いつもどこかに置くと、なくしてしまいそうで不安に思っていた。
コンパクトがそんなふうに自分と雅弘の日常にぴったりと、必要なものとして入り込んできたことが、紅緒にかすかな充足をもたらした。
紅緒は、一ヶ月後に異動になった。慣れない部署に突然入ることになり、すでにできあがっている人間関係にも溶け込めず、仕事の内容もわからず、取り残されたような気持ちで毎日を過ごすことになった。
コンパクトの中には、不安を鎮める薬が入るようになった。泣きそうにつらいとき、どうしても会社に行きたくないとき、逃げ出したくなるとき、コンパクトの中の魔法の薬が助けてくれた。
紅緒はそのうち、雅弘が何をしてくれても心から喜べなくなっていった。サービス精神が旺盛で、紅緒を喜ばせるために細やかな心遣いができる雅弘は、落ち込んでいる紅緒を元気づけようと、紅緒の故郷でしか売っていない、紅緒の大好物の、チョコレートでくるんだりんごのお菓子を取り寄せて突然渡してくれたり、いかにも紅緒が好きそうな、貝殻の形をした石鹸をきれいな箱に詰め合わせて持ってきてくれたりした。
日常から離れたほうがいいかもしれない、と、遠くにドライブに連れていってくれたり、旅行に誘ってくれたりもした。それらの気遣いが、紅緒には重荷になっていった。ただ「ありがとう」と、いつものように喜んで、微笑んで見せればいい。それだけのことをするのに、全身の力を使うくらいの労力が要った。疲れ切った人間にとって、喜ぶというのはこんなに重労働なのか、と思った。
雅弘は、紅緒の笑顔が「本物ではない」ことに気づいていた。そして、紅緒を救えないことに無力感をつのらせていった。努力をする人なだけに、余計に「何も力になれない」ということが、雅弘にはひどく空虚なことに感じられたようだった。
「俺といても、紅緒は幸せになれないから」
最後にそう言った雅弘の顔は、ひどく疲れていて、生のままの男の、セクシーな表情をしていた。
「でも、困ったら、いつでも連絡してほしい」
心配そうに、名残惜しそうにつけ加える雅弘の優しさが、紅緒の罪悪感をかき立てた。自分といても、雅弘は幸せになれない。紅緒もそう思った。戻る気もなければ、都合のいいときにだけ頼る便利な男にしたくもなかった。
最後の力を振り絞るようにして、紅緒はひとりの時間を生きた。会社に行き、するべきことをただ、淡々とした。帰ると疲れ切って、お化粧を落とすこともせずベッドに潜り込んだ。泣けるときはまだ、心が元気なのだと知った。涙も出てこない乾いた夜を、紅緒はひとりで耐えた。
そのうち、ちょっとした、どうでもいいようなことが紅緒を楽しませてくれるようになった。仕事帰りにふと見かけて入った写真展、化粧品を買うために寄ったデパートで通りすがりに見た美しいバッグ、つけっぱなしのテレビでやっていた映画。生きている限り、心臓は絶え間なく動き続けているのだと、紅緒は自分の心に教えられているような気がした。
少しずつ元気を取り戻していった頃、化粧ポーチの中に、塗装のはげかけた小さなコンパクトを見つけた。ずっと前に、そんな小さなケースには入り切らないほど薬の量が多くなり、使わなくなっていたものだった。使わなくても、お守りのように持っていた。そして、今ではもう、薬を飲む必要はなくなっていた。
紅緒はそれを取り出し、手のひらに乗せ、じっと眺めた。メッキの金色が光る、なにかとても尊いものが、そこには残っていた。
<著者プロフィール>
雨宮まみ
ライター。いわゆる男性向けエロ本の編集を経て、フリーのライターに。著書に「ちょっと普通じゃない曲がりくねった女道」を書いた自伝エッセイ『女子をこじらせて』、対談集『だって、女子だもん!!』(ともにポット出版)がある。恋愛や女であることと素直に向き合えない「女子の自意識」をテーマに『音楽と人』『SPRiNG』『宝島』などで連載中。マイナビニュースでの連載を書籍化した『ずっと独身でいるつもり?』(KKベストセラーズ)を昨年上梓。最新刊は『女の子よ銃を取れ』(平凡社)。
イラスト: 安福望