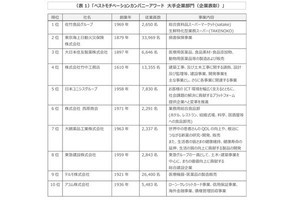昨今、リモートワークや業務効率化により、組織内での上司と部下の対話が減少しています。それにより、目先の業務以外で部下と何をどう話せばいいか分からないという上司も現れてきています。
そこで本連載では、組織内において部下の継続的成果と成長を支援し、さらにエンゲージメントを高めるために行う、対話のフレームワーク「すり合わせ9ボックス」を活用して、上司が「部下をダメにする話し方」について考察してみましょう。
すり合わせ9ボックスとは
すり合わせ9ボックスは、上司と部下が対話すべき3つの要素(業務・個人・組織)を、さらに3つの時間軸(過去・現在・未来)で分けた、計9つのテーマで構成したのです。
2回目の今回は、「振り返り(業務×過去)ボックス」についてです。
上司のアドバイスが部下の成長機会を奪っている
もし現在、あなたの周囲で部下が指示待ちで言われたことしかやらない。自発的に考えない、動かない。という「結果」があるとするならば、必然的にそうなる「原因・プロセス」があるはずです。
つまり、自ら考えて動かない部下がいるのは、考えさせない組織の仕組みや考えさせない上司との関わりがあるのです。
一般的に、ピラミッド組織は上から下への指示命令で動くようにできています。いわゆる上意下達です。ですから、問題があれば部下は上司に伝えて、上司に判断を委ねて回答・指示を待つという考えない癖ができてしまいます。
もちろん、自分で考えて動く人もいますが、構造上そうなりやすいのです。
そして、このコミュニケーションパターンに上司も慣れています。ですから、上司は部下の問題を速やかに引き取って、アドバイスや指示を出してしまいます。
部下が成長しない振り返りのパターン
以下は、業務で問題のあったことについて、上記のパターンで「振り返り」を行う場面です。
上司 「なんで今回納期に遅れたの?」
部下 「はい。先方の担当の方が、結構アバウトな人だったので『そんなに細かく詰めなくても任せてくれているのかな』と思って勝手に進めてしまって、先方の意向とのズレが生じたのが主な原因です」
上司 「そんなのさ、勝手に判断しちゃダメでしょ。思い込みが一番怖いから」
部下 「はい」
上司 「俺の経験上、考えがアバウトな人って、一見何でも良さそうなんだけど実はこだわりあったりするんだよ。だから、しっかり相手のニーズを落とし込んであげないとダメなんだよね」
部下 「はい」
上司 「今後、自分で勝手に判断しないで、ちゃんと相手に確認してね」
部下 「はい。次からそういう意識でやっていきたいと思います」
上司が正解をアドバイスします。このようなコミュニケーションにより、果たしてその後部下に変化が起こるのか? は、本人次第にはなりますが、得てしてこのような正論は頭では理解できますが、なかなか腹落ちまでしないことの方が多いでしょう。
さらに、このようなコミュニケーションは、正論を言っている上司のエネルギーが高まり、聞いているだけの部下のエネルギーは下がりがちです。これでは、次への変化も起こりづらい。
そしてここでの一番の問題は、部下が成長するために必要な「考える機会」を奪っていることです。
しかし、なぜ上司はこのようなコミュニケーションパターンになりがちなのでしょうか? それは、「成果軸」で考えているから。効率的に成果を出すためには、上司が持っている答えを早く部下に渡した方が、早く成果が上がるからです。
部下の成長のために行うことは「部下の考えを整理するお手伝い」
一方、部下に考えてもらうコミュニケーションを取るためには、「成長軸」を前提として対話する必要があります。現場では成果軸、一歩引いて振り返りを行う場面では成長軸で部下と接する切り分けが必要です。
そのうえで、部下が自らの頭を働かせてアイデアや気付きを得るために、部下にたくさん語ってもらえるよう、上司は支援をします。私はこれを、「部下の考えを整理するお手伝い」と言っています。実際には、抽象度の高い言葉を具体化したり、曖昧な点をクリアにしていく質問を投げかけたりします。
以下は、問題のあったことについて「振り返り」のサポートを行うパターンです。
上司 「今回、納期に遅れた原因を自分なりに分析するとどうかな?」
部下 「はい。先方の担当の方が、結構アバウトな人だったので『そんなに細かく詰めなくても任せてくれているのかな』と思って勝手に進めてしまって、先方の意向とのズレが生じたのが主な原因です」
上司 「そう。ちなみに結構アバウトな人っていうのは(どういう意味)?」
部下 「はい。担当の方は、いつも私に案件を丸投げなのです」
上司 「丸投げ……。信頼されていたってことかな?」
部下 「最低限の信頼はもちろんあったと思いますが、忙しい方なので、極力任せたいという意識が強かったのではないかと思います」
上司 「なるほど。相手の心理を推察できるのはいいね。では今回は担当の方の心理にどんな変化があったのだろう? 何が違ったのかな?」
部下 「確かに、そこは聞けてなかったです。ただそういえば、私に『お願いします』と依頼した後に、『私の方でもちょっと考えます』って言っていた気がします。今回は自身でもじっくり考えたかった案件だったのかもしれないですね」
上司 「うん。そこは確認したいね」
部下 「はい。いつもと同じように考えてしまっていました。次回お会いする時にじっくりと聞きたいと思います」
上司 「あらためて、今回の納期遅れからの顧客対応について、どんな学びがあったかな?」
部下 「とにかく自分勝手に判断しないことですね。そうならないために、毎回相手に『これで良いですか?』という確認を取ることを実践しなきゃ、と思いました」
上司 「いいね。それってすぐ実践できそうだけど、実際これから行っていくイメージはありますか?」
部下 「はい。まさに今日別のお客様のアポイントがあるので、早速そこで実践していきたいと思います」
上司 「いいね」
成長を考えるなら上司は答えを言うべきではない
このように、「自分勝手に判断しない。確認を取る」という教訓は同じですが、はじめの会話は、上司の教訓の部下へのアドバイスであり、後の会話は、部下自らが経験によって導き出した学びや教訓です。
人は相手から言われたことよりも、自分自身で見出したことの方がコミット意識が高まるのは自明でしょう。上司は(上司の)答えを言うのではなく、部下の答えを引き出す関わりをしていくことが部下の成長促進のためには必要となります。
今回、部下が教訓を導き出せたのは、上司の関わりによって新たな考えが浮かんで、たくさん話ができたからです。ぜひ、このような観点で部下との振り返りの時間を持ってみてください。