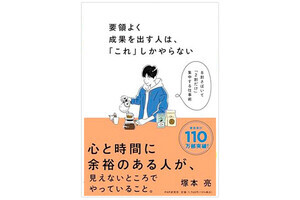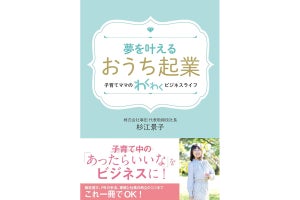日経BPは、このほど『できるリーダーが「1人のとき」にやっていること マネジメントの結果は「部下と接する前」に決まっている』(1,980円/大野栄一著)を発売した。本書は、優秀なリーダーが持つ力についてひも解き、リーダーシップの質を高める「1人の時間」の重要性や過ごし方のヒントについて解説した一冊である。
■チームのエネルギーを高めるリーダーになるには
では、エネルギーを高めるリーダーになるにはどのようにしたらいいでしょうか。実はこの問いに対しては、すでに本書でヒントとなることを示しています。それは、「思考の檻にとらわれずに考え、問うこと」です。
「自分はどこに向かいたいのか?」
「何を成し遂げたいのか?」
「その目的地にたどり着くために必要なことは何か?」
リーダーがこうした問いを持つことで進むべき道が明確になり、志が高まります。
■エネルギーは「Be」に着目して循環させる
エネルギーに関しては、高めることを目指すよりも、適切にマネジメントすることが重要です。
エネルギーの効果的な管理手法として、「凝固型」「波型」「循環型」の 3つのアプローチがあります。 3つのアプローチ方法を理解し、適切に活用することが、組織や個人のエネルギーを最適化につながります。
ここでは、「1カ月で売上を20%向上させる」という目的があるとして3つのアプローチそれぞれでPDCAを回し、その違いを見ていきます。なお、どのアプローチでも、施策は「新製品の販売促進キャンペーンを実施する」とします。
3つのアプローチの一番の違いは、「どこに焦点を当てるか―行動(Do)か、結果(Have)か、状態(Be)か」です。
①凝固型=Doにフォーカス
成果を生むのは「適切な行動の積み重ね」であり、PDCAは継続的なプロセスであるべきだと考えます。
・Plan(計画):市場分析をもとに、具体的な施策を策定させる。
・Do(実行):組織の力を活用し、計画を確実に実行する。
・Check(評価):データを重視し、成果とプロセスの両面を振り返る。
・Action(改善):次の施策を検討し、プロセス全体を最適化する。
経営とは、成果を上げることです。行動の量と質を高め、計画的な実行と改善を続けることで、継続的な成長を実現します。
ただし、「行動」を重視しすぎると、組織の柔軟性が失われるリスクもあります。また不足感と正解を探す確実性を探索するようになります。
②波型=Haveにフォーカス
「結果を所有すること」に着目し、成功を拡大するか、失敗を管理するかのどちらかに舵を切ります。
・Plan(計画):目標達成のための戦略を明確にし、最もインパクトの大きい施策を選定する。
・Do(実行):最小限のリソースで最大の成果を出せる方法をとる。
・Check(評価):売上データを分析し、成功パターンを見極める。
・Action(改善):成功すれば、さらにスケールさせるための手を打つ。失敗すれば、徹底的にコントロールし、細部まで介入してリスクを最小化する。
競争ではなく独占を狙います。成功したら加速し、失敗したら徹底的に修正するというアプローチは、スタートアップの成長戦略に近いです。
ただし、結果という状況に振り回されると、組織の安定性を欠く可能性があります。そこに属する人も代替の利く部品として扱われる可能性が高まります。
③循環型=Beにフォーカス
「状態がすべてを生み出す」という考え方を持ち、チームの精神的なエネルギーを最大化することに注力します。
・Plan(計画):売上向上という目標ではなく、「この製品が市場に与える価値」をチームで深く共有する。
・Do(実行):メンバーが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、マインドのインスピレーションと健全なる身体のコンディショニングを与える。
・Check(評価):個々のメンバーの状態を観察し、必要に応じて励ましやフィードバックを行う。
・Action(改善):チームの創造力とエネルギーが循環する環境を整え、革新的なアクションが自然に生まれるようにする。
顧客は、「自分が何を求めているか」を基本的にわかっていません。市場やデータに左右されるのではなく、「チームが何を信じ、どんな状態で働くか」が革新を生むという思想になります。
そのため、循環型のPDCAは、「状態を整えることで、自然と行動や結果がついてくる」というアプローチを取ります。
・安定した成果を求めるなら→凝固型(Do)
・大胆な成長を狙うなら→波型(Have)
・革新を生み出したいなら→循環型(Be)
という傾向はありますが、どれが良い悪いではありません。どのアプローチを採用するかは、組織の文化や戦略、リーダーの哲学によって異なってきます。どれかひとつに偏るのではなく、状況に応じて組み合わせることで、組織の持続的な成長が可能になります。
また、多くの人は「Do(行動)→Have(成果)→Be(状態)」の順序でものごとを考えがちですが、これでは真の満足感を得られないことがあります。
まず「Be(すでにそうである)」を整え、そこから「Do(行動)」を起こすことで、自然と「Have(成果)」が得られるという考え方が大切です。この順序を意識することで、無理なく望む成果を手に入れることができます。
・喚起力を高めるための「1人の時間」の使い方①
現場ではDoに目が向きがちに。落ち着いて部下のBeに目を向ける時間を持つ。
書籍『できるリーダーが「1人のとき」にやっていること マネジメントの結果は「部下と接する前」に決まっている』(1,980円/大野栄一著)
同書では、本稿で紹介した以外にも、チームや部下のリソースを引き出すリーダーの力について多数解説している。気になる方はぜひチェックしてみてほしい。
イラスト: 村林タカノブ