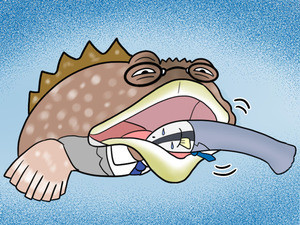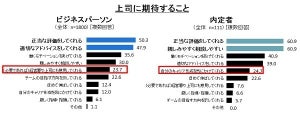シリーズ第1回では、6月29日に国会で成立した働き方改革関連法改正の概要について紹介しました。しかし働き方改革は法律で定められた項目だけに限った取り組みではありません。
大きな時代の潮流であり、これまでも多くの企業が取り組んできており、実績を上げています。
背景には少子高齢化による構造的で切実な人材不足やグローバル化があり、また大手広告代理店での新卒社員の過労自殺というセンセーショナルな事件が起きたことも大きなきっかけとなりました。
「人が足りないからワンオペで無理を強いる」という悪循環では企業が破綻する、ということが誰の目にも明らかになったのです。
それに合わせて企業トップの価値観や常識も大きく変わりつつあります。働き方改革の実行と成功は、経営トップの宣言と旗振りが必須といってよいでしょう。
働きがいと生産性向上
働き方改革のテーマは、大きく分けて長時間労働の削減、休暇の促進、多様な働き方の実現、この3つに分けられます。誰もが快適に働いて(働きがいの確立)、パフォーマンスを上げる(生産性向上)ことができる企業になることです。
今回は、法改正に先がけて働き方改革を実行し、成果を上げている事例を施策ごとに紹介します。
テレワーク
会社のオフィス以外で勤務をすることで、リモートワークともいいます。在宅勤務が中心ですが、IT技術や情報端末の進歩により、自宅から近いサテライトオフィスやカフェなどで執務することも可能な時代になりました。
通勤時間や体力を消耗することなく、最近では育児や介護のみならず全社員を対象とする企業も増えてきました。
朝型勤務制度
大手総合商社が社長主導で導入したことで、一気に広まったワークスタイルです。ラッシュアワーが始まる前の6~7時台から執務を始めることで、気持ちよく思考や企画の質を高めることができます。
人間が集中して仕事ができる時間は1日せいぜい6時間ですから、午後3~5時には退社して、夕方以降は学習や余暇、家族との団らんに充てることができます。
業務シェアリング
独力では困難な仕事をチームで担当し、チームであふれそうな仕事を組織の垣根を超えて支援し合う業務シェアリングです。
業務量や進捗、労働時間がリアルタイムで共有できるシステムと、あらかじめ他組織の支援が可能なマルチ業務型の人材育成やマニュアル整備によって実現することができます。
週4日正社員、プチバイト
週5日働いて2日休むフルタイム社員が大半の日本ですが、最近は大手アパレル企業のように週4日働いて3日休む週4正社員制度を持つ企業も出てきました。
1日10時間×4日で週40時間フルタイムとすることもできますし、短時間勤務制度を採用することもできます。
中には1日2時間程度のプチバイトを上手に活用しているドラッグストアやコンビニチェーンなどの取組も見られます。
フレキシブルフライデー、集中タイム
2017年に政府が月末金曜日に早帰りを推奨するプレミアム・フライデーを提唱しました。実効性には疑問も多いですが、あきらめるには及びません。
1日の労働時間を短くするために、フレキシブルフライデー(月1回は金曜日に早帰り)やラッキーフライデー(土日と祝日が重なるときは金曜日を休暇とする)、集中タイム(1日2時間を打ち合せも電話もシャットアウトして自分の業務に集中)など、職場ぐるみで様々なアイデアを試してみることが大切ですね。
ユニーク休暇
休日や夏季休暇、年末年始休暇だけでなく、会社独自のアイデアで有給休暇を与えるユニークな休暇制度が多くなりました。
勤続5年ごとに一定期間を連続して休めるリフレッシュ休暇、サバティカル休暇、飛び石連休をつないで長期休暇にするブリッジ休暇、バースデイ休暇、ボランティア休暇、資格試験に備えるチャレンジ休暇などアイデアは多彩です。
計画年休制度
年次有給休暇の取得率は2017年で50%弱。これを政府は2020年までに70%にする目標を掲げています。法改正により一人あたり年5日の取得も義務化されました。
「結果的に取得できなかった」ではなく「前もって取得する日を申請または指定しておく」ことで、前向きに堂々と有休取得を促進することができます。
育児休暇
育児休暇や介護休暇のように法律で認められている休暇はもちろん、入学式や授業参観など家族のイベントに参加するための休暇、バースディ休暇や記念日休暇など、様々なライフサポート休暇を設ける企業が増えています。
年次有給休暇の取得促進策とする場合と、独自の有給休暇としてアドオンする場合があります。
CWOの任命
働き方改革を戦略的に企画実行するために、社長や人事部が音頭をとることが多いですが、CWO(チーフ・ワークスタイル・オフィサー)を任命してプロジェクト化し、経営ガバナンスとしての責任を明確化する企業も現れています。
BPR、業務サポートシステムの導入
アナログで無駄の多い手作業を整理して、業務フローを再構築して成果を上げている企業も多数あります。
BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)や業務サポートシステムというと資金力のある大企業のみが実現できると思われがちですが、比較的安価なIT技術やバーコードリーダ―などのツールを使うことで、中小企業やベンチャー企業のローコストでの成功例も多く出ています。
働き方改革が成功したその先には、二つの風景が広がるでしょう。一つは社員が本来の生きがいと働きがいを見出し、輝いていること。
二つ目は、その企業がイノベーションと生産性向上という果実を手にしていることです。採用競争力を高める施策としても有効です。多くのビジネスパーソンと企業にトライしていただきたいと思います。

|
著者プロフィール : 米澤 実(よねざわ みのる)
社会保険労務士事務所 米澤人事コンサルティングオフィス代表
千葉県船橋市出身。株式会社リクルート(現リクルート・ホールディングス)でクリエイティブディレクター、ライン組織マネジメント、グループ企業の人事部長を経て、2010年独立。現在は「元気で強い成長企業の実現を支援する人事労務コンサルタント」として活動している。