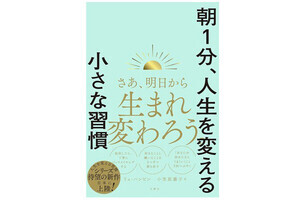ビジネスパーソンが“今読むべき本”を厳選し、要約してそのエッセンスを伝える「flier(フライヤー)」。最新のトレンドを学んだり、読みたい本を見つけたりするためのツールとして、累計122万人のユーザーに活用されています。
この記事では、flierを利用する意識の高いビジネスパーソンの中でも特に、20代~30代のユーザーが今、リアルに読んでいる本とその傾向を紹介します。同世代のビジネスパーソンは今、どんな本を読んでいるのでしょうか? なぜその本が選ばれたのでしょうか? 気になった本があれば、ぜひチェックしてみてくださいね!
「ゆるい職場」時代、Z世代はどう働く?
2月の1位は『会社はあなたを育ててくれない』(古屋星斗、大和書房)でした。
リクルートワークス研究所主任研究員で、『ゆるい職場』『なぜ「若手を育てる」のは今、こんなに難しいのか』などの著書を持つ古屋星斗さんの最新作。現代の職場環境を鋭く分析し、その課題を浮き彫りにする古谷さんの作品は、毎回大きな話題を呼んでいます。 かつて日本の職場では、経験のない若者を会社が一人前になるまで育てるのが当たり前でした。ところが労働環境が変わり、「会社が育ててくれない」時代となったのです。今は長時間労働の減少や休暇が取りやすくなったなど、働きやすい環境が整いつつあります。その一方で、能力や経験の差を「個人」が請け負わないといけなくなった状況は、特に若い世代にとって大きな不安要素となっています。
本書では、現代の若手社会人がどのようにキャリアを描いていくべきかを多様な視点から提示しています。これからの時代を生きるビジネスパーソン必読の一冊です。
部下がついてこない…。新米マネジャー必読の書
2位は、『部下をもったらいちばん最初に読む本』(橋本拓也、アチーブメント出版)。「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」で総合グランプリを受賞した、いま話題の書籍です。
昇進して初めて部下ができたものの、マネジメントがうまくいかない――。そんな悩みを持つ新米マネジャー向けに書かれたのが本書です。
著者の橋本拓也さんは、新卒3年目で初めて管理職に就いた際、メンバーと信頼関係が築けず、異動や退職が続く苦い経験をしました。そこで取り組んだのが、「リードマネジメント」です。
リードマネジメントとは選択理論心理学を基盤とした、「メンバーの成長を通して組織パフォーマンスを最大化すること」を目指す手法。リードマネジメントを取り入れてからは、マネジャーとしての力を発揮し、現在は取締役として1300名以上のメンバーを統括する立場になりました。
本書では、リードマネジメントの考え方・やり方について詳しく解説しています。メンバーの力を引き出し、チーム力を向上させたいマネジャーは読んでみてはいかがでしょうか。
誰でも理解できる! 「説明のコツ」がわかる本
3位は『頭のいい説明「すぐできる」コツ』(鶴野充茂、三笠書房)でした。
どうしたらスッキリとわかりやすい説明ができるようになるのでしょうか? 本書に掲載される「頭のいい人」がやっている説明のコツを、一部ご紹介します。
・相手が聞きやすい順に話す
自分が思いついた順番ではなく、相手の聞きやすさに合わせること。具体的には「大きい情報」→「小さい情報」の順番だとわかりやすい。
・相手に「心の準備」をさせる
相手に聞く準備ができていないと、何を言っても伝わりません。本題に入る前に「ご相談があるのですが」などと「話の種類」を前置きすることで、相手はスムーズに聞く姿勢に入ることができます。
・「相手が聞きたい情報」を厳選する
ビジネスシーンでは、なるべく不要な言葉をカットして話を短くすることが鉄則。「聞き手の聞きたいこと」を考えて、その重要度から伝える情報を選びましょう。
話題の書から、ビジネスと人生のヒントを得よう
今月はビジネス関連の書籍が上位にランクイン。新年度に向けてエンジンをかけているマイナビ世代の姿が見えたランキングとなりました。
本の要約サービスflierには、他にも、ビジネススキルを磨きたいときや自分とじっくり向き合いたいときに役立つ書籍が多くそろっています。2月のランキングでは、『世界の一流は「休日」に何をしているのか』(越川慎司、クロスメディア・パブリッシング)、『読むだけで数字センスがみるみるよくなる本』(深沢真太郎、三笠書房)、『「この人なら!」と秒で信頼される声と話し方』(下間都代子、日本実業出版社)、『仕事のできる人がやっている減らす習慣』(中村一也、フォレスト出版)などがベスト10にランクインしました。
来月はどのような本が注目を集めるのか、楽しみにしていただければ幸いです。