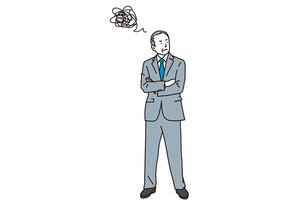独立してビジネスを開始するとき、多かれ少なかれ開業資金は必要です。事業内容によっては自己資金でまかなうのは難しいため、融資を受ける必要があります。
今回は開業資金を借り入れる方法として、日本政策金融公庫の融資制度などを紹介します。開業資金を調達するための参考資料としてください。
開業で必要な資金は2種類ある
開業で必要な費用は、設備費用と運転資金の2種類あります。事業をスムーズに立ち上げるには、それぞれの資金がどの程度かかるのかを把握することが大切です。
設備費用
設備費用は、設備の導入や設置に関する費用のことです。エアコンや換気設備、ガスや給湯器、パーテーションなどが代表的です。場合によってはリフォームや内装工事も必要となり、その工事費も設備費用です。
また、事業で用いる機械や事務機器などの設備も該当します。業態によって異なりますが、多くの機器を揃えることが必要なケースもあります。購入する以外に、リースをする方法もあるため、検討するのもよいでしょう。
運転資金
運転資金とは、事業を継続させるために発生する資金のことで、以下のようなものがあります。
- 人件費
- 水道光熱費
- 原材料や商品の仕入れ代金
- 広告宣伝費
- 通信・インターネット関連の費用
店舗で働く従業員の人件費、電気・ガス、原材料の仕入れ代金などは、事業を継続するうえで必要不可欠です。目安として、開業時には最低でも3ヶ月分の運転資金を準備しておく必要があります。
開業資金を借り入れる方法4つ
業態によって異なりますが、開業資金は数百万円から1,000万円程度かかることが一般的です。すべて自己資金で用意するのは難しく、借り入れをするケースが多いでしょう。
開業資金を借りる方法として、主に以下4つがあります。
日本政策金融公庫の融資制度
日本政策金融公庫とは、国が運営している政策金融機関です。民間の金融機関では手が回らない領域を補完するために設立されました。
個人事業主や中小企業を対象に事業資金の貸付を行っており、開業資金を借り入れる際の有力な候補の1つです。具体的には「新規開業資金」の制度があり、年齢などの条件を満たすと、一般よりさらに低金利で借りられることもあります。
日本政策金融公庫を利用するメリットは、民間よりも金利が低いこと、無担保・無保証の制度もあることです。創業初期でも申し込みやすいですが、審査を受ける必要があり、審査期間も長めになっていることに注意しましょう。
自治体・金融機関の制度融資
制度融資とは、自治体が金融機関・信用保証協会と連携して行う融資制度です。個人事業主や中小企業のスムーズな資金調達を支援することを目的として運営されています。
信用保証協会は、返済できなくなった場合に、残債を返済する機関です。信用保証協会による保証があることで、金融機関は貸し付けたお金を回収しやすくなるため、個人事業主や中小企業も融資を受けやすくなります。
制度融資は、民間の金融機関よりも低金利で借り入れができるケースがあります。ただし、利息だけでなく信用保証料の負担も発生することが注意点です。
ビジネスローン・不動産投資ローン
銀行や信用金庫などが取り扱う、事業資金を借り入れるためのローンです。担保・保証人が不要で、資金の使途に制限がないため、幅広い運転資金・設備資金として活用できます。
融資までの期間が短いのも特徴で、最短の場合は即日で融資を受けられるケースもあります。急いで借り入れをする必要があるときには便利でしょう。
ただし、金利は他の方法に比べて高いため、返済の負担は大きくなります。融資上限額もあまり高くなく、個人事業主は利用できないこともある点に注意しましょう。
日本政策金融公庫で利用できる融資制度3つ
開業資金を借り入れる方法は複数ありますが、創業で初めて借りるなら、日本政策金融公庫がおすすめです。ここからは、日本政策金融公庫の融資制度のうち、創業を対象にした制度を3つ解説します。
新規開業資金
新規に開業する方、または事業開始後おおむね7年以内の方が利用できる融資制度です。融資限度額は7,200万円で、うち運転資金は4,800万円が上限となっています。
返済期間は設備資金が20年以内、運転資金が10年以内で、据置期間は5年以内です。返済期間が長めに取られているため、無理なく返済しやすくなっています。
新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)
女性や若者・シニアを対象として、企業や開業をサポートする融資制度です。新たに起業・開業する方、事業開始後おおむね7年以内の方のうち、女性の方・35歳未満の方・55歳以上の方のいずれかに当てはまる場合に利用できます。
こちらの融資制度では、先ほどの新規開業資金で適用される金利よりも低金利で融資を受けられるのがメリットです。年齢や性別などの要件を満たせば有利な条件で借り入れができるため、当てはまる場合は積極的に利用しましょう。
新規開業資金(再挑戦支援関連)
過去に廃業したことがあり、また開業にチャレンジする方を対象にした融資制度です。こちらで調達した資金を、以前営んでいた事業における借り入れの返済に充てることもできます。
利用するには、次のすべてに該当する必要があります。
- 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
- 廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人である
- 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込みなどである
- 廃業の理由・事情がやむを得ないものなどである
開業資金を借り入れるためのポイント
資金を融資してもらうには、審査に通過する必要があります。ここでは、審査にパスするための重要ポイントを4つ解説します。
事業計画書をしっかり作成する
融資に申し込む際には、事業計画書の提出が求められます。金融機関が融資をするか審査をする際に、事業計画書は重要な資料です。
事業計画書をしっかりとした内容にすれば、事業の継続性などの説得力が増し、審査に通る可能性が高まります。以下のような内容をしっかりと記載しましょう。
- 創業の動機
- 経営者の経歴
- 取扱商品・サービス
- 取引先・取引関係
- 借り入れの状況
- 事業の見通し
- 必要な資金と調達方法
ただ単に記載するのではなく、「アピール」と「根拠のある数字」を示すことが大切です。
資金の用途を明らかにする
事業計画書では、資金の用途も重要なポイントの1つです。借り入れた資金をどのように使うのか、用途を明確に説明する必要があります。
曖昧な説明では通用しませんので、「この機材を5つ導入するから○○円」「運転資金がこれだけ必要だから3ヶ月分として○○円」といったように、具体的に記載しなくてはなりません。
自己資金を多めに用意する
自己資金が多いほど、審査にパスする確率は高くなります。自己資金が多ければ、すぐ資金不足に陥る可能性は低い、返済できる根拠があるなどと判断されるためです。
目安として、融資希望額の3分の1程度の自己資金を用意できるとよいでしょう。
しっかりプレゼンをする
融資を受ける際、ほとんどのケースでは審査担当者との面談を受けることになります。30分~1時間程度で、伝えるべき情報をわかりやすくプレゼンする必要があります。
常識的な服装・態度を心がけることはもちろん、緊張しすぎないことも重要です。担当者から質問もされますが、あわてず落ち着いて対応しましょう。
借り入れ以外で開業資金を調達する方法
融資以外にも、開業資金を調達する方法はいくつかあります。十分な額を借り入れられそうにない場合や、借り入れを多くしたくない場合に検討してみてはいかがでしょうか。
補助金・助成金
自治体では、制度融資とは別に、創業を対象にした補助金・助成金の制度を用意しているケースがあります。補助金や助成金は融資と異なり、返済不要なのがメリットです。
たとえば東京都では「創業助成事業」を行っており、創業初期の経費の3分の2を、上限300万円まで助成しています。
助成金や補助金は返済不要な分、対象や条件が限定され、審査も甘くはない傾向です。事業計画書などをしっかり準備して申し込みましょう。
クラウドファンディング
資金調達方法として、クラウドファンディングも一般的になりつつあります。事業計画や目的をWebで公開し、賛同してもらえた方から少額ずつ資金を集める方法です。
クラウドファンディングには、対価を求めない「寄付型」、商品・サービスを提供する「購入型」、分配金などを配る「金融型」があります。事業の内容にあったタイプを選びましょう。
クラウドファンディングは商品・サービスの宣伝効果もあるのがメリットですが、目標額に到達しなければプロジェクトが成立しないといった点に注意が必要です。
ベンチャーキャピタル
ベンチャーキャピタルとは、ベンチャー企業やスタートアップ企業に出資をする投資会社・ファンドを意味します。企業の将来性を判断して出資をするため、金融機関から融資を受けられない場合でも、資金調達ができる可能性があります。ベンチャーキャピタルからの出資金は借入金ではなく、返済する必要がないのもメリットです。
ただし、出資に見合う利益を出すことが望まれるため、成果が出せない場合は投資から撤退される可能性があります。また、出資を受ける代わりに自社株を譲渡するのが一般的であり、譲渡する議決権株式の数によっては、経営に介入されるおそれもあります。