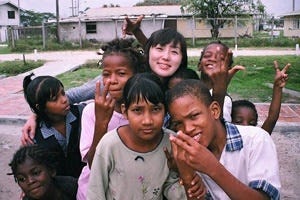これまでの中で、それぞれに特に印象に残った取材を聞くと、佐々木アナが挙げるのはHIV/エイズで両親を亡くし、2人の妹たちを育てるマラウイの16歳の少女。
「当時30代前半で、自分のことばかり考えていた私は、その少女に“学校にも行けず、妹たちの世話をしなければならないことについて、どう考えていますか?”と聞いたんです。すると、“私は生きられている。この子たちを育てるのが私の仕事なんです”と答えてくれて、この年にして誰かのために生きることを選ばざるを得ない人がいる、でもそれを幸せだと語ってくれるということに本当に頭が下がる思いで、もっと支援があればと強く思わされました」
また、HIVに感染して孤絶されたパプアニューギニアの少年の姿も忘れられない。
「ご飯を食べさせてもらえず、会話もしてもらえず、屋根も壁もない吹きさらしの掘っ立て小屋で毛布をかけられているだけで、もう死を待つだけの状態だったんです。両親は亡くなっているのですが、お姉ちゃんは元気なので、親戚の家で大事に育てられ、学校に行っている。その時に、“命は平等”なんて言葉はウソだと思ってしまいました。彼らにとって将来稼ぎ手になってくれる未来はそっちにしかないわけなので、過度な貧困の状況では、とても責められないんです」
この経験は、その後のアナウンサー人生に大きく影響した。
「どんな環境でも生きようとしている人たちを見てきて、“自分には何もできない”と思わないようになったと思います。1歳6カ月の赤ちゃんに自分の母乳を通してHIVをうつしてしまったお母さんが、そのお子さんを亡くすという瞬間を見て、自分の無力感を感じたんです。でも、ユニセフのスタッフの方に言われたのは、“佐々木さんが自分は無力だと思わないでほしい。この事実を伝えてくれる人がいないと、この出来事はないことと同じになってしまう。ここで見たことをぜひ伝えてください”ということ。ここから、伝えること、人の話を聞くという行為とは何なのかを突き詰めて考えるようになり、アナウンサーとしての自分の基礎になったと思います」
地震大国の日本だからこそできる支援
昨年は国土の3分の1が水没する被害を受けたパキスタンを、今年は大地震の被害があったネパールを取材した倉田アナは、「支援」という概念が大きく変わったと話す。
「パキスタンは非常に宗教色の強い国で、災害が起きてもすべて“神のおぼし召し”ということで片付けるんです。なので、またモンスーンが来て洪水が起こるかもしれないけど、彼らは同じところに住み続けるし、同じ材料でまた家を作る。それは今年行ったネパールも同じ考えでした。そこで私は“地震の勉強はしていますか?”と、いろいろなところで質問したのですが、どこに行っても“したことはないです”と返ってくる。“防災の術があるなら知りたいですか?”と尋ねると、みんな“知りたい”と言うんです。それを聞いて、支援の形として当然お金は最低限必要なのですが、地震大国の日本にできることとして、もしかしたらその“術”を伝えるということも、お金と並ぶくらい大きな支援なのではないかと思いました」
「最初は正直な気持ち、衛生環境などを見て、現地の人たちを憐(あわれ)むような気持ちがあったんです」と打ち明ける倉田アナ。「でも、我々は現地の水や生の食べ物でお腹を壊してしまうけど、免疫の違う彼らにとっては当たり前のものなんですよね。そうしたことに気づいた時、我々が自信を持ってできる支援として、“防災の術”があると思ったんです」と感じるようになったという。