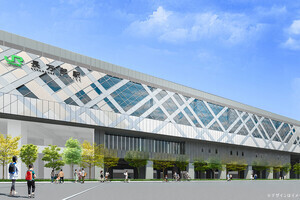北海道新幹線の新函館北斗~札幌間について、建設主体の鉄道・運輸機構は5月8日、「2030年度末の開業は極めて困難」と判断し、国土交通大臣に報告した。4月末から北海道新聞、朝日新聞、NHKなどが「関係者」の情報として報じ、5月8日にJR北海道もコメントを発表。「営業主体の立場から必要な協力を行ってまいります」とした。
2030年度末の開業を断念したおもな理由は、ニセコ~倶知安間の羊蹄トンネルで巨大な岩に突き当たったためとされる。ただし、建設費の高騰や2024年問題など、他にも原因がありそうに思える。
北海道新聞電子版の4月27日付記事「道新幹線札幌延伸 30年度断念 正式発表 来月8日軸」によると、鉄道・運輸機構と国土交通省はこの時点ですでに調整に入っており、当初は4月下旬に正式発表する予定だったという。しかし、札幌市の秋元克広市長は「納得できない」、北海道の鈴木直道知事も「説明を受けていないので承知していない」と会見で表明。鉄道・運輸機構と国土交通省は「丁寧な説明」を準備するため、延期したようだ。
-
新函館北斗~札幌間のトンネルと明かり区間
(出典 : JRTT鉄道・運輸機構ウェブサイト https://www.jrtt.go.jp/project/asset/pdf/hokkaido/240401_jrttproject_hokkaido_progress_table.pdf)
説明が丁寧であっても雑であっても、工事が間に合わないことに変わりはない。この場合の「丁寧な説明」とは、「先行して整備した駅周辺などの費用補償」や工期延長によって増加した事業費の負担割合についてだと思われる。小樽市の迫俊哉市長は、4月26日の定例会見で、新小樽駅周辺に整備する予定だった駐車場の着工を遅らせると語った。じつは、小樽市は民間調査団体の「消滅可能性自治体」リストに入ってしまっている。小樽市としては、先延ばしにされそうな新幹線関連整備より、市民の生活のために予算を使いたいはずだ。
NHKの5月10日のニュースによると、国土交通省側は有識者会議を開催。工期などを検証した上で、開業時期の延期を判断するための議論を始めた。まずは工法の変更等で工期を短縮できるか検討し、工期延長は避けられないと判断できたところで、新たな開業時期を示すという手順になる。
新函館北斗~札幌間の用地取得率94%、土木工事着手率99%に
鉄道・運輸機構は北海道新幹線延伸区間の進捗を公開している。4月1日現在、用地取得率94%、土木工事着手率99%となっている。用地が94%なのに土木工事が99%となった理由は、土木工事がおもに線路を敷くための路盤作りで、用地は線路に加えて駅や保線施設なども含むからだろう。もし土木工事未着手の1%の中に未取得用地があると厄介になる。
-
新函館北斗~札幌間の進捗
(出典 : JRTT鉄道・運輸機構ウェブサイト https://www.jrtt.go.jp/project/hokkaido.html)
工事進捗の詳しい状況も鉄道・運輸機構のサイトに公開されていた。トンネル工事は50工区のうち15工区で本坑掘削完了、25工区が掘削中。羊蹄トンネルは有島工区と比羅夫工区に分かれており、両側から掘削している。有島工区側は掘削率56%、巨大な岩が見つかった比羅夫工区側は掘削率64%、全体で60%となる。残ったトンネル群の中でも低い進捗率である。
進捗率だけ見れば、新小樽(仮称)~札幌間の札樽トンネルは約24.8%とかなり低い。6工区に分かれており、全体で約26.2kmのうち6.5kmとなっている。ただし、すべて同じタイミングからスタートしているわけではない。あるトンネルが終わったら、そのチームが次のトンネルに着手という事例もあるはず。予定した時期に100%になっていればいい。
鉄橋や盛土など、トンネル以外の部分は「明かり区間」という。こちらは20工区のうち11工区が橋脚基礎工事中、5工区が高架橋工事に進んでいる。完工区間はないものの、明かり区間はトンネル内のような未知の要素が少ないので、予定通りかもしれない。一方、準備中とされた4工区は気になる。こちらも用地取得率が関係していそうだ。
10m続く巨岩を粉砕せよ、2024年問題に対応せよ
新函館北斗~札幌間の工事延長約211.9kmのうち、トンネルは約168.9kmで8割を占める。全体の掘削率は74%で、もうひと息という数字に見えるが、さかのぼって3月1日のデータは73%、2月1日のデータは72%だった。1カ月に1%の進捗で、このペースだと100%になるまで、つまりトンネル全通まであと36カ月、つまり3年かかる。3年後は2027年だから、2030年度末に間に合いそうではないか。ところがそう簡単にはいかない。理由は2つ。羊蹄トンネルの巨大な岩の処理と、2024年問題によって工事のスピードが遅くなるからだ。
-
新函館北斗~札幌間のトンネル掘削状況。2022年8月発表
(出典 : JRTT鉄道・運輸機構ウェブサイト https://www.jrtt.go.jp/project/asset/pdf/hokkaido/240401_jrttproject_hokkaido_progress_table.pdf)
鉄道・運輸機構が2022年2月8日に発表した資料によると、羊蹄トンネルの巨岩は2021年7月に見つかった。札幌側から掘り進めたシールドマシンが約3.5km地点で岩盤に当たり、掘り進めなくなった。トンネル内部からの調査で、進路方向に10mを超える巨岩があったようだ。岩の範囲を測定するため、地上からの追加調査を実施し、2022年1月に岩の除去に向けた対策工法を決定した。トンネル先端部の手前から分岐するように作業用トンネルを掘って迂回し、巨岩の横に取り付いて、岩盤を砕いて取り除くという。
おそらく山岳工法のように巨岩にドリルで穴を開け、そこにダイナマイトを詰め込んで爆破する方法になるだろう。爆破して巨岩のかけらを運び出し、また爆破して運び出しの繰返し。巨岩は周囲の支えになっていたかもしれず、取り除けば支えを失った土や岩が降りてくるかもしれない。地下水をせき止めているかもしれない。巨岩を取り除くだけでは済まないような気がする。
-
羊蹄トンネルの巨岩と対策
(出典 : JRTT鉄道・運輸機構ウェブサイト https://www.jrtt.go.jp/corporate/public_relations/pdf/20220208_youtei-press.pdf)
もうひとつの開業遅延要素は2024年問題。トラックやバスのドライバー不足等で話題となった2024年問題は、「時間外労働の上限規制」が影響している。この規制は労働基準法など8つの労働法を改正する「働き方改革関連法」によって施行される。すでに大企業で2019年4月から、中小企業でも2020年から定められており、労使が合意しても労働時間は年間720時間まで、月100時間まで、複数月にまたがる場合は月平均80時間となっていた。ただし、建設業界、道路運送業界、医師、鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業は猶予期間が与えられていた。その期限が2024年3月までだった。
つまり、2024年問題はすべての企業の問題だった。トラックやバスのドライバーは人材不足の影響で対応が遅れ、2024年4月に間に合わず、荷物の遅れやバスの減便として現れている。そして土木建設業界も同様に人材不足である。いままでと同じ労働者数の場合、残業を減らせば作業量が減るため、工期が延びる。工期を守ろうとすれば労働者を増やすしかない。しかし労働者の数はむしろ足りない。
「不測の事態」のゆとり時間が削られた
北海道新幹線の新函館北斗~札幌間は、2011年12月26日に「整備新幹線の取扱いについて(政府・与党確認事項)」で想定開業時期を「新青森・新函館間の開業から概ね20年後」とされた。新青森~新函館北斗間の開業は2016年3月(2015年度末)だったから、自動的に札幌延伸開業も2035年度末となった。さらに2014年9月24日、政府与党PTにより開業時期短縮の検討が始まり、2015年1月14日に政府与党の合意で5年前倒しされ、2030年度末開業とされた。
開業の短縮は、北陸新幹線金沢~敦賀間、西九州新幹線武雄温泉~長崎間と合わせて検討され、事業費の財源として5,400億円が必要と算定された。その内訳は、「新規着工3区間の貸付料を前倒し」「並行在来線の線路使用料として留保する貨物調整金の見直し」が合わせて約4,560億円、「公費負担」が国と自治体合わせて約840億円だった。
簡単に言うと、北海道新幹線の場合、2030年度末から2035年度末までの建設費負担がなくなるから、その分を現在の財源に繰り上げよう、という話である。
しかし、鉄道・運輸機構としても、「お金を積んだから工期を短縮してね」と言われたところで、そう簡単に工期を短縮できない。人手不足は深刻で、コロナ禍や海外の紛争も影響し、資材が高騰している。お金を積まれても、できないものはできないし、不慮の事態に備えて建設期間にゆとりを持たせたい。それでも国が「やりなさい」と言って、「できません」と返したら会議は終わらない。「やります」と言うまで終わらない会議に出席させられる。
筆者も過去に似たような経験がある。延々と続く会議を終わらせるために、「やります」と言うしかない。それでも結局、状況が変わらず、「できませんでした」となったら、「ごめんなさい」と言うしかない。なぜなら「やりますって言ったでしょ」となるからだ。そう考えると、なんだか鉄道・運輸機構が気の毒になってきた。もっとも、鉄道・運輸機構もゼネコンに対して同じことをするのだろう。
北陸新幹線ではフリーゲージトレインの見直しに伴う敦賀駅の構造変更、トンネル内で盤ぶくれ現象という想定以外の事象が起きた。北海道新幹線では巨岩が出た。もう切り詰めた工期では対応できない。北陸新幹線は2025年度末から2022年度末に短縮しておきながら、実際には工期が2年遅れて2023年度末開業となり、1年しか短縮できなかった。
北海道新幹線も北陸新幹線と同じ道をたどりそうだ。2035年度末から2030年度に前倒ししたが、巨岩のせいで、「働き方改革関連法」が成立したせいで、実際には工期を延長する事態となった。羊蹄トンネルの工期は4年遅れともいわれており、結局、当初の予定通り2035年度末開業になるかもしれない。
オリ・パラ招致活動停止も背景に、一方で並行在来線の協議は
北海道新幹線の開業延期は半年前から検討されていた。2023年10月15日付の本誌記事「札幌五輪断念、北海道新幹線の札幌延伸も延期? 工事に4年分の遅れ」で紹介したように、2023年10月7日に共同通信が政府筋の情報としてスクープしている。昨今の報道はこのスクープが正しかったという証でもある。
当時の理由は羊蹄トンネルの遅延と、札幌市の2030年冬季オリ・パラ、2034年冬季オリ・パラ招致活動停止で、急ぐ必要がなくなったからとされていた。2023年12月19日、JOC(日本オリンピック委員会)から札幌招致関係者会議に招致活動停止の提案があり、招致活動停止を決定した。札幌市長が記者団に「撤退や白紙ではなく停止とする」と説明した。
並行在来線となる函館本線新函館北斗~長万部間のバス転換について、北海道庁は具体的なルート策定のために函館バスと協議する方針となった。貨物専用線化についても国や北海道庁が有識者会議を発足させている。しかし受け皿となる会社をどうするかなど、結論は出ていない。
新函館北斗駅から函館駅まで新幹線車両を直通する計画について、函館市長は並行在来線問題とセットで検討するという姿勢を見せている。並行在来線については、北海道新幹線の開業延期で検討の深度化が可能となった。
北海道新幹線の開業に合わせたまちづくりは予定の見直し、延期が必要に。地元企業も開業に向けた取組みの変更を強いられる。旅行者や沿線で生活する人にとっても、新幹線開業をひとつの節目としていたかもしれない。開業延期は残念だが、延期するからにはもっとも良い形で開業してほしい。