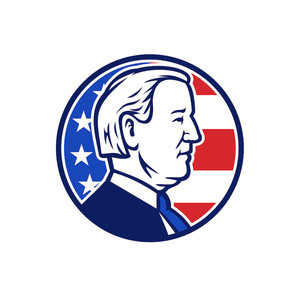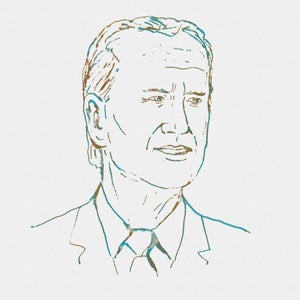マネ―スクエアのチーフエコノミスト西田明弘氏が、投資についてお話しします。今回は、米国の金融政策について解説していただきます。
米国のバイデン大統領は3月9日、今年10月に始まる2024年度の予算教書を公表しました。社会福祉などの支出を増やす一方で、法人や富裕層に対する増税を盛り込む野心的な内容でした。もっとも、共和党が下院の過半数を占める議会で、予算教書に沿った予算編成が行われる可能性はほぼゼロでしょう。
予算教書の公表を受けて、政府と議会、民主党と共和党の予算交渉がスタートします。果たして、どんなドラマが待っているか。そうしたなか、金融市場はデットシーリング(債務上限 ※後述)の行方に注目しています。共和党がデットシーリングを交渉材料に使うことでデフォルト(債務不履行)の可能性が高まるからです。
日本にデットシーリングは必要か
デットシーリングは政府債務の抑制を目的としたルールです。日本の国債発行残高は22年末時点で1,116兆円。これに対して米国は同じく31兆ドル。円換算で約4,000兆円なので、実は米国の方が大きいのです。ただし、経済規模と比べるため、GDP比(国内総生産)は日本が約200%、米国が123%です。そのため、日本こそデットシーリング(政府債務の法定上限)が必要なように思えます。
もっとも、デットシーリングは、必ずしも政府債務の抑制に有効とは言えません。政府債務は、歳出と歳入の差である財政赤字、それが積み重なった「結果」に過ぎないからです。歳出や歳入に直接的に手を加えず、その結果としてすでに存在している債務の履行を禁止するだけだからです。
もちろん、デフォルト(債務不履行)を回避するために政府債務を減らそうとするインセンティブにはなりますが、政府債務削減のメカニズムはデットシーリングには含まれていません。
また、過去に頻繁にみられたように、政府や議会には政府債務を減らすよりもデットシーリングの引き上げで対応する選択肢を選びがちです。
債券自警団
デットシーリングよりも政府債務の削減に有効な「仕掛け」があります。それは債券市場です。財政赤字が拡大すれば(=国債発行額が増加すれば)、国債需給の悪化から国債価格が下落し(市場金利が上昇し)、国債発行コストが増加するだけでなく、経済にとって様々な悪影響が出ます。政府や議会はそうした事態を回避しようとするでしょう。
そして、財政赤字が実際に拡大しなくても、そうなるような動きが出るだけで、国債が売られて警告が発せられるのです。そうした債券市場のメカニズムを、著名なエコノミストはかつて「債券自警団」と名付けました。
最近でも、「債券自警団」が活躍する場面がありました。昨年の英国のケースです。ジョンソン首相の後を継いだトラス首相(当時)が財源の裏付けがない大型減税を提案した途端に、英国の市場金利が急騰して強烈な警告を発したのです(英国株も英ポンドも売られてトリプル安になりした)。結局、それが原因でトラス首相は在任期間わずか49日で辞任しました。
日本のケースでは……?
日本では市場金利が比較的安定しており、「債券自警団」が登場する気配はありません。これにはいくつかの理由が考えられますが、最大の理由は日銀が国債を大量に買っているからでしょう。「債券自警団」が動き出そうとすると、日銀が国債購入額を増やして市場金利の上昇を抑え込んできた経緯もあります。いうまでもなく、YCC(イールドカーブ・コントロール=長短金利操作)のためです。
日本で「債券自警団」に活躍してもらうためには、YCCを制限・撤廃する、もっと言えば国債を購入する日銀の量的緩和そのものに制約を加える必要があるのかもしれません。「植田総裁」の下でYCCを含めた日銀の金融緩和がどう変化するか、大いに注目です。
◆デットシーリング
米連邦政府の法定「債務上限」のこと。政府はデットシーリングを超えて債務を増やすことができない。債務が上限に達すると、都度、議会が上限を引き上げてきたが、予算交渉などに関連して引上げが難航すると、デフォルト(債務不履行)の懸念が高まる。とりわけ、国債の利払いや社会保障は自然発生するので、これが履行できない可能性が意識される。米政府は債務が上限に達すると、一時的に政府基金等から資金を流用する奥の手を使って時間稼ぎをするが、それにも限界がある。米政府はこれまで一度もデフォルトしたことはないが、2011年は8月の限界ギリギリまでデットリーリングの引き上げが遅れて金融市場が大きく動揺した(米ドル安、株安、金利低下)。