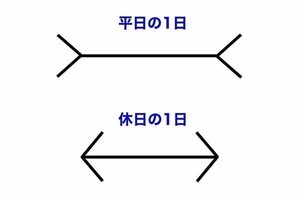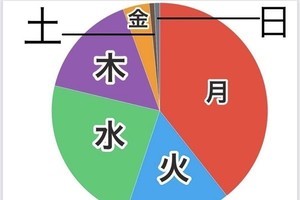うどんの出汁の色からエレベータの乗り方まで、言葉のイントネーションの違いからバス代金の支払いタイミングまで、日本東西南北で文化、風習などさまざま。では、地名における「谷」と「沢」が大きく分かれているの、知っていました?
末尾が「谷」と「沢」の地名を地図化すると、きれいな東西差がありました。
そもそも「谷」と「沢」も意味は、山や丘に挟まれた細長く溝状に伸びた地形のことで、ほぼ同じ意味。では、何が違うのでしょうか。「沢」は縄文時代以来の言葉で「谷」は弥生時代に大陸から持ち込まれた言葉と言われています。諸説ありますが、この歴史的&地理的な要因から、東日本には「沢」のつく地名が多く、西日本には「谷」がつく地名が多いとの説も…。
本当の理由は深く歴史や文献を調べないとわかりませんが、地理Bの旅さんが作成した日本地図を見ると何らかの地域傾向があることだけは歴然としています。改めて地図で見える化すると説得力がありますよね。でも微妙に入り混じっているところもあれば、「谷」をタニと呼ぶ地域や、ヤと呼ぶ地域も。地理Bの旅さんのスレッドでも大いに盛り上がりました。
「これは興味深いですね」「関東では、や 関西では、たに」「面白い! 佐渡は綺麗に半分こ」「福島市の地名が沢と谷が両立していて興味深い」「平地しかなくて真っ白な十勝地方」「これも、関ヶ原を境にして別れているんですね」「谷沢さんは最強」など。投稿者の地理Bの旅さんにお話を伺いました。
■投稿者さんに聞く
……この分布図を作ろうと思ったきっかけは?
地名の地域差に関心があり、これまでもいくつかの地図を作成して投稿してきました。沢と谷の東西差については地理学のいくつかの書籍でも紹介されていたので、自分でも確かめてみようと思い作成した次第です。
……改めてこの分布図を作って気づいたこと、思ったことは?
沢と谷は明瞭な地域差があって分かりやすいと感じました。これまでも地名の分布図は作成して投稿してきましたが、たくさんの方にとって身近な地名を取り上げたことで、大きな反響があり嬉しかったです。地図化に用いた「歴史地名データ」や「地理院地図」は誰でも使えるものなので、関心を持った方は自分でも試してみてほしいです。また、地名の地域差の理由には諸説ありますが、分布図の読み取りだけでは地域差の理由は説明できません。古地図や歴史的資料なども確認して、地域差の理由を調べる作業も今後行ってみたいと思いました。
……気になるリプライなどありましたか。
東西差といっても関東は末尾に谷の付く地名が多く、その理由についてたくさんの方が考えてくださり、楽しく読ませていただきました。渋谷のように「~谷」を「~や」と読んだり、「~谷」を「~やつ」と読む地名もあります。東日本には「谷地」・「谷戸」など別の類型の地名が混在しているので、それらについてもさらに詳しく調べてみたいです。
……今後作ってみたい地図は?
日本全体で分かりやすい地域差のある地名の分布図に加え、一部の地域だけに見られる地名なども地図化したいと思います。地名という身近な事例をきっかけに、たくさんの方が地図や地理に関心を持ってくださるとありがたいです。
▼末尾が「谷」と「沢」の地名を地図化すると、きれいな東西差がありました。
末尾が「谷」と「沢」の地名を地図化すると、きれいな東西差がありました。 pic.twitter.com/avXjnDcFtJ
— 地理Bの旅 (@chiribgeo) January 27, 2023