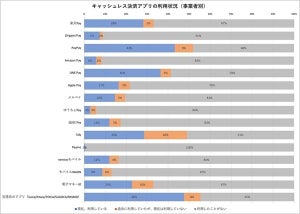子育てや介護などの事情により、時間を短縮して働き続けられる制度を「短時間勤務制度」(時短勤務)と言います。今回は、時短勤務の利用期間やフルタイム勤務に戻したあとの働き方についてチェックしていきましょう。
時短勤務はいつまで利用できる?
育児のための時短勤務
「育児・介護休業法」では、育児や介護のために、従業員が時短勤務(短時間勤務)をすることができるように、社内制度を整えることが義務付けられています。
このうち、育児を理由とした時短勤務(短時間勤務)の利用対象者は、「3歳未満の子を養育する従業員」と規定されています。
よって、育児・介護休業法の規定に基づいた時短勤務(短時間勤務)は、子どもが3歳になる誕生日の前日まで利用できるということになります。
加えて、時短勤務(短時間勤務)を利用するためには、以下の条件に該当する必要があります。
・短時間勤務をする期間に育児休業を取得していないこと
・日々雇用される労働者でないこと
・1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
・労使協定により適用除外とされた従業員でないこと
介護のための時短勤務
一方、介護のための時短勤務は、要介護状態にある家族を介護する場合、連続する3年以上の期間、利用することができます。日々雇用される労働者以外のすべての男女労働者が対象です(ただし、勤続1年未満の労働者と、週の所定労働日数が2日以下の労働者については、対象となりません)。
また、毎日の労働時間を短縮する以外に、フレックスタイムの制度や、時差出勤の制度などを設けている会社もあります。現在、会社に勤務している方で、時短勤務を検討している方は、他にどのような選択肢があるのか確認してみると良いでしょう。
育児のための時短勤務、実際の取得可能期間は?
育児のための時短勤務は、先ほどご紹介したように、「子どもが3歳になるまで」と法律で定められています。つまり、子どもが3歳の誕生日を迎えたら、フルタイムに戻るというのが一般的なルールです。
結果として、厚生労働省が行った「平成29年度雇用機会均等基本調査」によれば、「短時間勤務制度がある」と回答している事業所の最長利用可能期間は、「3歳未満」(57.0%)が最も多くなっています。
ただし会社によっては、子どもがさらに大きくなるまで、時短勤務を認めているケースもあります。
「小学校就学の始期に達するまで」が 18.9%、「小学校就学の始期に達するまで及び小学校入学以降も対象」としている事業所割合は 39.0%。子どもが3歳を超えても短時間勤務制度が利用できる会社が多くなってきているのです。
時短勤務を延長したいと考えている方は、1人で悩まずに、まず会社に相談してみましょう。
フルタイム勤務に戻すタイミングは?
フルタイム勤務に戻すタイミングをどのように判断したか、そのきっかけについて、時短勤務を経験したマイナビニュース会員(116名)を対象にしたアンケート調査では、以下のような回答が寄せられました。
子どもが3歳未満(時短勤務を終えた時期、以下同)
「保育園の預かり時間が延長された」(43歳/その他・専業主婦等)
「親と同居が始まった」(48歳/コンピューター機器)
「会社の決まりだから」(31歳/その他メーカー)
「もっと稼ぎたくなったから」(29歳/その他)
子どもが小学校入学前
「学童に入ったから」(43歳/医療・福祉・介護サービス)
「小学生になってある程度子どもと言えどもできることが増えて、安心できたから」(39歳/サービス)
「子どもに手がかからなくなってきたので」(34歳/その他)
「いい加減フルタイムに戻らないと自分の席がなくなりそうだったから」(44歳/医療・福祉・介護サービス)
子どもが小学3年生まで
「学童保育が充実していたから」(46歳/その他)
「一人で家にいられるようになったから」(45歳/その他)
「兄弟で留守番できるようになったから」(36歳/その他)
「会社の規定マックスまで使いました」(46歳/ガラス・化学・石油)
子どもが小学6年生まで
「子どもが留守番できたり友達と遊びに行くことが多くなったから」(50歳/ドラッグストア)
「子どもに手がかからなくなったから」(44歳/電力・ガス・エネルギー)
「留守番ができるようになったため」(44歳/フードビジネス)
「会社の規定マックスまで使いました」(46歳/ガラス・化学・石油)
上記の回答も踏まえてフルタイム勤務に戻すタイミングの判断基準を考えてみます。
まず、子どもの成長に注目してみましょう。たとえば子どもが少し成長し、食事や着替えなど、ある程度自分でできるようになってきたら、フルタイム勤務への復帰のサインです。時短勤務中に、お子さんが保育園での生活に慣れ、お母さんの仕事を応援してくれるようになったら、大変心強いですね。
また、フルタイム復帰の判断基準の2つ目として、夫など家族との協力体制や、効率的に家事が行える環境が整っているかどうかを確認しましょう。時短勤務中に、夫との役割分担を決めて、家事や子育ての力の抜きどころを確認します。そして、必要に応じて、家事代行サービスや、食洗機やお掃除ロボットなどの最新家電の導入も行い、家事環境を整えることが大切です。
最後に、フルタイム復帰へポイントとして、お母さん自身が、仕事と家事や子育ての両立に、自分なりのペースがつかめるようになってきているかどうかを見極めましょう。フルタイムに復帰するベストなタイミングは、人によって異なりますが、お母さんなりに「仕事と子育ての両立に、少し自信が持てた時」がチャンスです。家族みんなで、時短勤務中にシミュレーションを行い、フルタイムのワーキングマザーになることに対して、少しずつ心の準備を進めていきましょう。
時短勤務からフルタイム勤務へ戻すと、毎日の生活が多忙で、大変になるのでは? と不安に感じている方もいるかもしれません。もちろん、時間的な余裕はなくなるかもしれませんが、フルタイム勤務に戻すことで、時短勤務にはないメリットもあります。
たとえば時短勤務の場合、フルタイム勤務に比べると、毎月のお給料やボーナスが少なくなってしまうのが一般的です。また、時短勤務をしている期間は、残念ながら大きなプロジェクトを任されたり、昇格したりというチャンスが減ってしまう方も多いのではないでしょうか。
そして、時短勤務中は、他の社員の方に仕事をお願いしなければならず、少し肩身が狭い思いをすることもあるかもしれません。フルタイム勤務に戻すことで、より自分の力を十分に発揮して、やりがいを持って仕事に取り組むことができるでしょう。
いかがだったでしょうか。子育てや介護をしながら働き続けるというのは、大変なことです。条件さえ満たせば利用することができる「短時間勤務制度」は、育児や介護と、仕事との両立に悩む方の強い味方ですね。
もちろん、時短勤務をサポートしてくれる上司や、仕事をカバーしてくれる会社のチームの方などに、常に感謝することも大切ですが、現在、育児や介護などのために、仕事を辞めようか迷っている方は、「短時間勤務制度」を利用しながら、働き続けるという選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。
下中英恵

|
女性のためのお金の総合クリニック「エフピーウーマン」認定ライター ファイナンシャルプランナー(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)。第一種証券外務員、内部管理責任者。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は東京において、資産運用や税制等多様なテーマについて、金融記事の執筆活動を行っている。