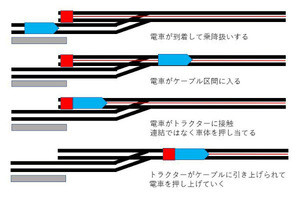復活した山岳鉄道「シャルガン8」
今回の旅で筆者が最も楽しみにしていたのが、セルビア南西部の街ウジツェからさらに西へ約30km、自然保護公園の町モクラ・ゴラから発着する山岳観光鉄道「シャルガンスカ・オスミツァ(シャルガン8)」の列車に乗ることだった。セルビア語で数字の8を「オッサム」といい、シャルガン山の急斜面を登るために敷設された線路のループが、上から見ると8の字に見えるためにその名が付いたそうだ。
緑色のディーゼル機関車に牽引されたさまざまな規格の混成客車の1両に乗り込むと、22のトンネルと5つの橋を通過し、およそ40分かけて終点のシャルガン・ヴィタシ駅に到着する。路線の総延長は15.44km。モクラ・ゴラ駅の標高は567m、シャルガン・ヴィタシ駅の標高は808mだから、ループを描きながら241mの高低差を駆け上ったことになる。帰りは景色の良い途中駅に停車し、休憩しながら同じ線路をモクラ・ゴラ駅まで引き返す。
この鉄道はもともと観光用に建設されたものではない。かつてベオグラードからサラエヴォを経由し、アドリア海沿岸の都市ドゥブロヴニクまで24時間で結ぶ旧ユーゴスラビアの狭軌鉄道の一部だった。この鉄道は1974年に廃止されたが、1999年に鉄道会社「ZTPベオグラード」が観光鉄道として再建することを決め、復活を遂げたのが現在の「シャルガン8」なのである。
さて、車内で配布されるパンフレットに「ユニークな建築上の傑作である世界有数の狭軌鉄道」(原文は英語)と紹介されている「シャルガン8」は、もちろん満足度の高い観光列車なのだが、いかんせんウジツェからモクラ・ゴラまでのアクセスが良くない。バスもあるが本数が少ないため、今回は行きも帰りもタクシーを利用した。帰りはモクラ・ゴラのホテルでウジツェからタクシーを呼んでもらったが、思いのほか時間がかかった。
| 「シャルガンスカ・オスミツァ(シャルガン8)」インフォメーション(2018年9月訪問時) | |
|---|---|
| 乗車時間 | 約2時間 |
| 出発時刻 | 10:30発、13:30発の2本 |
| 料金など | 800ディナール(1ディナール=約1円)。時期によっては600ディナール。事前の乗車予約可能 |
新駅なのにまるで廃墟!? ベオグラード中央駅
最後は都市の顔ともいえる鉄道のメインステーションに関する話題。今年7月1日、ベオグラード駅(ベオグラード本駅)が134年の歴史に幕を閉じ、今後はすべての国内・国際列車の発着が1.4kmほど南のベオグラード中央駅(2016年開業)に移されたというニュースが報じられた。そこで、ベオグラード中央駅の様子を見るため訪れてみた。
歴史的な趣きのあるベオグラード本駅と比べ、新駅はまだ整備中といった雰囲気で、駅前にはなにもない。また、駅構内の別のホームに移る場合、屋外の金網に挟まれた連絡通路を歩くことになる。いずれきちんとした駅舎が出来上がるのだろうが、いまのところ、新駅にもかかわらず、まるで廃墟のように見えた。
筆者は新駅からローカル線のディーゼルカーに乗り、ルーマニア国境に近いヴォイヴォディナ自治州のブルシャツという街まで出かけてみた。とくに目的があったわけではなく、日帰りにちょうどいい距離だったのだ。
ドナウ川を渡ると、車窓に見えるのは地平線の彼方まで広がるトウモロコシ畑。とくに面白い景色というわけでもないのだが、久しぶりにゆったりと列車旅を楽しめた。もっとも、セルビア国内の都市間の移動は、長距離バスのほうが圧倒的に便利だった。
セルビア旅行で注意すべきことは?
さて、ベオグラードへの直行便が就航していないこともあり、セルビアは日本人にとってまだまだなじみの薄い国かもしれない。セルビア統計局の2016年のデータによれば、同年に日本を訪れたセルビア人の数は2,486人、セルビアを訪れた日本人は5,245人とのことで、非常に少ないと言わざるをえない。
しかし、ドナウ川クルーズ、ベオグラード要塞、セルビア正教会の教会建築、セルビアワインをはじめとする食文化、さらに青木さんに誘われ訪れた南部の街レスコバツの毎年恒例のBBQ祭りも見学でき、現地のさまざまな観光資源を楽しむことができた。「1ディナール=約1円」と、世界で最も円換算が容易な通貨というのも、日本人にはありがたい。
言葉の問題に関して、ベオグラードでは人によってレベルはまちまちだが、若い世代を中心に英語を話せる人が多い。ホテルではほぼ100%通じるが、キオスクやタクシードライバーは英語を話せない人も多い。地方に行っても、各店に大体1人は英語を話せる人がいる印象だった。
なお、これはセルビアに限った話ではないが、悪質な「ぼったくりタクシー」には要注意。じつは筆者も、ドナウ川クルーズの帰りに「ぼったくりタクシー」にひっかかってしまった。ベオグラードに長年住む通訳の大塚真彦さんによれば、悪質タクシーに引っかからないようにするには「タクシースタンド(タクシー溜まり)のタクシーを避け、流しをつかまえるようにすること。最近はホテルと悪質タクシーが結託している悪質なホテルはなくなったと思うので、ホテルでタクシーを呼んでもらってもいい」とのこと。海外では何が起きるかわからないだけに、気をつけたいところだ。
筆者プロフィール: 森川 孝郎(もりかわ たかお)
慶應義塾大学卒。IT企業に勤務し、政府系システムの開発等に携わった後、コラムニストに転身し、メディアへ旅行・観光、地域経済の動向などに関する記事を寄稿している。現在、大磯町観光協会理事、鎌倉ペンクラブ会員、温泉ソムリエ、オールアバウト公式国内旅行ガイド。テレビ、ラジオにも多数出演。鎌倉の観光情報は、自身で運営する「鎌倉紀行」で更新。