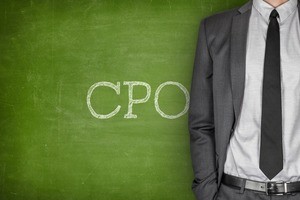最高経営責任者を意味する「CEO」をはじめ、ビジネスの世界には「CxO」という役職が多数存在します。それぞれに重要な役割を担っていますが、今回は、あまり聞き馴染のない「CKO」についてご紹介します。
■CKOの意味
「CKO」とはアメリカの組織で使われる役職名で、「chief Knowledge officer」の略語です。企業内における知識やノウハウ、情報などを管理する責任を担う「最高知識責任者」のことを指します。
■CIOとの違い
CKO・CIOともに、「情報」に関係した役割を担っていますが、「CIO」(Chief Information Officerの略語)は、情報システム関連業務の責任を負う「最高情報責任者」で、経営戦略に沿ったIT戦略を立案・実行します。一方CKOは、個人が持つ知識や情報を組織全体で共有し、企業価値向上に活かしていく「ナレッジ・マネジメント」の戦略を立てる役割を担っています。
■CKOの役割
「CKO」の役割は、個人が持つ知識やノウハウ、情報といったものを組織全体で共有し、企業価値の向上に活かしていく、いわゆる「ナレッジ・マネジメント」の戦略を立てることが主になります。戦略を立てるにあたっては、上層部が決定した経営方針や目標を理解する必要があります。今、組織にとって何が重要なのか、必要とする知識は何なのかを確認した上で、従業員への知識の想像と普及、意識改革を促していきます。
ひとつの部門の中に留まりがちなスキルやノウハウを集約し、マニュアル化するなどして、全従業員で共有できるようにします。また、同じ作業の繰り返しによってマンネリ化しがちな現場を活性化し、新たな発想が生まれるような改革意識を促す役割も担っています。そのほか、特許権や著作権といった資産を把握し、活用するのもCKOの役割です。
■知識とその共有方法
一言に「知識」と言っても、業種などによってさまざまあり、それぞれの知識に合った方法で共有する必要があります。
例えば、長年の勘や経験によって身に付いた熟練工の技のような知識は、当然のことながら、実際に作業を見たり、直接教えてもらったりすることで、その部門の中で引き継がれていくものです。しかしながら、このままではこの価値ある知識はその部門の中でしか活用されません。
また、時に組織というものは、それが自社のためであっても、自分たちの優れた知識を他部門や他支店に放出することを嫌う傾向があり、それが知識の共有の妨げになることもあるのです。CKOは、そういった従業員の意識改革を行うと同時に、この"技"を極力マニュアル化・数値化するなどして、会社全体の知識となるようマネジメントします。
また、カスタマーセンターなどが得た情報も「知識」のひとつです。顧客から寄せられた意見や苦情をデータベース化し、全社員で即座に共有し伝達できるようにすることで、顧客の声を営業や開発に活かし、顧客満足度の向上に繋げていきます。
今回はCKOについて説明しましたが、ここに挙げた役割が全てではありません。CIOやCFOなどに比べてあまり浸透していない役職ですが、ITやAIの発達などにより企業を取り巻く環境が目まぐるしく変化していく今、スピーディにナレッジ・マネジメントを実行するCKOの重要性が、改めて注目されているようです。