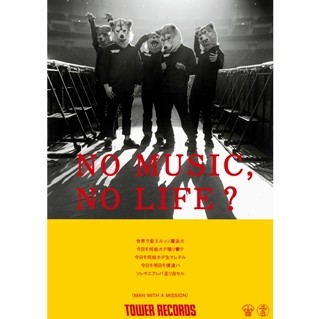2016年5月に亡くなった冨田勲さんの追悼公演が11月11日、12日に東京・Bunkamuraオーチャードホールで開催される。前回に引き続き、そのオーケストラと初音ミクの音が交わるステージの裏側を支えることぶき光の言葉を紹介したい。冨田さんとの共演での課題となるのは、躍動的な生楽器たるオーケストレーションと統制された電子音たるミクの音をいかにして適切なタイミングで重ね合わせるか、そして両者を違和感なくオーディエンスに聴かせるかといった問題だ。ことぶきと冨田さんの仕事は、2012年の「イーハトーヴ交響曲」の初演以来であるが、これらの課題をクリアするカギは20年以上も前、90年代初頭の解凍P-MODELでのパフォーマンスや平沢進のソロライブにあったという。
解凍P-MODELとは、"凍結"と呼ばれる一旦の活動休止期間をおいて、91年から93年に"解凍"と称して再始動していた時期の同バンドを指す。ことぶきは解凍以前よりP-MODELに参加していたが、その時のレコーディングの成果は残念ながらライブ映像音源としてしか残されていない。一方で解凍P-MODELは、凍結以前よりも積極的にシーケンサーやサンプラーといったデジタル機材の使用を前面に押し出し、洪水のような電子音とバンドアンサンブルとが共存した、クラブシーンなどとも異なるテクノサウンドを展開。そのステージでことぶきは、当時のドラマー・藤井ヤスチカが刻むバスドラムから、全体のシーケンサーを回す"ヒューマン・クロック"と呼ばれるシステムを披露。自身を取り囲むようにシンセを縦(!)に並べた奇抜なパフォーマンスもみせ、そのアクロバティックなスタイルから"キーボード妖怪"とも評された。"ヒューマン・クロック"のシステムは、冨田さんと共に作り上げてきたステージの核の一つ。第2回は、その点に着目しながら、解凍P-MODEL時代の逸話や平沢との楽曲制作の裏側までを振り返ってもらったエピソードを中心にお伝えしたい。
解凍P-MODELの映像を見た冨田さんが「できるじゃん」って
――冨田さんのお仕事の話も少しずつ出始めたところで、今回のコンサートでのことぶきさんの役割をあらためて教えていただけますか。
プレイヤーとしてのエレクトロニクス奏者というのが1つあります。それらを含んだ同期とかシステムの枠組みを作る役割、それと舞台の演出という役割、その3つですね。
――冨田さんから声がかかったのはいつ頃ですか?
「イーハトーヴ交響曲」の仕込みの段階。シンク(同期)システムとか"ヒューマン・クロック"で周りを走らせる仕組みをどうやって作るかと試行錯誤していた時ですね。
――"ヒューマン・クロック"というと解凍P-MODELで使われていた手法ですよね。
よくご存じで! まさにそうなんですけど、でもそれって今になって分かる話で。90年代当時のオーディエンスは誰も気付いてなかった。ただ、それは知らなくて良いことで。例えば劇団四季やディズニーランドが「私たちはこういうシステムでやってます」と説明するわけないじゃないですか。むしろバレない方が良い。でもなぜこのように、舞台裏の話を聞いていただいているかというと営業、要は金の話です。そして、なぜこれが必要かというと、次を作れないから。今思えば、こういうのって2、30年前にはある意味、必要なかったのかもね。それか、僕らがバカすぎて気付いてなかったか(笑)。
――冨田さんは、その解凍P-MODELでのことぶきさんのプレイをご存じだったんですか。
仕込みの初期段階で「例えばこういうことです」と『BITMAP 1979-1992』(92年)*なんかの映像を見てもらいました。と言うのも、「テンポを30%以上の揺らぎで制御するなんて無理だよね?」って話を振られてね。冨田先生も色んなシステムを作っていて、すごく現場をご存じ…むしろオーソリティー(権威)なくらいですが、「いや僕ら30%以上どころか完全に(演奏を)止めてからBPM180まで、0から加速していくみたいなのをやってましたので、OKです」って返すと「えー!?」と驚かれたんですよね。それで実際に映像を見てもらったら「できるんじゃん」って。
*『BITMAP 1979-1992』:解凍P-MODELのツアーを収めたライブVHS。2014年にはDVDとして再発された。
冨田さんとの2つの課題
――当時の「NO ROOM」の演奏なんてまさにそれでしたね。一度止めて、一気に加速するという。
まさにそう! ああいうのはクラシック界、ハイ・アート*の世界だと、多分雑に見えると思うんだ。でもぶっちゃけ、ハイ・アートの方が中身だけ見れば雑なんだよね。彼らのテンポの揺れってハンパない。そのズレを人数で上塗りして作り上げている、つまり目くらまし戦法のものすごいやり方です。もっと言えばオーケストラって装置は、人数を重ねるために倍音を削ってるわけじゃないですか。弦1本弾けば世界観ができる楽器の豊かな倍音をわざわざ削って、音の豊かさも消したがゆえに人数を重ねることによって、別の音色を作り上げることが可能になった。なので揺らぎはあったほうが、あの世界を出すためには有効で。それを冨田先生はシンセでやっちゃったわけだ。シンセのダメなところとして単音の中に入ってる情報量があまりにも少ないということがよく言われますよね。ただ、それだったらオケの楽器の方が一つ一つで見ればもっと少ない。なぜ皆が「オケ楽器の音は豊かな音響を作れる」という勘違いをしてるかと言えば、(音を)重ねてるからです。それを冨田先生は理解しちゃった。何の性格も持たないものにリメイクしちゃった楽器の音を、あえて人数重ねて別の音響感を作るやり方。それをシンセでやったのが冨田先生なんですよ。
*ハイ・アート:ポップ・ミュージックなどの大衆芸術(ロー・アート)に対して、理解するのに一定の教養を必要とする芸術のこと。クラシック音楽や古典的な演劇、絵画など。
*倍音:基本となる音の周波数に対して2倍以上の周波数を持つ音。音には正倍数の倍音が含まれている。ギターやベースのハーモニクス奏法などでも身近に知られる。
――"ヒューマン・クロック"の仕組みは今回のコンサートでも生かされてるんですね。
そうです。やってることは何年も変わってないですね(笑)。
――冨田さんには、平沢さんのソロライブ映像も見せられたと伺いました。それは「Orchestral Manoeuvres In The Nurse」*ですか?
何で知ってるんですか(笑)。その通りです。冨田先生との仕事にはテーマとなる課題が2つありました。1つは"ヒューマン・クロック"での同期をどうするか、もう1つはオケとコンピュータをどうやって共存させるか。前者は『BITMAP 1979-1992』を、後者を平沢さんソロのものを、それぞれ参考にしながらやってみました。
*「Orchestral Manoeuvres In The Nurse」:90年に行われた平沢のソロライブ。電子音を基調としながら、看護師の仮装をした生楽器の演奏チームがバックにつき、ことぶきもキーボーディストとして参加していた。公演タイトルは、70年代から活動しているシンセ・ポップバンド、オーケストラル・マヌヴァーズ・イン・ザ・ダークのもじり。