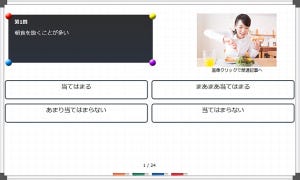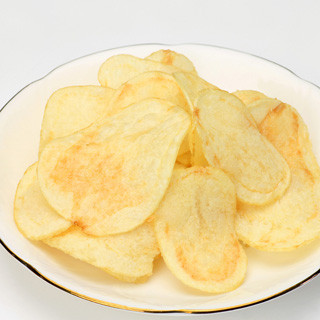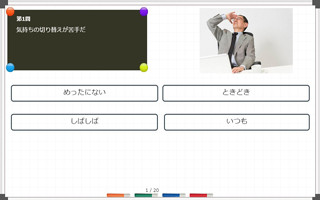ただ、予防にどれだけ努めていても、残念ながら発病リスクをゼロにすることはできない。万一に備え、脳出血の治療法も知っておこう。
ほとんどの場合、まずは点滴治療
福島医師は、脳出血の治療は手術と点滴治療に大別できると話す。ただ、脳出血の原因は圧倒的に高血圧であるため、血圧を下げる薬を用いてから脳の腫れを軽くする薬を点滴するパターンが多いという。
それでも血がなかなか止まらなかったり、もしくは最初からある程度出血の量があったりする場合は開頭手術となる。例えば、最も脳出血を起こしやすい「被殻」と呼ばれる部分では、血腫の量が30ml以上になったら積極的に手術をする。最近では開頭をせずに、内視鏡で500円玉程度の大きさの穴を開けて、そこから血腫を取り除くという治療も出てきている。
しかし、複雑な機能を有した脳だけに、出血した場所によって治療方法は異なってくると福島医師は解説する。
「視床出血の場合、脳の中で特別大切な場所となるため原則として開頭手術をしませんし、予後の改善も期待できません。ただ、脳室に出血がおよんでいると、水頭症を合併することもあるため、脳脊髄液を逃すような手術をすることはあります。また、小脳の出血では3cm程度の出血でも出血部位が脳幹といういわば生命維持装置に近いため、早い段階で手術をしますね」。
一方で、脳動静脈奇形(AVM)のように動脈と静脈が複雑に絡み合うことで出血を起こすケースでは、奇形の血管を摘出して再度の出血を予防する。出血が見られない症例では、放射線治療も血管奇形の縮小効果が得られる場合もあるため、治療の選択肢に入ってくるという。
普段の節制と迅速な受診を心がける
脳出血により生じた症状の回復過程は、その出血範囲と部位に左右される。残念ながら、完全にダメージを受けてしまった細胞は元に戻らないため、発症後の後遺症は少なからず残ってしまう。
日ごろからの食事における節制が脳出血予防には必要なこと、そして突然の頭痛やしびれなどの脳出血とおぼしき症状が出たら、一刻も早く医療機関に行くことが予後をよくするために大切だと覚えておこう。
※写真と本文は関係ありません
記事監修: 福島崇夫(ふくしま たかお)
日本大学医学部・同大学院卒業、医学博士。日本脳神経外科学会専門医、日本癌治療学会認定医、日本脳卒中学会専門医、日本頭痛学会専門医、日本神経内視鏡学会技術認定医。大学卒業後、日本大学医学部附属板橋病院、社会保険横浜中央病院や厚生連相模原協同病院などに勤務。2014年より高島平中央総合病院の脳神経外科部長を務める。