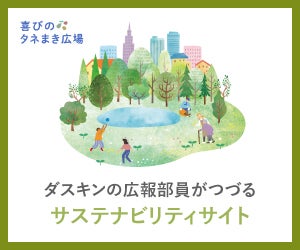持続可能性を意味する「サステナビリティ」。最近になって浸透したイメージが強い言葉ですが、実は半世紀以上前からサステナブルな社会の実現をめざして取り組みを続ける企業があります。
それは、清掃・衛生用品のレンタル事業をはじめ、「ミスタードーナツ」といった外食産業なども手掛ける株式会社ダスキンです。1963年の創業以来、「物を大切に、繰り返し、みんなで使う」という発想で、社会の役に立ち、人々の暮らしを豊かにする事業を展開してきました。
創業時よりチャレンジ精神旺盛な社風で、社員一人ひとりのアイデアから、時代に先行した多くのサステナブルなサービスが誕生してきました。時には何度も試行錯誤を繰り返し、それでもくじけることなく、社会の役に立つために果敢にチャレンジを続けるダスキン。そんな企業の歴史とすべての事業活動の根底にある思いに迫ります。
日本の掃除を変えたい……創業者の思いが紡いだダスキンの歴史とは
ダスキン創業のきっかけは、1961年にまでさかのぼります。創業者の鈴木清一が、アメリカの知人から「ダストコントロール」という新しい技術を教わったことがはじまりでした。
ダストコントロールとは、ホコリをたてずにホコリを取って、包み込む技術。それは、その当時日本で行われていた掃除とは、まったく異なるものでした。
家庭用商品第1号【ホームダスキン】の誕生
1960年代の日本の掃除といえば、ハタキとホウキでホコリを集めて、ぞうきんがけをするのが一般的でした。手間がかかり、重労働で、冬場には冷たい水を使うので、手にひびやあかぎれができるなど、家事の中でも掃除は大きな負担となっていました。
「ダストコントロール技術を活かしたら、日本の家庭の掃除をもっと楽にできるかもしれない」。そう考えた鈴木清一の頭を、さらにこんな考えがよぎります。
一定期間、このダストコントロール技術を取り入れた化学ぞうきんをお客様に貸し出して、汚れたものと交換することを繰り返す「貸しぞうきん」を商いにできないだろうか……。 |
すぐに研究開発が開始され、1963年2月にはダスキンの前身となる株式会社サニクリーンを設立。11月には小さな工場も開設されました。そして、翌年6月に社名を株式会社ダスキンに変更し、10月にはついに家庭用商品第1号となる化学ぞうきん「ホームダスキン」が発売されたのです。
水を使わずに、さっと拭くだけでホコリを包み込む新しい掃除方法は、人々をつらい水拭き掃除から解放し、「魔法のぞうきん」と呼ばれました。
この画期的な新商品は、全国への展開方法もまた画期的でした。
ダスキンの理念に賛同していただける方々に、ダストコントロール事業をビジネスチャンスとしてほしい。 |
そんな思いから鈴木清一は、加盟店が商品を販売・提供するフランチャイズシステムを導入。さらに、ホームダスキンは買い取りではなく、定期的に汚れたものをキレイなものと取り換えるレンタルシステムが採用されたのです。
この2つのシステムは、当時の日本では非常に珍しいビジネスモデルでした。そして、この時取り入れられた2つのシステムが、その後のダスキンの事業のあり方を形づくる基礎となっていきました。
結果的にこれらの取り組みが社会課題を解決することにもつながります。契約家庭を訪問してレンタル品をお届け・回収するお客様係には女性を積極登用。女性の社会進出が進んでいない当時を先取りする先進的な取り組みをしました。
さらに、ホームダスキンのレンタルシステムは、環境にやさしい循環型ビジネスの先駆けでもあり、使用済みのレンタル品は回収し、97%を再商品化。現在では、どうしても再商品化が難しい残りの3%は、モップやマットについたホコリや汚れとともに再資源化されています。
【ミスタードーナツ】1971年日本1号店オープン
ホームダスキンの事業もようやく軌道に乗り始めた1968年、鈴木清一はフランチャイズシステムを学ぶためアメリカへと渡りました。そして、そのシステムを学ぶために訪問した先が、1955年にアメリカで開業した「ミスタードーナツ」でした。
店舗でドーナツを味わった鈴木清一は、そのおいしさに感動します。
こんなにおいしいドーナツをひとりでも多くのお客様に食べてもらおう。そしてひとりでも多くの人々に喜んでもらおう。 |
これまで行ってきた清掃用品のレンタル事業とは畑違いのビジネスながら、「商売をしながら、フランチャイズシステムを実践的に学ぶ機会となる」と考え、日本での事業展開を検討。
その後、提携内容の詳細を決めるため、再びアメリカを訪問。そこで提示されたのは当初の話とは異なり「東京・大阪の2大都市のみでなく、日本全国でフランチャイズ展開する権利を譲渡する」という契約内容でした。また、契約金も、当時のダスキンの資本金の約2倍に相当する高額なものでした。
鈴木清一は、ホテルに戻りベッドに潜り込んで、一晩中頭を抱えたといいます。もしも、この事業が失敗すれば間違いなくダスキンはなくなる……と。大いに悩んだ末に出た結論はこうでした。
一からフランチャイズを学べば、きっとダスキンの加盟店の皆さんにもお返しができるはず。 また、日本に前例のないドーナツチェーンをつくれば、日本の皆さん、特に若い方の新しいビジネスチャンスとなるだろう。 |
契約は締結され、1971年4月、住宅開発が進む大阪郊外のロードサイドに、ミスタードーナツ第1号箕面パイロットショップがオープンしました。ガラス張りの外観や鮮やかなオレンジ色のユニフォームをまとったスタッフが働く店内はアメリカを彷彿とさせ、連日多くのお客様が訪れる大盛況となりました。
オープンから半年後には、スタッフを育成するミスタードーナツトレーニングセンター(現・ミスタードーナツカレッジ)も開校し、店舗は全国へと拡大。ミスタードーナツは若者を中心とした雇用を創出し、人々の憧れの職場となっていきました。
その後も時代に合わせて、現在までにさまざまなチャレンジを実施している「ミスタードーナツ」。一部店舗では、環境に配慮した食器の活用や閉店時廃棄のドーナツのリサイクルなど、サステナブルな取り組みを積極的に行っています。
ダスキンのサステナビリティはこれだけに留まりません。当時、自由で先進的だったアメリカのビジネスを取り入れ、日本の暮らしを豊かにしていきたいという思いで色々なチャレンジをしてきました。
1978年にスタートした家庭用品や趣味用品、旅行用品などを貸し出す総合レンタル業「レントオール」は、大量生産・大量消費の時代に逆らい、人々の意識を変える取り組みとなりました。また、1988年に開始された家事代行サービスの「メリーメイド」は、家事は主婦の仕事とされていた時代に、女性の家事負担を軽減しゆとり時間を生み出すサービスとして、人々の暮らしに豊かさをもたらしました。
試行錯誤の連続……それでもチャレンジし続ける理由とは
こうして掃除用品のレンタル事業とフードサービスの2本柱を確立したダスキン。順調に歩みを進める裏では、多くの苦労や困難も経験してきました。
中でも特に障壁の大きかった取り組みが、先ほど紹介した総合レンタル業「レントオール」です。
必要な品を貸し借りすることで、物を活かす場づくりができないものか……。 |
そんな思いから生まれた事業でした。
しかし当時は、高度経済成長を背景に大量生産・大量消費、使い捨ての文化が広がり、物を所有することがよしとされた時代。生活用品の総合レンタル業はほとんどありませんでした。
そこで、四季の行事や季節ごとの変化など人々の暮らしを一つひとつ丁寧になぞって、取り扱う商品を慎重に選定し、お客様視点でカテゴリをつくりました。しかし、ようやく品目を選んでも、レンタル業への理解が進んでいなかった当時は風当たりが強く、「販売店に影響を及ぼす」との懸念もあって商品供給を渋るメーカーも。スタートからいきなり窮地に立たされます。
そんなムードを打ち消してくれたのは、当時30歳前後の団塊の世代です。戦後の物不足を鮮烈に記憶している戦前世代とは異なり、団塊の世代は物を所有することに対する執着が少なく、合理的に趣味や生活を楽しむ手段としてレンタルは瞬く間に浸透していったのです。
その後は、運動会で利用されるテントやスポーツ用品、冬のレジャーのスキー用品、単身者向けには1年単位で貸し出す家具や家電など時代をとらえた商品ラインアップで、事業は順調に成長していきました。
ダスキンの事業は、どの事業もとんとん拍子で成長を遂げたわけではありません。100戦以上90敗と言われる程失敗も多かったそう。ホームダスキンの事業開始時は、「ぞうきんは使い古しの布でつくるもので、買ったり借りたりするものではない」という認識が当たり前だった時代。1軒1軒地道にご家庭を訪問して実際に掃除をし、お客様に便利さを実感いただくことが契約の増加につながりました。
また、ミスタードーナツの開店にあたっては、「ぞうきん屋が、飲食業なんて」という声があがったほか、食品輸入規制の影響でアメリカの店舗と同じミックス粉(小麦粉に砂糖などの原材料を配合したオリジナルの粉)を輸入できず、自前で調達先を見つけなければならないといった出来事も。
しかし、どのような状況でもチャレンジを続けてきた理由には、ダスキンが創業当初から大切にしているとある思いが深くかかわっています。
これは、ダスキンの経営理念の一部です。
それが本当にお客様の喜びにつながることであれば、失敗を恐れず、苦労をいとわず、とことんチャレンジしてほしい。 |
そんな創業者の思いを継承し、今も昔も変わらず常に挑戦し続ける企業として歩んできたのです。
サステナビリティで人々の暮らしを支えるための新たな取り組みとは
創業時から受け継がれてきたサステナビリティの取り組みとチャレンジ精神。それは、現在も変わらず大切にされ、新しいサステナブルなサービスが生まれる原動力となっています。
ごく最近誕生した2つのサービスをご紹介しましょう。
【イベント衛生サービス】
多くの人が集まるイベント会場の感染対策や衛生管理を請け負うサービスです。これまでさまざまなイベント会場の設営や運営を行ってきたレントオールのノウハウと、清掃用品をレンタルするダストコントロールと衛生サービスを提供する事業の知見が組み合わさって誕生しました。
新型コロナウイルス感染症の影響で、各種イベントの延期や中止などイベント業界を取り巻く環境が大きく変化し、イベント実施時には来場者・関係者の安全はもちろん、感染拡大防止の観点からも衛生管理が重要なポイントとなったことに始まったこのサービス。
近年では新型コロナウイルスワクチンの大規模接種会場の設営・衛生管理の運営を担当し、withコロナやafterコロナ時代の現在は、展示会やコンサート・スポーツ大会などの会場で来場者が安心して楽しめる空間づくりを行っています。
イベント衛生サービスの特長
・会場受付や入口に、表体温計測機器、吸塵・吸水マット、列の密接緩和用フェンス
・会場内諸室に空間清浄機、飛沫対策パネル、開放による捕虫器
・会場各所に手指消毒場所の設置
・手すりやドアノブの拭き上げ、トイレやゴミステーションなどの循環清掃
【防災サポートサービス】
災害発生時に自治体が抱える課題のひとつとしてよく挙げられる、避難所の設置運営の難しさ。年齢、性別などが異なる様々な人が滞在する避難所では、感染症対策だけでなく人々の導線やレイアウトも重要となります。
そんな課題にアプローチするため、2022年7月にスタートしたのが防災サポートサービスです。災害発生時の敏速な避難所の開設支援を目指して各自治体と連携を図り、避難所開設に必要な資材の提供と避難所の衛生管理で、地域の人々の避難所生活が少しでも快適なものとなるようサポートします。
防災サポートサービスの特長
・避難所開設に必要なレンタル商品約100アイテムを全国の各拠点に常備
・全国どこでもすべての資材を敏速に供給
・管轄の店舗が被災にあった場合でも敏速に近隣店舗が対応
・事前の価格設定で、災害時の価格高騰時にも安心
これらの感染症や災害といった社会課題の解決をめざすサービスもまた、ダスキンが現在に至るまで大切にしてきたサステナビリティが起点となっています。
時代を先取るダスキン。今後もサステナビリティとともに歩んでいく
自分たちにできることは何なのかを必死に考え、試行錯誤の末にさまざまなサービスを展開してきたダスキン。それは、失敗を恐れないチャレンジ精神が根付いている何よりの証です。これからもダスキンはサステナビリティを大切に、人々のよりよい暮らしのために挑戦し続けます。
***
人に、社会にやさしさと喜びを届ける「喜びのタネまき」。ずっと大切にしてきた変わることのないダスキンの想いです。「喜びのタネまき広場」では、そんな「喜びのタネまき」を通して、喜びや笑顔があふれるサステナビリティな活動の数々をご紹介しています。
[PR]提供:株式会社ダスキン