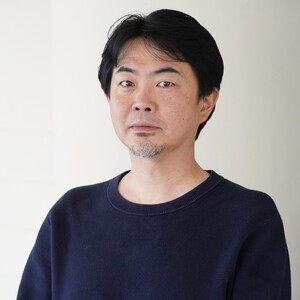――制作会社の社長という立場で、地上波テレビの広告市場が縮小する一方、動画配信サービスが台頭するこの流れは、どう捉えていますか?
これはチャンスだと思います。社員全員と毎年面談しているのですが、若い世代のスタッフが本音でうらやましいです。世界に自分のコンテンツを発信できる環境がどんどん広がっていく彼らを、僕は「一撃世代」と呼んでるんです。見る景色も経済力も一撃で変わる可能性があって、いまじんが蓄えてきたものをそのために投資することもできるので、本当にうらやましい世代です。
例えば、アイドル好きの社員が、そのアイドルのマネージャーに交渉して、イベントや映像を作ったりしているんですけど、そのアイドルが新しい学校のリーダーズみたいに化ける可能性もあるわけじゃないですか。そうやって成功した社員は、契約の仕方も変えていかなければいけないですよね。これからは圧倒的なコンテンツを作ったら、それに見合う対価をきちんと支払うべきだと思いますし、そういう人がどんどん出てきてほしいです。
――そのために、積極的に企画が出せる環境を整備されているのでしょうか。
そうですね。映像化は無理だと言われていたHuluのドラマ『十角館の殺人』を立ち上げたプロデューサーも、原作者のいる京都まで通って信頼を勝ち得ました。そうやって、自分の好きなものを企画にして形にしていくのを見ると、すごいなと思うし、そういうスタッフがいっぱいいると会社としても強くなっていく。クリエイターとして個人の名前を売ってほしいけど、うちは組織力という面でも自信がありますし、いまじんブランドを今後も大きくしていきたいので、そのバランスを見ながら考えていきたいですね。
「あれはテレビ芸術」さんま×紳助伝説の生トーク
――ご自身が影響を受けた番組を1本挙げるとすると、何でしょうか?
昔、『27時間テレビ』(フジテレビ)の深夜のさんまさんのコーナーに、紳助さんが出たことがあったじゃないですか。あれは本当にすごいと思いました。生放送で本当に言っちゃいけないことをギリギリ避けながらの2人の掛け合い。あれはテレビ芸術ですよね。
――双方の攻守のターンがあって、互角に戦ってる感じがしびれました。
そうそう! しかも、あれ絶対台本ないですから。僕らが書くスタジオ台本って、収録でその通りにいくと面白くないんですよ。やっぱり台本に書けないことが起こると、その放送がハネるので、まさにそんな放送でしたよね。
――いろいろお話を聞かせていただき、ありがとうございました。最後に、気になっている“テレビ屋”を伺いたいのですが…
ABEMA第二制作局長の古賀吉彦さんです。弊社もABEMAさんとはいろいろお仕事をさせていただいてますが、近年見たコンテンツで個人的にワクワクしたものが、ABEMAの『1000万円シリーズ』(『亀田興毅に勝ったら1000万円』『朝倉未来に勝ったら1000万円』など)です。あれこそ先ほども申し上げた「見たいもの」だと思います。古賀さんは『1000万円シリーズ』以外にも、『72時間ホンネテレビ』や、恋リアの『オオカミ』シリーズ、2022年のカタールW杯を手がけていたりと、すごいなと思います。
第一印象は「若いのにスマートに会議を仕切る方だなあ」でした。我々の業界では、よく最初の会議だけ「威勢よくかます人」がいるんですが(笑)、そういうものが全くなく自然体で、これからのエンタメ業界に必要な“華”のある人だと思います。
- 次回の“テレビ屋”は…
- ABEMA第二制作局長・古賀吉彦氏