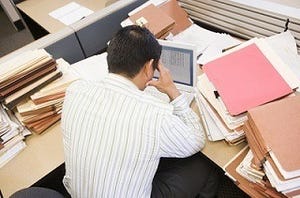本連載の第26回では「業務のバラツキを減らそう」と題し、業務品質やスピードのバラツキが生む弊害と対応についてお伝えしました。本稿では仕事の生産性をどう捉え、向上させればよいか、その考え方をお話します。
昨今の働き方改革のトレンドにより、多くの企業が社員の残業を減らそうと躍起になっています。それに伴い、上司から「残業を控えなさい」「仕事の生産性を上げなさい」などと指示を受けている方は多いのではないでしょうか?
しかしながら、サボっているのならまだしも、毎日ろくに休憩も取らずに必死で仕事しているのに、これ以上どうやって生産性を上げればよいのか見当もつかない。上司に聞くと「それを自分で考えるのも仕事のうちだ」と取り付く島もない。仕方がないので、とりあえず机の上を整理してみるか。このような経験、ありませんか?
生産性をどう捉えるか
「生産性」と一口に言っても、それを表すと考えられる指標はいくつもあります。社員1名あたりの売上高や粗利額、工場であれば投入原材料あたりの製品生産量などです。これらに共通して言えるのは「投入資源量あたりの生産量」、より平易な表現では「インプット1単位あたりのアウトプットの量」といったところでしょうか。これらは各々、「生産量÷投入資源量」「アウトプット量÷インプット量」で算出することができます。そして、この計算結果の値を増加させることがすなわち「生産性の向上」を意味しますが、そのためにはインプット量を増やさずにアウトプット量を増やすか、アウトプット量を減らさずにインプット量を減らすかの2択しかありません。
このことを踏まえて、オフィスワーカーの生産性について考えてみましょう。まず経営の観点からすると、インプット量を人件費と捉えることができます。そして人件費には本来、基本給と残業代に加えて賞与、社会保険料などが含まれますが、ここでは単純化するために基本給と残業代の合計金額と置きましょう。すると、一社員として基本給を直接的に増減させることはできないので、勤務時間の増減によって「残業代」のみコントロールが可能ということになります。そこで、ここでは勤務時間をインプットとみなすことにしましょう。
次にアウトプット量についてですが、こちらは営業であれば売上高や粗利などのわかりやすい指標を設定することもできますが、内勤の事務など売り上げに直接かかわらない職種もあるので、工夫が必要です。そこで、アウトプット量としては一旦「顧客価値」を設定し、職種ごとに「自分たちが仕事の結果として生み出す顧客価値は何か」を定義するのです。なお、この「顧客価値」は奥が深く、本稿の中で論ずるには重すぎるテーマなので、別の機会に詳しくお伝えすることとし、ここでは割愛いたします。
ここまでの議論をまとめるとインプットには「勤務時間」、アウトプットには「顧客価値」を設定し、生産性は「顧客価値÷勤務時間」で測定するのがよいのではないかと考えられます。そして、「顧客価値」を実際の仕事に当てはめて考察すると、例えば営業ならば一般的な「売上額÷勤務時間」に加え、「商談件数÷勤務時間」や「顧客からの相談件数÷勤務時間」など、営業事務ならば「見積書作成件数÷勤務時間」や「問い合わせ対応件数÷勤務時間」などを生産性の指標として設定することが可能でしょう。
生産性を上げるためにすべきこと
無事に生産性を定義できたら、今度はどうやってそれを上げるか考えましょう。この時点ですぐに「とにかく一生懸命頑張ろう!」などと根性論、努力論に走ってはなりません。生産性を上げるということは本質的にどういうことなのか、そのロジックを考えることが近道になります。ここでは4つの方法をご紹介します。
1.稼働率を上げる
もし現状、勤務時間内で仕事に集中できていない時間帯があれば、それは顧客価値を生まずに時間をムダにしていることと捉えられます。職場にいるのに事実上、稼働できていないということで稼働率が低い状態とも言えます。
例えば一日に残業を含めて10時間勤務している人が、実働5時間であれば稼働率は50%ということになります。この場合、仮に稼働率を100%にできれば残業はおろか、5時間勤務で今と同じ顧客価値を生むか、現状と同じ10時間勤務で今の2倍の顧客価値を生むことができます。いずれの場合でも生産性は2倍になるということですね。
なお、稼働率が低い原因が単に「サボっている」ということであれば、上司や同僚からのプレッシャー等で対処できるかもしれませんが、サボっているのではないけれど、仕事に集中できないという場合もあります。特に睡眠不足や過剰なストレスなどによりパフォーマンスが低下している状態を「プレゼンティズム」と呼びますが、そのような場合には早急に原因を突き止め、対処することが必要になるでしょう。
2.顧客価値を生む業務の比率を上げる
現状、勤務時間内はほとんど休む間もなく仕事に集中できているという方も少なくないでしょう。そのような方はすでに忙しく働いているので、「生産性を上げろと言われても、これ以上頑張れない」と思われるのではないでしょうか。しかしながら、職場での仕事のすべてがそのまま顧客価値を生むことにつながっているとは限りません。むしろ日々行っている仕事の中には、顧客価値を生まないものが紛れ込んでいることが一般的です。
これが一体どういうことなのか、具体例で説明しましょう。例えば家電メーカーのカスタマーセンターで働いている社員が、自社の商品の不具合について顧客から問い合わせを受けた場合、まずは顧客から詳しい状況を聞き出すはずです。そしてすぐに回答できない場合には、社内のデータベースで情報を検索したり、ベテラン社員に聞いたりして回答します。
このケースにおいて、顧客価値を「不具合を修正するための情報を伝えること」と定義したとします。すると、「社内のデータベースで情報を検索する」ことと「ベテラン社員に聞く」ことはどちらも顧客価値を生まない作業として捉えることができます。こう話すと必ず「わからないことを調べたり聞いたりすることは正しい情報を伝えるのに欠かせないのではないか」と反論される方がいます。それはそうなのですが、だからといってこのケースにおいて調べたり聞いたりすること自体が顧客価値を生む仕事とは言えないのです。
顧客の立場に立つと、「不具合を修正するための情報を聞く」ことさえできればよいのであって、もし仮にオペレーターから「お調べしますので少々お待ちください」と言われて30分も待たされた上に、「データベースから情報を調べて、ベテランにも相談しましたがわかりませんでした」と言われたらどうでしょうか。顧客にとっては「情報の検索」や「ベテランへの相談」は価値を提供する仕事とは言えないのではないでしょうか。そのため、いかに検索や相談の時間を減らして、顧客への情報提供に集中できるかが生産性向上のカギになります。
このように仕事の中から顧客価値を生まないものを特定し、それを減らす一方で、顧客価値を生む仕事を増やすことによって生産性を上げられるのです。
3.顧客価値の生み出し方を変える
顧客価値を生まない仕事を特定して減らすことができたら、次は「顧客価値を生む仕事」を今より効率的にできないかを考えます。これは業務プロセスや使用するツール、意思決定ルールの変更や自動化などによって実現可能です。わかりやすい例で言えば、顧客からの問い合あわせ対応をメールからチャットに変更することで迅速な対応を可能にしたり、コールセンターのオペレーターが電話応対の際にAIを駆使することで、より幅広い内容に即座に回答できるようにしたりすることなどが挙げられます。
また、営業であれば、これまで紙の資料を印刷し、1枚ずつめくりながら顧客にプレゼンしていたのを、タブレット端末を用いて顧客に響くプレゼンをするようにしたり、内勤の事務であれば、これまでエクセルファイルの伝票に手入力していたのをマクロで自動化したり、さらに受注データをRPA(ロボティクス・プロセス・オートメーションの略)で自動入力させたりするのも、「顧客価値を生む仕事」の大幅な効率化に繋がるでしょう。
4.顧客価値を再定義する
一般的な生産性向上の取り組みは、これまで紹介した3つで十分にカバーできますが、さらに高次元のレベルの方法もあります。それは顧客価値を再定義することです。例えばスターバックスコーヒーが「コーヒーそのものを提供する」というのではなく、「第三の場所」というコンセプトのもと、「ゆったりとくつろげる時間を提供する」ことを顧客価値と定義したように、それまで当たり前のように考えていた顧客価値をゼロベースで捉え直すということを意味します。
この考え方を営業の仕事に応用すると、例えば「顧客の利用シーンに応じた自社商品の紹介」という仕事は、「顧客の課題に応じた自社商品を含めたソリューションの提供」という具合に捉え直すことができます。これは少々違いがわかりにくいかもしれませんが、前者が「自社商品をいかに売るか」にフォーカスした営業である一方、後者は「顧客の課題をいかに解決するか」にフォーカスした営業です。顧客の立場に立ってみると、どちらがより高い価値を提供してくれるかは明々白々でしょう。
このように、これまでの仕事が顧客に提供している価値についてゼロから見直して、本当に顧客が困っていることは何か、真に欲しているものは何かということを突き詰めて考え抜くことで、顧客価値を再定義し、新しい価値を提供できるように既存の仕事を再設計すると、顧客価値を一気に増大させることができる可能性があります。
本稿では仕事の生産性をどう捉え、向上させていくかについてお話しました。ここで述べた例はどの職場や職種にも当てはまることではありませんが、考え方は広く応用できるはずです。自社やご自身の仕事について生産性向上の取り組みの参考になれば幸いです。