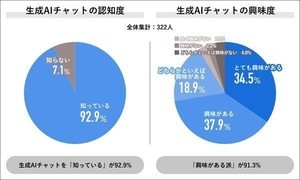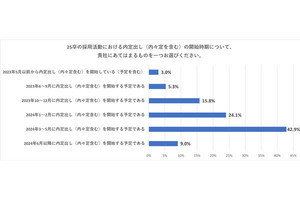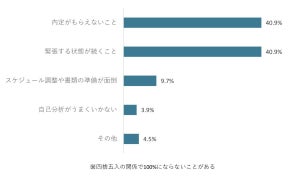理系学生の面接では、技術面接官やエンジニアが参加するケースがあります。特徴を理解して準備をしましょう。
Check Point1.面接官は専門外であると認識してわかりやすく説明する
理系学生の面接では、人事担当者だけでなく技術面接官や現場のエンジニアが参加するケースがあります。
特定の決まったパターンがあるわけではありませんが、専門分野が同じでも、大学の研究レベルには精通していなかったり、専門分野が異なる社員が面接官となるケースも少なくないので、できるだけわかりやすく説明できるように準備しましょう。
専門性が高い内容をわかりやすく説明できることは、自分の専門性の高さの証明でもあります。技術面接官からの質問であっても、人事担当者の存在を常に意識し、相手の理解度を確認しながら話を進めましょう。
Check Point2.研究内容については全体像から説明するように配慮する
研究内容を説明する際は、いきなり各論から入るのではなく、まず全体像から説明することを心がけましょう。
研究分野や対象、研究の目的や課題など、研究の背景や前提条件など研究の概要から話を進めます。全体像が理解されたら、具体的な研究活動について質問されるでしょう。それに答える形で、日々の具体的な研究活動について説明をしていきます。
ただし、面接は学会発表のプレゼンとは異なります。技術論になるとついつい熱くなって持論を展開してしまいそうになりますが、面接官との対話を意識して冷静に答えていきましょう。
Check Point3.研究における考察はPDCAを意識して説明する
研究活動は、日々、どのようにPDCA(Plan=計画、Do=実行、Check=評価、Action=改善)を回しているのかを説明できるようにしましょう。
目標値をどう定め、どんな課題感を持って研究に取り組んでいるのか、目標数値の達成や課題解決のためにどう計画し、どんな工夫をしているのか、そして、結果をどう分析し、どう改善しようと考えているのかという視点で活動を整理します。
理系出身者に限らず、どんな仕事もPDCAの連続です。自分にPDCAのセンスや実行力が備わっていることを表現することを心がけましょう。
Check Point4.研究意義は社会的に貢献する視点で説明する
理学の役割は、自然の仕組みや自然現象の真理を見極めることにありますが、工学の役割は社会を便利にしたり快適にしたり、人類の幸福に役立つモノや仕組みを生み出すことです。
特に、工学系の研究では、自分がいったい何のために研究をしているのか、また、研究を通して発見したこと、研究の成果が社会にどのように役立つのかについて、自分なりの思いや考えを説明できるようにしましょう。
あらためて自分の研究の意義を見つめ直してみて、社会が求めていることやニーズとどう結びつくのかを整理しておくことが重要です。
Check Point5.研究テーマ選定理由を問われたら研究に対する意欲を伝える
面接では、研究テーマを選んだ理由について質問を受けるでしょう。自分で主体性を持って決定した背景を説明しましょう。しかし、自分で決定したのではなく、指導教授によって決められたり、あらかじめ用意されたテーマの中から選んで決めるようなパターンもあるでしょう。
答えに困ることもあるかも知れませんが、受け身の姿勢をそのまま説明するのはよくありません。たとえ他者から与えられたテーマであっても、その研究テーマに対して自分がどう考えているのか、研究に対する意欲や前向きな姿勢を伝えるようにしましょう。
Check Point6.苦労したことを問われたらガクチカの回答意識で答える
面接では、主に専門知識や技術のレベルが確認されますが、「研究活動で苦労したこと」についても質問があるでしょう。そんなときは、ガクチカ(学生時代に力を入れて取り組んだこと)を回答する意識で答えるといいでしょう。
例えば、「実験ではなかなか思うような数値が出ずに苦労しました。しかし、担当教授だけでなく先輩にもアドバイスをいただき、異なるアプローチの手法を試した結果、予想した結果が得られました」というように、どんな課題に直面し、それをどう乗り越えたかについて具体的に表現することを意識しましょう。
Check Point7.入社後に何に挑戦したいのかを整理しておく
技術責任者や現場のエンジニアが面接官として参加している場合は、「わが社のエンジニアに求める知識レベルや技術があるのか?」を確認しながら、「具体的に何をやりたいのか?」が問われることになります。
つまり、会社が求める人材要件と本人の希望のマッチングをはかっているわけです。
その際は、単に志望する職種名を回答したり、手がけたい製品や技術を答えるだけでは不十分です。自分がどんな製品や技術を生み出したいのか、既存の技術をどう発展させたいのか、意欲的な回答をするように意識しましょう。
Check Point8.研究活動の仕事への活用をイメージしておく
理系学生の場合は、今まで自分が研究してきた分野の専門知識や技術と直接リンクしない職種に就く可能性もあります。
しかし、研究活動で培ったスキルや研究の基となった学術領域の知識は必ず活用できるはずです。データ分析、実験計画などの知識やスキル、各学科の専門知識などは、職種が違っても充分に役立つでしょう。
自分が研究活動を通してどんな専門知識やスキルを身に付けたのか、また、それは研究テーマと直結しない仕事でどう活用することができるのかについてイメージできるようにしておきましょう。
イラスト作成:内山弘隆