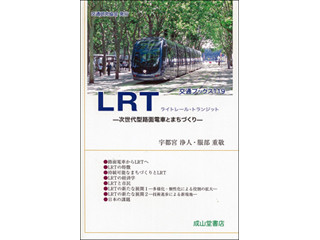乗り鉄、乗りつぶし系鉄道ファンにとって、鉄道路線の新規開業と廃止への関心は高い。JR三江線の廃止が迫り、お別れ乗車のにぎわいの報道に寂寥感も感じる。そんな中、未来に向けた取組みのニュースがあった。宇都宮市と松山市のLRT路線新設計画だ。
栃木県宇都宮市、同芳賀町と第三セクターの宇都宮ライトレールは3月20日、宇都宮市で合同会見を行った。国土交通省からLRT計画について工事を認可されたという趣旨だ。栃木県も3月22日に都市計画事業を認可した。これで今月中に着工し、4年後の2022年に開業する見通しとなった。
今年度の着工は現市長の選挙公約であった。今月は残り10日を切っている。合同会見の質疑応答で、市長は「来賓の日程調整が必要な起工式を待たずに、まずは測量、重機を入れた作業など、見える形で着工させたい」と抱負を語った。
認可された区間はJR宇都宮駅東口から東進し、ショッピングモールのベルモール、清原工業団地、清原台団地、宇都宮テクノポリスセンターを経由して、芳賀町の本田技研北門までを結ぶ。距離は14.6km。JR宇都宮駅東口~本田技研北門間の所要時間は普通(各駅停車)で約44分。快速で約37~38分とのこと。快速は宇都宮駅東口から7番目の停留場、平出町停留場で普通を追い越す。平出町停留場は2面4線の緩急接続構造となっている。運行間隔はピーク時に6分、オフピーク時は10分。
車両は新潟トランシスが製造し、3連接車体で全長30m。これは軌道敷設規定による最大長となる。将来的に特認手続きを取り、さらに長くすることも考慮している。軌間は1,067mmで、JR線や東武線と同じ。将来的な既存鉄道との乗入れを考慮したという。ただし、架線電圧は750ボルト。在来線は1,500ボルトだけど、これは線用敷地内に設置すると定められているため。既存の路面電車が採用する600ボルトより高い理由は、電気的な損失が少ないからだ。運転最高速度は70km/h以上とするけれども、当面は軌道運転規則にもとづき、40km/hが最高速度となる。
なお、計画では宇都宮駅西口から東武宇都宮駅付近を経由して、桜通り十文字(桜2丁目交差点付近)に達するルートもある。桜通り十文字は宇都宮市の西側各方面と宇都宮駅方面のバス路線が合流するところ。こちらも建設の意向があり、調査と関係各方面との調整が続けられるという。
一番の問題は、東西を結ぶLRTが「宇都宮駅をどのように通過するか」だろう。宇都宮駅は在来線ホームが地上駅、新幹線ホームが高架3階にある。そこで、宇都宮市とJR東日本は、JR宇都宮駅2階にLRTを交差させる方向で調整した経緯がある。栃木県経済同友会もその前提で東西駅前広場の構想図を発表していた。LRTの車両も、JR駅2階の通過を前提として、車両の高さを3,625mm以下にしている。
宇都宮ライトレールに関しては、費用対効果、過大な税金投入などを問題視して、いまだに反対意見も多い。また、道路の拡幅を行わずに軌道を設置することから、一般自動車、貨物輸送などでトラックを必要とする人々からも不安の声があるようだ。鉄道ファンとしては、新路線の開業はうれしく、期待したい。
愛媛県松山市のLRT延伸は構想段階にある。3月24日付の読売新聞記事「路面電車延伸 『実現性あり』」、愛媛新聞記事「松山路面電車 空港延伸、可能性確認 検討会報告書 全条件満たせば」によると、愛媛県と松山市が3月23日、伊予鉄道市内線を松山空港へ延伸する構想の実現性について、検討結果をまとめたという。
現状では採算性が厳しいとしつつ、空港利用者や沿線人口の増加、新工法によるコスト削減、空港リムジンバスの廃止、沿線開発の誘発など9条件をすべて満たせば費用対効果があると試算された。第6回松山空港アクセス向上検討会で報告され、承認された。
この構想の背景には、愛媛県などが実施するJR松山駅付近の連続立体交差事業がある。2008年に都市計画が決定し、2009年に事業が認可された。開業時は街外れにあった松山駅も、市街地が広がったことから市を分断する形になってしまった。そこで、松山駅を高架化し、周辺の踏切を解消して、新たな幹線街路も建設する。貨物駅と車両基地は北伊予~伊予横田間に移転し、跡地は駅前広場と土地区画整理事業を実施する。完成予定は2024年度とされている。
この事業に合わせて、伊予鉄道市内線のJR松山駅前停留場をJR予讃線高架下に移設し、路面電車軌道を丁字路状に整備して、環状路線の両方向から発着できるようにする。松山空港延伸ルートは、新しいJR松山駅前停留場からさらに西側へ延伸して空港に至るという構想から始まっている。松山空港アクセス向上検討会は2015年から開催されていた。愛媛県、松山市、伊予鉄道、愛媛大学から委員が参加し、オブザーバーとして大阪航空局松山空港長、四国運輸局交通施策部長、四国地方整備局都市調整官などが出席している。
検討ルートは、JR松山駅から路面電車で延伸する3つのルートと、JR松山駅を通らず、郊外電車の郡中線から分岐するルート。合わせて4ルートある。新規建設区間はすべて路面電車、併用軌道で整備される。つまり、JR松山駅経由は伊予鉄道市内線に乗り入れ、土居田駅経由は路面電車を郡中線に直通させて、松山市の中心街、松山市駅へ直行させる。路面電車方式を採用する理由は、中心市街地で移動手段として定着し、松山らしさの象徴であり、新設道路を使用して新規用地取得を不要にするためでもある。
こちらも鉄道ファンとしては楽しみな計画だ。鉄道好きだからといっても、始めから終わりまで鉄道にこだわるわけではない。若いうちはともかく、休暇を取りづらい立場になれば、航空路線も駆使する。そして空港から都市中心部まで鉄道があれば利用したい。
ただし、「9条件をすべて満たす」という前提はかなり厳しそうに思える。報道ではすべての条件がクリアされていなければならないというけれども、空港リムジンバスの廃止は一般旅行客の利便性を考えると、厳しい。主要ホテル、観光地を巡回して空港を結ぶという形態の空港リムジンバスは便利だし、鉄道アクセスのある空港のほとんどで鉄道とバスは共存している。利用者に選択肢がないというだけで、不便な空港のレッテルを貼られそうだ。
併用軌道の形態では、最高速度が40km/hであるという「軌道運転規則」も忘れてはいけない。新たに整備された信号の少ない路線なら、リムジンバスは時速60km/hで走行でききる。しかし路面電車はLRTに進化したところで時速40km/h。この差は大きい。
宇都宮市は一部の専用軌道区間で速度を出せるように、最高速度70km/h以上で車両を導入する予定だという。しかし、軌道運転規則を改正して、もっと速度を出せるようにしたほうがいい。バスより大きな車体、ゴムタイヤより摩擦力が小さい鉄の車輪では、フルブレーキで停まれる距離が長いかもしれない。
しかし「軌道運転規則」が制定された1954(昭和29)年と現在では、車両の性能が大幅に向上しているはず。低コストで環境に優しく、公共交通の旗手として注目されるLRTだけど、課題は最高速度。LRTを生かすための法整備も必要となっている。