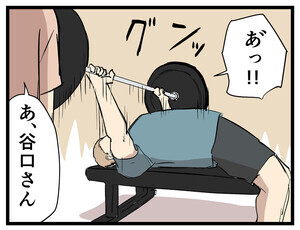厚労省は2040年に国内の認知症者当事者が、約600万人(国民の7人に1人)に達するという将来推計を発表しています。認知症の人口が増えるということは、認知症当事者をサポートする現役世代も増えるということ。仕事をしながら認知症の家族を支えるのは容易ではありません。さらに定年延長によって、働きながら認知症と診断される人も今後は増加する見込みです。
そんな「認知症共生社会」に向けて、社会はどう備えるべきか。企業の取り組みや当事者・家族の声を通じて、そのヒントを探るべく「認知症をめぐるビジネスケアラーの実情を考えるシンポジウム~共生社会の実現に向けて、企業に求められる役割と取組み~」に参加しました。
すでに取り組みを実行している企業、若年性アルツハイマーの当事者、家族の会など多角的な目線で語られた「認知症共生社会」の現状と未来とは――?
【イトーヨーカ堂】身近なスーパーから広がる共生社会―理解と制度で安心を支える
イトーヨーカ堂の「認知症共生社会」に向けての取り組みは利用者としてもありがたいものでした。
定期的に認知症サポーター養成講座を開催し、「認知症という病気や症状について、正しい知識を得ることが一番大事だと考え、8割いるパート従業員やお店で働くテナントの方、警備の方も含めて受講を推進しています」とイトーヨーカ堂 サステナビリティ推進部 総括マネジャーの小山遊子さん。
養成講座の開講を始めたきっかけは、高齢化が進む中、店内で起こり始めた異変。「例えば帰り道が分からないお客様がいたりと、今までと違ったことが起きていました。どう対応したらいいのかという声が従業員から集まり、本業であるお客様の接客を充実させるために講座を開催しました」ということ。
認知症当事者を家族に持つ者としては、日々利用するスーパーに理解者がいてくれるのは、それだけで生活の安心感がまったく違います。さらにこの取り組みは従業員の方にもいい効果を生んだそうです。
「家族が高齢に差し掛かるので参考になったという声が多い。講座の内容を仕事とプライベートの双方に生かしていきたいという声が非常に多くありました。また、講師は地域包括支援センターから来ていただくのですが、介護に直面した時に相談する地域窓口となる地域包括支援センターの存在を知ることも有意義だと実感しています」と小山さん。
実際に家族に介護が必要となった場合に利用できる「ワーク・ライフ応援プラン」では休業と短時間の勤務、介護休暇を状況に応じて選べるということ。 「育児と違って、介護はいつ始まるのかわからない。仕事で迷惑をかけてはいけないという責任感から、従業員が疲れ果てて辞めてしまうケースもあり、制度を充実させました」ということで、現状、介護休暇は700名程度が利用しているそう。
介護は周りから見えないことが大きな課題。認知症に関しては偏見もあり、病気を口にしづらいという現状も捉え、仕事と介護の両立を提案するポスターを店のバックルームに貼ったり、仕事と介護の両立ブックを配布したりと周知のための動きも活発に行っているそう。今後着実に、顧客も働く側も安心して生活できる場所になっていきそうです。
【大成建設】介護はいつ始まるかわからない―“備え”が従業員を守る
大成建設の場合は、「建設業の働き方を変えていこうと社員にヒアリングしたところ、介護に対して不安を感じている方が多いとの結果が出ました。そこで2010年から介護という観点から働き方改革を進めています」と管理本部 人事部 人財いきいき推進室室長の北迫泰行さん。
人手不足の現状で、介護離職を防ぐことは大きな課題です。そのため介護と仕事が両立できるように会社の制度や介護保険制度をまとめた資料を配布。社員が不安を解消することを目的に始めた介護セミナーはオンラインで家族も参加でき、休日開催にしたり、1ヶ月間見逃し配信をすることで参加者が増加しているといいます。
制度面では要介護者1名に対して通算180日の介護休業、介護休暇は半日単位、時間単位での取得も可能で被介護者の人数にかかわらず20日/年、両立支援フレックスを導入するなど充実していて「介護休暇の日数を整えることで社員が休みを取りやすくなる。2023年度の介護休暇利用は約240名、2024年度には300名を越すなどニーズは高いと感じています」とのこと。
また、「社員自身や親御さんが認知症と診断されても、心理的安全性が保たれていない職場だと会社に言いづらい。そのため、風土醸成をしてほしいという声が非常に多くなっています」と今後の課題も提示していました。
【当事者と家族の声】カミングアウトできる職場づくりが鍵―「言いづらさ」からの解放を
若年性アルツハイマー型認知症の下坂厚さんと「公益社団法人認知症の人と家族の会」代表理事の鎌田松代さんは、当事者と家族の視点から語ります。
46歳で若年性アルツハイマー型認知症を発症した下坂さんは「仕事での失敗が受診につながって診断を受けました。当時は認知症の知識がまったくなく、認知症になったら何もできなくなる、職場に迷惑をかけてしまうと考え、すぐに退職してしまった。振り返ってみると、職場に前もって認知症の正しい知識と理解があれば、部署を替えたりサポートを受けることで働きつづけることは可能だったと思います。働き続けることが症状の進行を緩やかにするということも経験しています」と貴重な経験を語ってくれました。
介護を経験した家族を代表する鎌田さんは「介護をしていることを言いづらいというのが一番の問題。制度があっても、休みが増えてくると正規職員で働くことに負い目を感じて、働く形態を変更せざるを得なくなったというような調査結果もあります」と、カミングアウトしやすい職場環境の重要性を訴えていました。「介護は先が見えないところが不安の要因」というのも大事な視点だと感じました。
早期発見と継続就労が、認知症共生社会の鍵となる
働きながら家族の介護を行う“ビジネスケアラー”は、2030年には318万人に達すると経産省は試算しています。それに関わる経済損失は約9兆円。もはや介護は家庭の問題ではなく、企業も認知症を“自分ごと化”する必要があることは明白です。
診断された当事者が働き続けること、介護の負担を軽くするためにも必要なのは早期発見、早期診断。認知症の進行を抑える薬も開発され、それによって初期の段階を長く保つことができれば、当事者も家族も長く社会とつながった生活を送ることができます。また社会としても、働き手不足の緩和や介護保険の負担を抑えるなどの効果が期待できます。
しかし現状では「早期受診、早期診断に結びつかない要因がある」と、鎌田さんと下坂さん。
「認知症というと中程度から重度の方の病態像をイメージされている方がまだまだ多い。そのため、同じ話をする、外出や料理の段取りに時間がかかるようになったというような軽度の認知症の状態では、年のせい、疲れているせいと捉えてしまって受診につながらないのではないでしょうか。認知症の病態像のグラデーションが幅広いことを知ってもらい、気づいた時に相談ができる環境をつくることが早期受診につながるのではないでしょうか」(鎌田さん)
「我々働き盛りは早期受診につながったところで、『認知症の診断が出てしまったら、この先どうなってしまうんだろう』という不安がまだまだ大きい。早期診断することによって役割を持って活躍できるところが増えていることを周知して、経済的な支援などがあれば受診に対する心理的な不安の軽減につながってくると思います」(下坂さん)
企業の“自分ごと化”が、社会を変える第一歩に
「認知症共生社会」「企業の役割」というテーマだけを見ると難易度が高そうに感じましたが、現場の人から出てきた解決策は「認知症の偏見をなくすために正しい病状を周知すること」「カミングアウトしやすい職場にすること」「助け合える企業風土」など、費用的負担は少なく、今すぐに始められそうなものばかり。とはいえ周知にも偏見をなくことも時間がかかることもたしかです。だからこそ、企業の自分ごと化が進み、いち早くその第一歩を踏み出してくれる企業が増えることに期待します。