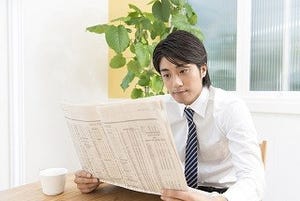前回は「必要(需要)」が「生産」を促し、企業が「利益」、私たちが「賃金」を得る……という流れについて説明しました。今回はその延長で「景気」について考えてみましょう。
「景気」とは?
そもそも景気とは何でしょうか。私たちは普段から、お天気の話をするように「景気はどうですか」とか「景気が悪くて……」などと口にします。しかし、改めて景気が何かを説明しようとすると、意外に難しいのではないでしょうか。
「お金が儲かっているかどうか」というのも、一つの説明ではあります。ただ、この連載で何度か繰り返してきたように、「お金」に注目しすぎると経済の本質を見誤ります。お金が儲かっている、儲かっていないというのは、景気が良い/悪いことの「結果」にすぎないからです。
では、どう考えればいいのか。この連載では、経済の中心にあるのは「生産」、つまり「私たちが働くこと」だと強調してきました。実は景気も同じです。景気が良いとは、「みんなが活発に働いている」、つまり「モノやサービスがたくさん生まれている」という意味です。逆に、失業して働けない人がたくさんいたりして、「モノやサービスを生み出す活動が鈍っている」ことを景気が悪い、と言っているのです。
景気が良い/悪いのものさしになるGDP
ですから、現在の景気が良いのか悪いのかを測るものさしには、生産の大きさを示すGDPがよく使われます。GDPは「国内総生産」という名前の通り、「ある国で1年間にどれくらいのモノやサービスが生み出されたか」を金額で表す指標でした。そこで、ある年とその前年の数字を比べて、生産活動がより活発になっているか、停滞しているかをみればいいのです。
GDPが前の年より増えていた場合、ニュースなどでは「経済成長した」と表現されます。ある国のGDPが100兆円で、次の年が101兆円に増えた場合は、「1%経済成長した」とか「経済成長率が1%だった」というわけです。逆に減った場合は「マイナス成長だった」といいます。後者の場合は、人々が働いて得られた成果が、前の年より小さくなってしまっているのです。
好況と不況は交互に訪れる
この経済成長率が高かったり、前年より率が上昇したりしている時期には、商売でもうけるのも、就職するのも簡単です。逆にマイナス成長の時期や、成長率がだんだん下がっているような時期には生産が停滞しているので事業が赤字になったり、就職や転職が難しくなったりします。一般には前者を「好況期」、後者を「不況期」と呼びます。
不思議なことに、どの国でもこの好況と不況が交互に訪れます。景気は波のように良くなったり、悪くなったりを繰り返しているのです。
 |
「景気の波」 |
日本には無数の会社や団体があり、バラバラにビジネスをしています。私たち個人も思い思いに買い物をしたり、仕事をしたりしているはずで、みんなが相談して同じ行動をとっているわけではありません。普通に考えればそれぞれが打ち消しあって景気は安定しそうなものですが、そうはならないのです。
好況のとき
このナゾを解くカギは、前回お話しした「経済の流れ」にあります。必要が生産を促し、企業が利益を得て……という循環図をもう一度見てみましょう。
生産のきっかけとなる人々の「必要(需要)」は、様々な要因で増えたり減ったりします。例えば、アメリカの景気が良くなれば、日本製品をたくさん買ってくれるようになるでしょう。この場合は輸出するためのモノの必要性が高まるわけです。
すると、企業はそれに合わせて生産を拡大します。自動車や家電がたくさんアメリカに売れれば利益が増えます。利益が増えれば従業員にボーナスをはずむでしょう。生産量を増やすために人を新たに雇ったり、残業時間を増やしたりするので、その分も支払う給料(賃金)が増えるはずです。
こうして利益や賃金が増えると、それ自体が新しい必要を生むことになります。企業は利益を使って新しい工場を建てる(投資)かもしれません。懐が暖かくなった従業員も、「ボーナスが出たからスーツを新調しよう」とか「ちょっと高級なレストランでぜいたくしてみようかしら」(消費)などと思うでしょう。
つまり、新しい必要が生まれるわけで、それ自体が次の生産の拡大につながっていきます。こうした好循環が起きているのが好況の時期なのです。
不況のとき
ところが、この逆が起きることもあります。アメリカで金融機関が倒産したことがきっかけで世界的な不況が起きた「リーマンショック」はそうした例の一つです。
アメリカでモノが売れなくなると、日本からの輸出も減ります。すると日本企業は生産を縮小しなければなりません。雇っていた人をクビにしたり、給料やボーナスを引き下げたりする必要も出てきます。
そんな時に「どんどん工場を増やそう」という企業は少ないですし、個人も財布のひもをキュッと引き締めるでしょう。つまり、投資や消費の必要性が低下するのです。もちろん、そうなるとさらなる生産の縮小が起きてしまいます。こうして経済活動がどんどん鈍くなって不況が訪れるのです。
不況になると、企業や個人が何かのきっかけで明るく前向きな姿勢になるまで、生産は回復しません。本当はみんなが「いっせいのー……」とでも声をかけて一度に消費や投資を増やせば景気は回復するはずなのですが、実際には困難です。企業は「赤字になりそうだからボーナスは増やせない」と考えるでしょうし、個人も「これからボーナスは減りそうだから節約しなければ」と思うからです。
そうした行動がますます景気を冷え込ませて自分たちの首を絞めるのですが、それぞれはごく当然の行動をとっているだけなのでやっかいです。こうした悪い流れを断ち切るには、何か人々や企業を前向きにするようなきっかけが必要です。それは偶然、やってくることもあるし、経済の主要登場人物の一つである「政府」が、人々が前向きなるように道路や橋を造るなどの「投資」を増やす政策が成功する場合もあります。
「景気の気は気分の気」という言葉がありますが、私たちの先行きについての予想が明るいか暗いかで、経済活動も大きな影響を受けるのです。
著者プロフィール:松林薫(まつばやし・かおる)
1973年、広島市生まれ。ジャーナリスト。京都大学経済学部、同大学院経済学研究科修了。1999年、日本経済新聞社入社。経済解説部、東京・大阪の経済部で経済学、金融・証券、社会保障などを担当。2014年、退社し報道イノベーション研究所を設立。2016年3月、NTT出版から『新聞の正しい読み方~情報のプロはこう読んでいる!』を上梓。